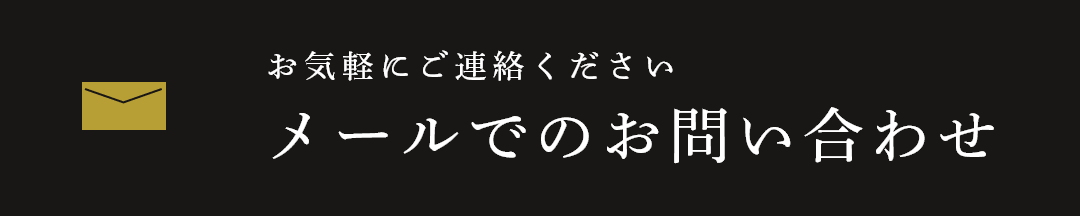-
2021.05.05
【損害賠償】契約不適合による損害賠償請求の要件

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
ネット上でも、契約不適合に関する解説はたくさんありますが、契約不適合を理由とする損害賠償請求の要件について、正確に、というか詳細に解説にするものが見当たらなかったので、私自身の備忘録的な意味も兼ねて(笑)、今回は、この点について、説明させていただきます。
なお、契約不適合責任の免責条項とその有効性については、こちらをご参照ください。
■契約不適合
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、契約不適合責任を追及することができます。その責任追及の手段の1つとして、損害賠償請求があるのです(民法564条、415条1項)。
目的物の「種類」に関する契約不適合とは、品名、形状・色彩、産地、製造業者等に関して合意した内容と異なること、「品質」に関する契約不適合とは、性質、効用、企画、価値等について合意した基準に満たないことをそれぞれ意味します。もっとも、いずれの契約不適合であっても、効果に変わりはありませんので、両者を区別する実益はありません。
また、目的物に数量不足があったすべての場合に、「数量」に関する契約不適合があったことになるわけではありません。契約当事者が、その契約において、「数量」に特別な意味を与え、その数量を基礎として代金額が決定されたような場合にはじめて、「数量」に関する契約不適合があったことになります。
契約不適合に該当するか否かの判断枠組みは、
・当該売買契約が具体的にどのような物を対象としていたか確定する段階と、
・実際に引き渡された物がその契約内容に適合する性質を有していたかを判断する段階
の2段階からなります。売買の目的物が契約の内容に適合しないことについての主張・立証責任は、債務不履行を主張する買主が負います。
■損害と因果関係
また、契約不適合により、買主が損害を被ったこと、契約不適合とその損害との間に相当因果関係があることも要件となります。これらについての主張・立証責任も買主が負います。
■売主の責めに帰すことができない事由
買主は、売主に対し契約不適合責任を追及するにあたり、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によって生じたことを主張・立証する必要はありません。
これに対し、損害賠償請求を受けた売主は、抗弁として、契約不適合が「債務者(売主)の責めに帰すことができない事由」によるものであったことを主張・立証して損害賠償責任を免れることができます(415条2項)。
もっとも、売主に帰責事由がないとして、損害賠償責任を免れるのは、実務上、不可抗力など例外的な場合に限られます。
■追完の催告の要否
契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(562条1項)。
※ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完請求をすることができません(同条2項)。
そこで、買主が売主に対し、契約不適合炉理由として、損害賠償請求をするにあたり、予め、履行の追完を請求する必要があるか、損害賠償請求権と追完請求権との関係が問題となります。
(追完とともにする損害賠償の場合)
まず、売主により追完されても、填補されない損害(たとえば、遅延損害金の賠償や、転売する機会を失ったことによる得べかりし営業利益)の賠償については、追完請求と両立するものであり、予め追完の催告をしなくても、損害賠償請求することができます。
(追完に代わる損害賠償の場合)
これに対し、買主自らが費用をかけて目的物を修補したり、他から適合する目的物を調達した費用など、追完請求とは両立しない損害賠償の請求については、諸説あります。
代金減額請求権も解除権も、原則として追完の催告を要求していることから、損害賠償請求においても、原則として、売主に対し、まずは追完の請求をし、売主に追完する機会を保証しなければならず、それでも売主が追完しなかった場合にはじめて、損害賠償請求することができるとされています(追完請求権の優位性)。
ただし、次の場合は、例外的に、追完の催告は不要となります(563条2項)。
・履行の追完が不能であるとき。
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
・これらの場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。また、契約不適合に関する規定は任意規定ですので、追完の催告を要せず、直ちに、追完に代わる損害賠償請求をすることができる旨の特約は有効です。そこで、買主がこれを望むのであれば、予め売買契約書にこのような特約を明記しておく必要があるわけです。
■権利行使期間
(種類・品質の契約不適合の場合)
買主は、売買目的物に種類ないし品質に関する契約不適合があったことを知った場合、それを知った時(※引渡時からではありません)から1年以内に、売主に対し、不適合の事実を通知する必要があり、この通知をしないと損害賠償請求をはじめ、責任を追及することができなくなります(566条本文)。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、期間の制限を受けません(同条但書)。また、同条は任意規定ですので、特約でこれと異なる定めを設けることができます。
通知は、単に「契約不適合がある」旨抽象的に告げただけでは足りず、細目にわたるまで告げる必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に不適合の種類・範囲を告げる必要があります。他方、不適合責任を追及する意思を明確に告げて、損害額の根拠まで示す必要はありません。
上記権利行使期間の定めは、債権の消滅時効に関する一般準則の適用を排除するものではありませんので、買主が契約不適合の事実を知った時(主観的起算点)から5年、売買目的物の引渡しを受けて(客観的起算点)から10年で消滅時効にかかります(166条1項)。
(数量・権利の契約不適合の場合)
数量ないし権利に関する契約不適合については、特別な権利行使期間の制限の規定はありません。その結果、債権の消滅時効に関する一般準則が適用され、買主が契約不適合の事実を知った時から5年、売買目的物の引渡しを受けてから10年で消滅時効にかかります(166条1項)。
■損害賠償請求権と解除権との関係
買主が契約不適合を理由に売買契約を解除しても、損害賠償請求権は失われるものではなく、損害賠償請求することができます(545条4項)。
また、買主が買主に対し、追完に代わる損害賠償を請求しても、実際に、その弁済を受ける(あるいは損害賠償請求権が他の債務と相殺される)までは、解除権や代金減額請求権は失われません。
-
2021.04.19
【損害賠償】店舗火災や業務上の火災では、損害賠償請求できる?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
近隣から発生した火災被害に遭った場合、自らかけている火災保険により補償を受けるのが一般的でしょう。
しかし、建物に火災保険をかけているだけでは、家財の損害は補償されません。家財も対象とした保険に加入する必要があります。
また、火災被害に遭ったことにより、うつ病になってしまい、通院したり、お店の経営をしていたが休業を余儀なくされ、休業損害が生じたような場合も、このような損害は自らかけている火災保険では、補償されないのが通常です。
そこで、火災保険では補償されない損害について、火災をおこした加害者(失火者)に対し、損害賠償請求したいが、失火者に重過失がないと、損害賠償請求できないと聞くので、果たしてできるだろうかとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
■失火責任法の規定
失火責任法は、「民法709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」と規定しています。そのため、失火者に重過失がなければ、不法行為に基づく、損害賠償請求をすることはできません。
■重過失とは
最高裁昭和32年7月9日判決は、「重大なる過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い注意欠如の状態」を指すものと判示しています。
しかし、下級審裁判例では、形式的には「故意に近い著しい注意欠如」という枠組みを用いながらも、具体的な判断に際して故意と比べて、重大な過失の有無を判断したものはありません。
下級審判決では、火気を扱う事業者について、自らの過失に基づき火災を発生させた場合には、基本的に、重過失があるとして、損害賠償責任が認められています。
行為義務自体が高められている場合、とりわけ、業務上の注意義務違反がある場合には、その違反をもって重過失と判断する傾向にあります。
業務者はたとえ軽過失であったとしても、重過失のある市民と同じレベルのサンクションを受けるべきと考えられているのです。
刑法第117条の2も、「業務上必要な注意を怠ったことによる」過失と、「重大な過失による」失火とを並べて、同等に刑罰を加重していいます(以上、潮見佳男著「不法行為法Ⅰ〔第2版〕」259頁)。
以下、重過失があるとして、損害賠償請求を認めた裁判例を紹介させていただきます。
■東京高裁平成29年9月27日判決
中華料理店の厨房付近から発生した火災により、当該店舗の上の階にあった居酒屋が全焼したことについて、中華料理店の従業員がガスこんろの調理用の火を消し忘れたもので、従業員にはガスこんろの調理用の火が点いたままであるとの認識がなかったものと考えられるが、揚げ物用の油が入った鍋を載せたガスこんろの火が点いていることを忘れて、その場を離れれば、火災に至る可能性があることは、料理人である従業員において極めて容易に予見することができる事柄であり、従業員には、揚げ物用の油が入った鍋の使用を終える際、ガスこんろの火が消えていることを確認すべき注意義務があるところ、その注意義務はわずかな注意を払えば履行することが十分に可能な内容というべきである。それにもかかわらず、従業員は、ガスこんろの調理用の火を消し忘れてその場を離れ、その結果、火災になったというのであるから、その失火については、従業員に重大な過失があったとするのが相当であると判示しています。
■その他の厨房器具に関する火災で損害賠償を認めた裁判例
その他にも、次の厨房器具に関する火災事案では、いずれも重過失があるとして、損害賠償請求を認めています。
(東京地裁昭和56年5月19日判決)
ガスコンロでから揚げを調理している途中で調理室を出て、料理の下準備をしているうち、ガスコンロの火がから揚げの油に引火して火災となった事案(広島地方裁判所昭和48年3月26日)
パン焼炉から小火が起こり一応消化したものの、パン焼炉周辺に散乱する鋸屑への水撒き、残火の確認をしなかったために、付近に堆積してあった鋸屑に引火し火災になった事案(東京地方裁判所42年8月2日判決)
業務用トースターを使用後電源を切らず、帰宅したため、上方の棚板に着火し火災となった事案■東京地裁令和元年6月13日判決
宗教法人が神宮から譲与を受けた鳥居材を当該被告が預かり保管中、その作業所において発生した火災により上記鳥居材が焼損した事案につき、元代表者は、作業所内には多数の木材が保管されており、同所に設置された焼却炉内の火が消火されずに残っていれば、そこから火の粉が飛ぶなどして周囲の木材に燃え移り、火災が発生する危険のあることを容易に予見することができたにもかかわらず、焼却炉内の火を確実に消火せずに帰宅したことによって、焼却炉を火元とする本件火災を発生させたことが認められ、元代表者には、失火責任法上の重過失があったものと認められると判示しています。
■東京地裁平成29年9月4日判決
焼肉店における無煙ロースターによる火災につき、「被告は、火力を扱う事業者として、火災等の事故を発生させないよう、メーカーの定めるロースターの使用方法を遵守して火災等の事故を発生させないようにする注意義務を負っていた」としたうえ、排気に含まれる油脂分を吸着しダクト内に油脂分が入り込むことを防ぐ機能を持つオイルキャッチャーを使用せず、当該機能を有しない金属たわしで代替し、また、高温の排気がダクトに入り込むことを防止しダクト火災のリスクを軽減させる機能をもつファイヤーダンパーを設置せず、さらに、被告が防火ダンパーやダクト内について、十分な清掃をしていなかったこと等を指摘して、「被告は、重要かつ基本的な注意義務を怠り、本件火災を惹起させたというべきであるから、重過失があるというのを免れない」と判示しています。
■東京地裁平成27年1月15日判決
家族で営む鋳物製造工場からの出火により被害を受けた近隣住民らが損害賠償請求した事案につき、同判決は、被告らが作業を終えてから、放置した高温の鋳型の周辺について段ボール等が存在していたにもかかわらず、居室で休み、高温の鋳型について特段の監視を行っていなかったと認定し、適切な監視を行っていたならば、段ボールが鋳型に接触して本件火災が発生したとしても、出火直後に段ボールを撤去したり、消火の措置を講じたりするなどすることができたものというべきであると判示しています。
そして、被告らにおいてわずかの注意さえすれば、たやすく火災の結果を予見することができたというべきであるのに、漫然と段ボール箱が近くにあるのに高温の鋳型を放置して、その監視をしなかったものというべきであるから、被告らの注意義務違反の程度は重大であるとして、損害賠償請求を認めています。
■東京地裁平成26年4月25日判決
工場内のH鋼をアセチレンガス切断機で溶断する作業をしていたところ、切断機の炎が断熱材に燃え移り火災が発生し倉庫等が延焼により焼失した事案において、同判決は、作業員には、ウレタン等の可燃性の断熱材が付着したH鋼をアセチレン切断機で切断するに当たって、断熱材を十分に除去することなく溶断作業をした注意義務違反があり、断熱材が残存しているか否かは目視等により容易に確認できたし、また、目視できない箇所に断熱材が残存している可能性も容易に認識しえたのに確認を怠っており、また、普段ガス溶断作業していた者らを待てない事情も認められず作業員はガス溶断作業をすべきでなかったとして、重大な過失があったとして、損害賠償請求を認めています。
■東京地裁平成18年11月17日判決
アセチレンガスによる切断作業の業者が周囲に可燃物がないかの確認を怠り火災を発生させたケースにつき、当該作業が爆発又は火災の発生する危険性の高い行為であるため、業者は十分な注意義務を負っていたとし、ガスバーナーの炎が当たるおそれのある板壁の部分に鉄板を差し込むという防火措置を講じていたものの、その防火措置が不十分であるとして、当該作業に業として従事していたものであることをも勘案して、重過失を認めています。
■東京地裁平成8年10月18日判決
ラーメン店舗の火災事故につき、店舗内装工事の請負人には、ガスレンジの設置に当たり、同判決は、条例の設置基準に依拠し、壁との距離の確保等につき十分確認し火災の発生を防止すべき注意義務があるところ、断熱材が使用されていたとは認められないのに、壁との距離を条例の設置基準に違反してガスレンジを設置したことは注意義務に著しく違反する重大な過失があったとして、損害賠償請求を認めています。
■東京地裁平成4年2月17日判決
印刷業者が業務上日常的に使用するガソリンを栓をしないままの瓶に入れて燃焼中の石油ストーブに近接した足元の床上に置いていたため、右瓶が倒れてガソリンがストーブに引火して火災が発生した事案につき、印刷業者は、引火性の強い危険物であるガソリンを日常的に使用していたのであるから、火気を使用するに際してはガソリンの取扱いについて万全の注意を払うべき義務があるにもかかわらず、ガソリンの入った瓶から約七五センチメートルしか離れていないところにストーブを置いてこれを使用し、ストーブが燃焼中であったのに、瓶を、栓をしないままで、ストーブに近い側であってしかも何かの拍子に触れるなどして倒す可能性の高い足元の床に置いていたというのであるから、印刷業者は、通常人の当然用いるべき注意義務を著しく欠いたものというべきであり、その注意義務違反の程度は、失火責任法所定の重過失に該当するものといわなければならないと判示しています。
-
2021.04.13
【クーリング・オフ】法人や事業者はできない?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
中小企業庁のホームページでも、「事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません」と説明されています。それは基本的には正しいですが、正確ではないかもしれません。

■根拠条文
訪問販売などについては、特定商取引法において、クーリング・オフの制度が定められています(9条)。
もっとも、「営業のためにもしくは営業として締結するもの」については、特定商取引法のすべての条項の適用が除外され、クーリング・オフも適用されません(26条1項1号)。
この適用除外の規定があることから、「事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません」と説明されているわけです。
■適用除外の解釈
しかし、同号の趣旨は、契約の目的・内容が営業のためのものである場合に特定商取引法が適用されないという趣旨であって、契約の相手方の属性が事業者や法人である場合を一律に適用除外とするものではありません。
例えば、法人や事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法が適用され、クーリング・オフもできる場合があるのです。
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、特定商取引法が適用される可能性が高いです。
令和2年3月31日付通達でも、以上のように説明されています。
「営業のためにもしくは営業として締結するもの」にあたるか否かは、形式的に、契約書上の当事者が誰かではなく、実質的に事業者の営業の目的との関連、契約の目的・内容・用途、使用形態、支払が営業経費か個人の家計からか、反復継続した取引か、事業者の事業規模などにより判断されるべきものです。
■クーリング・オフを認めた裁判例
法人や事業者が契約当事者の場合にも、クーリング・オフを認めた裁判例として、以下のものがあります。
【大阪高裁平成15年7月30日判決】
消火器の訪問販売業者が、自動車販売会社に対し、消火器38本を販売した事案につき、原告会社は、自動車の販売等を業とする会社であって、消火器を営業の対象とする会社ではないから、当該契約は「営業のためにもしくは営業として締結するもの」ということはできないとして、クーリング・オフを認めています。
【名古屋高裁平成19年11月19日判決】
個人で印刷画工を営む者が、通信機器(事務所用電話主装置・電話機)のリース契約を締結した事案につき、控訴人は、専ら賃金を得る目的で1人で印刷画工を行っていたに過ぎず、その規模は零細であったこと、経営困難との理由で、契約締結の約4か月後に廃業届を提出していること、控訴人の事業規模や事業内容からしても、従前から使い続けていた家庭用電話機が1台あれば十分であったといえること、控訴人は事業といっても印刷画工を専ら1人で、手作業で行うような零細事業に過ぎず、かつ、控訴人自身パソコンを使えないというのであって、リース対象の通信機器は、控訴人が行う印刷画工という仕事との関連性も必要性も極めて低いことからすると、当該リース契約は、控訴人の営業のために若しくは営業として締結されたものであると認めることはできないとして、クーリング・オフを認めています。
【東京地裁平成27年10月27日判決】
家族の住む住宅兼店舗で喫茶店を営む個人が電話機、ファクシミリのリース契約を締結した事案につき、被告は喫茶店を経営しているが、被告と妻のみが従事し、一日の来客は三〇人程度で、店舗を利用しているのは地元の固定客であって、電話番号は電話帳に記載していないこと、営業の手段として当該電話機及びファクシミリの有益性は希薄であり、したがって電話の利用は個人的使用が中心であって、ファクシミリも子どものクラブ活動等の連絡に利用しており、業務のために全く利用していないこと、当該リース契約締結の経緯、被告の営業の規模、内容、リース物件の営業使用の必要性や頻度を考慮すると、当該リース契約の契約書等に屋号を記載していること、リース料が被告の営業経費に通信費として計上されていること、インターネット上の飲食店検索サイトの店舗基本情報や、地元の飲食店マップに建物の電話番号が掲載されていることを考慮しても、当該リース契約は「営業のために若しくは営業として」締結したものとは認められないから、特商法の適用除外には該当しないとして、クーリング・オフを認めています。 -
2021.04.08
【不動産売買】ローン特約に基づく解約が認められない場合
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
不動産売買において、買主が売買契約締結後、購入意欲をなくしてしまったが、手付金の放棄や、違約金請求を免れるために、ローン特約を悪用し、意図的に融資を受けられないようにし、売買契約を無条件で解除しようとする場合があります(いわゆる、ローン壊し)。
このように、買主側に不誠実な対応がある場合には、ローン特約による解約が認められない場合があります。

■ローン特約とは
ローン特約とは、不動産売買契約において、買主が金融機関から融資を受けることができない場合に、無条件で売買契約を解除し、売主に支払った手付金の返還を求めることができる旨の特約をいいます。
マンションや住宅の買主は、金融機関から融資(住宅ローン)を受けて売買代金を支払うことが多いですが、買主に落ち度はないのに、審査が通らず、融資を受けることができなかった場合にまで、手付金を放棄したり、損害賠償を負わなければいけないのは、買主に酷であることから設けられている特約です(東京地裁平成16年8月12日判決等)。
■ローン特約による解約の効力が争われる場合
このように、融資を受けることができなかった場合、ローン特約に基づき、買主は、無条件で売買契約を解除できるのですが、次のような場合には、売主からローン特約による解約の効力を争われ、違約金を請求される場合があります。
① 買主が融資成立への努力義務を怠った場合
② 買主の責めに帰すべき事由によって融資が成立しなかった場合
③ ローン解約できる期限を過ぎた場合■買主の努力義務
買主は売買契約締結後、融資成立に向けて誠実に努力すべき、信義則上の義務を負い、これを怠った場合には、ローン特約に基づく解除をすることができません。
買主の努力義務としては、次のようなことが挙げられます。
・速やかに所定の融資申込書及び必要書類を提出すること
・融資審査手続において、金融機関からの照会があれば、誠実に対応すること(適切に応答し、事実に反する説明をしない)
・金融機関から、合理的な増担保の要求があれば、これに応じること■ローン特約による解約を認めなかった裁判例
(東京地裁平成10年5月28日判決)
同判決は、以下の事情により、ローンが実行されなかったことから、ローン解約を認めず、買主からの手付金返還請求を否定しました。
・共同買主XとA(妹)のうち、Aが共同買主という立場にあったにもかかわらず、連帯保証人になることを拒み、さらには共同買主となることまで難色を示したこと
・同時期に、Xが当初申告しないでいた高血圧症を自主的に申告したことによって、団体信用生命保険の審査が最終的に否決されていること
(東京地裁平成26年4月18日判決)
同判決は、一般にローン特約が売買契約に付される場合、売買契約の締結に先立ち買主側で金融機関に事前相談を行い、融資の見通しを示された上で売買契約を締結し、この見通しに沿って融資の申込み(本申込み)を行うことが予定されていることからすると、ローン特約が適用される融資の申込みとは、金融機関から示された見通しに沿った内容での申込みであるところ、買主らは、示された融資条件に沿った融資の申込みをしたということはできないとして、ローン特約に基づく解除を認めませんでした。
-
2021.03.30
【土地賃貸借】更新料を支払わないと、借地契約は解除されるか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は土地の賃貸借契約において、更新料支払の合意がなされているにもかかわらず、借地人が更新料を支払わなかった場合に、賃貸借契約を解除できるかについて、説明させていただきます。

■最高裁判例
最高裁昭和59年4月20日判決は、「土地の賃貸借契約の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人に対し更新料を支払う例が少なくないが、その更新料がいかなる性格のものであるか及びその不払が当該賃貸借契約の解除原因となりうるかどうかは、単にその更新料の支払がなくても法定更新がされたかどうかという事情のみならず、当該賃貸借成立後の当事者双方の事情、当該更新料の支払の合意が成立するに至つた経緯その他諸般の事情を総合考量したうえ、具体的事実関係に即して判断されるべきものと解するのが相当である」と判示しています。
そして、「原審の確定した前記事実関係によれば、本件更新料の支払は、賃料の支払と同様、更新後の本件賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、その賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているものというべきであるから、その不払は、右基盤を失わせる著しい背信行為として本件賃貸借契約それ自体の解除原因となりうるものと解するのが相当である。」と判示しました。
ただし、当該事案は、借地人に建物の無断増改築、借地の無断転貸、賃料支払の遅滞等の賃貸借契約に違反する行為があったが、調停において、これら借地人の行為を不問とし、紛争予防目的での解決金をも含めた趣旨で更新料の支払を合意したものと認められると事実認定されており、このような具体的な事情とは無関係に、一般論として、更新料の不払いにより、借地権契約が解除できるかについては、注意する必要があります。
■東京地裁平成27年4月10日判決
賃貸人が更新について賃借人に連絡した際に、具体的な額を提示することなく、話し合いを求めたにもかかわらず、賃借人は一方的に支払を拒絶していること、賃借人は、更新料支払条項を十分に理解し認識した上で、賃貸借契約の契約証書に署名押印しており、賃貸人は、更新時期にも同契約証書の作成経緯について説明し、再度、話し合いによる解決を求めたにもかかわらず、賃借人はかたくなに本件更新料支払条項の効力を否定して話し合いにも応じなかったことなどの事情からすれば、賃貸人及び賃借人間の信頼関係が破壊されたと認められ、更新料の不払は本件賃貸借契約の解除原因となる旨判示しています。
■東京地裁平成29年9月28日判決
同判決は、建物賃貸借契約に関するものですが、「賃貸人としては、賃借人が更新料を支払うことを合意したからこそ賃貸借契約を2回にわたり更新したのであり、他方、賃借人としても、更新料を支払うことを合意して賃貸借契約の更新を得たのであるから、更新料の支払は、更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているものといえる。」
「したがって、更新料の不払は、不払の態様、経緯その他の事情からみて、賃貸人・賃借人間の信頼関係を著しく破壊すると認められる場合には、更新後の賃貸借契約の解除原因となり得るものというべきである」旨判示しました。
そして、「更新料の不払の期間が相当長期に及んでおり、不払の額も少額ではないこと、賃借人が合理的な理由なく更新料の不払をしており、今後も当該不払が任意に解消される見込みは低く、当事者間の協議でその解消を図ることも期待できないことなどに照らすと、更新料の不払は賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤を失わせるに足る程度の著しい背信行為であるということができる。」し、賃貸借契約が解除により終了したとして、建物の明渡を命じています。
■契約解除を否定した裁判例
他方、東京地裁平成25年5月15日判決は借地契約の解除を否定していますが、更新の際に具体的な額の更新料を支払うことを約したことを認めるに足りる証拠がなく、更新に際して更新料を支払う義務を負うものではないことを理由とするものです。
-
2021.03.17
【建物賃貸借】連帯保証人による保証契約の一方的な解除を認めた裁判例
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
賃借人が長期間家賃を滞納しているけど、いずれ連帯保証人から支払ってもらえればいいなどと考え、賃借人に対し契約解除をし、明渡請求することを漫然と放置している大家さんはいらっしゃらないでしょうか。
そんなことをしていると、連帯保証人から、保証契約を解除され、滞納家賃の回収ができなくなってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
今回は、連帯保証人による保証契約の一方的な解除を認めた横浜地方裁判所相模原支部平成31年01月30日判決をご紹介させていただきます。

■ 事案の概要
市営住宅を賃借するにあたり、被告(賃借人の母)が連帯保証しました。しかし,賃借人は当時から生活保護を受給しており,ほどなく賃料支払を怠るようになって,賃借人と接触・連絡もとれない状態で契約解除ができる3か月分の滞納が生じたものの,原告(賃貸人)は,賃貸借契約を解除せず,連帯保証人である被告に上記滞納額の分割納付を求めました。その後も賃借人は賃料をまったく支払わず,滞納分が累積し,被告は,原告に対し,保証責任の拡大を防止するため,再三,賃借人を退去させて欲しいと伝えたが,原告は応じず,賃貸借契約から約14年が経過した時点で,ようやく建物明渡訴訟を提起し,被告に対し,滞納賃料,違約金,賃料相当損害金の合計約332万円の支払を求めました。
■ 判決の要旨
賃借人が賃料の支払を怠り,将来も支払う見込みがないことが明らかで,賃借人ともまったく接触・連絡もとれず,被告が保証責任の拡大を防止するため再三訴外賃借人を退去させて欲しいとの意向を示していたにもかかわらず,原告は,賃貸借契約の解除及び明渡しの措置を行わず,そのまま使用を継続させ滞納賃料等を累積させていたことから,原告には連帯保証契約上の信義則違反が認められ,保証人からの一方的意思表示による解除が許容されるとし,契約締結から12年以上が経過して被告が賃借人の退去を求めた時点で,黙示的な解除の意思表示がなされたと認定し,以後の保証債務の履行を免れると判断しました。
また,仮に上記時点での解除の有無にかかわらず,上記時点以降の保証債務の支払を請求することは,権利の濫用として許されないと判断しました。
■ 判断理由
判決は、「期間の定めのない継続的な建物賃貸借契約を締結する賃貸人、保証人は、保証契約を締結する時点で、債務の拡大の可能性・危険性・保証人側からの債務拡大の回避・防止が困難であるという事情について保証契約の前提ないし内容として、当然認識されているものと考えられ、また、継続的契約については、当事者間の信頼関係を基礎としていることをも考慮すると、賃貸人も保証契約上不当に保証人の債務が拡大しないようにする信義則上の義務を負担していると認めるべきである。」と判示しました。
そして、
①上記保証契約締結後相当な期間が経過し、
②賃借人が賃料の賃料の支払を怠り、将来においても賃借人が債務を履行する見込みがないか、
③保証契約締結後に賃借人の資産状態が悪化し、これ以上保証契約を継続させると、保証人の賃借人に対する求償権の行使も見込めない状態になっているか、
④賃貸人が上記事実を保証人に告知せず、保証人が上記事実を認識し、何らの対策も講じる機会も持てないまま、未払賃料等が累積していったり、
⑤上記のような事情のため、保証人が保証債務の拡大を防止したい意向を有しているにもかかわらず、賃貸人が依然として賃借人に上記建物の使用収益をさせ、賃貸借契約の解除及び建物明渡しの措置を行わずに漫然と未払債務を累積させているような場合には、
賃貸人の前記保証契約上の信義則違反により、賃貸人が保証契約の解除により信義則上看過できない損害を被るなどの特段の事情がない限り、保証人は、賃貸人に対する一方的意思表示により、上記保証契約を解除し、以後の保証債務の履行を免れることができると解すべきである。
また、少なくとも、前記のような事情がある場合、仮に保証人からの解除の意思表示がなかったとしても、賃貸人の保証人に対する保証債務の履行請求は、信義則に反し、権利の濫用として一定の合理的限度を超えては許されないと解すべきであると判示したのです。
-
2021.03.12
【マンション管理】役員候補者を制限する管理規約の有効性
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、マンション管理組合の役員である理事および幹事について、「立候補者が役員候補者として選出されるためには、理事会承認を必要とする」旨の管理規約の条項(以下、「本件条項」といいます。)の有効性について判断した裁判例(東京高裁平成31年4月17日判決)をご紹介させていただきます。

■ 事案の概要
原告らがマンション管理組合の役員として立候補したものの、理事会が理事ら全員の賛成により、本件条項に基づき、これを承認しない旨の決定したことから、原告らが役員立候補権を侵害されたとして、理事ら全員を被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
■ 本件条項の有効性
高裁は、本件条項について、明示されてはいないものの、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて明らかに管理組合の理事としての適格性に欠ける者については、理事会が立候補を承認しないことができるという趣旨であると解され、その限度で本件条項は有効であると判示しました。
そして、理事会が上記の裁量の範囲を逸脱して、立候補を認めない旨の決定をした場合は、立候補者の有する人格的利益を侵害するものとして、違法性を有すると判示したのです。
上記は、区分所有法には、規約は、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないと定められており(30条3項)、これを害するような規約の定めは無効であることを理由とした判断です。
■ 理事らの過失は否定
もっとも、高裁判決は、次の理由から、役員立候補者の承認をしない旨の決定をした理事らの過失を否定し、原告らの損害賠償請求を認めませんでした。・本件条項には、立候補者を承認するか否かの基準が明示されていないこと。
・理事会の裁量を制限するような定めはないこと。
・承認をしない旨の決定をした時点では、本件条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていなかったこと。
・理事らが法律やマンション管理について専門知識を有するものではなかったこと。
・理事としての報酬も多額ではないこと。ただし、規定に承認するか否かの基準が示さされていたり、理事が法律に関し専門的知識を有していたり、この判決が出た以上、今後は、違法な決定をした場合には、過失が認められ、損害賠償責任を負うおそれがありますので、注意が必要です。
なお、違法な決定に関与しても、過失がないと判断した要素、判断過程は、今後の実務の参考になります。
-
2021.03.03
週刊文春にコメントが掲載されます
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
先日取材を受けまして、明日3月4日発売の週刊文春(2021年3月11日号)に私のコメントが掲載されます。
皆様の期待を裏切って大変申し訳ありませんが、私が不祥事を起こして、文春砲の餌食になったわけではありません(笑)。

騒音トラブルに関する記事です。
誌面の関係があって、正確なコメントを掲載することはできなかったのですが、
騒音が受忍限度を超えるか否かの判断にあたっては、
単に音の大きさだけでなく、
・音の種類や発生頻度、
・影響の程度
・音を発生させる行為の公益上の必要性
・所在地の地域環境
・関係者同士で話し合われた内容・経緯
・騒音元の講じた防止措置の有無や内容
等を総合的に考慮して判断されることを補足しておきます。
-
2021.02.25
【不動産】移転登記の訴訟等にかかった弁護士報酬を損害賠償請求できるか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
土地の売買契約を締結したにもかかわらず、売主が土地の引渡や所有権移転登記手続をしないため、買主が、売主に対し、これら債務の履行を求める訴訟提起・追行や、保全命令、強制執行の申立てを弁護士に依頼した場合、これらにかかった弁護士報酬(弁護士費用)を損害賠償請求することはできるでしょうか。
最高裁令和3年1月22日判決は、このような場合に、弁護士報酬について、債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないとして否定しました。

■ 事案の概要
当該判決の事案は以下のようなものです。
買主は、売主である株式会社との間で、売主の所有する土地を9200万円で買い受ける旨の売買契約を締結し、売主に対して手付として500万円を支払いました。残代金全額の支払時に土地の所有権が買主に移転するものとされ、売主は、土地につき、自らの費用で、地上建物を収去し、担保権等を消滅させ、境界を指示して測量した上で、残代金の支払と引換えに引き渡すものとされました。
しかし、その後間も無く、残代金の支払期限前に、売主は営業を停止し、その代表者が行方不明となったため、買主は、弁護士に依頼して、処分禁止の仮処分の申立、所有権移転登記手続及び地上建物を収去して明け渡すことをを求める訴訟を提起し、上記判決に基づいて強制執行を申し立てるなどしました。
■ 否定した理由
最高裁は、以下の3つの理由から、訴訟提起等にかかる弁護士報酬を損害賠償請求することはできないと判示しました。
① 契約当事者の一方が他方に対して契約上の債務の履行を求めることは、不法行為に基づく損害賠償を請求するなどの場合とは異なり、侵害された権利利益の回復を求めるものではなく、契約の目的を実現して履行による利益を得ようとするものである。
② 契約を締結しようとする者は、任意の履行がされない場合があることを考慮して、契約の内容を検討したり、契約を締結するかどうかを決定したりすることができる。
③ 土地の売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務は、同契約から一義的に確定するものであって、上記債務の履行を求める請求権は、上記契約の成立という客観的な事実によって基礎付けられるものである。
そうすると、土地の売買契約の買主は、上記債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても、売主に対し、これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないというべきである。
なお、当該事案では、弁護士が、買主の代理人として、土地の測量等を土地家屋調査士に依頼し、その費用を支払ったりしていますが、最高裁は、このような事務は、買主が自ら土地を確保し、利用するためのものにすぎないから、同事務に係る弁護士報酬についても、買主が売主に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有するということはできないと判示しています。
■ 考察
裁判実務上、交通事故など不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、それにかかった弁護士報酬として、認容額の1割程度(実際に支払った金額ではありません)の損害賠償請求が認められています。
しかし、本件事案では、弁護士報酬の損害賠償請求が否定されました。その違いはどこにあるのでしょうか。
法定構成・根拠の違い、すなわち、不法行為に基づく損害賠償請求の場合には認められるが、契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の場合には認められない、と結論づけるのは短絡的で、間違っていると思います。
契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の場合でも、たとえば安全配慮義務違反を理由とする場合には、①の理由との関係でいえば、侵害された権利利益の回復を求めるものと言えますし、実際に、裁判例で、弁護士報酬の損害賠償請求を認めたものは多数存在します。
私は、③の理由が大きく、基本的に、損害賠償請求権が成立するか否かや、成立するとして、損害額をどのように算定するかについて、弁護士による専門的な判断を必要とする場合には、弁護士報酬の損害賠償請求が認められるが、契約内容から、債務の履行請求権が一義的に確定し、明確に導かれる場合には、弁護士報酬の損害賠償請求は認められないのではないかと思います。
後者の場合にも、弁護士に依頼して、訴訟等を遂行することが多くありますが、日本ではまだ弁護士報酬について敗訴者が負担する制度が導入されておりませんし、そのような程度では、弁護士報酬について損害賠償請求することはできないということです。
実際、売買代金請求訴訟や、貸金返還請求訴訟などでは、それに加えて弁護士報酬を請求することは認められていませんが、本件の土地の引渡や所有権移転登記請求訴訟も、これらと同様ということです。
また、②の理由、予測できない事件・事故により損害を被る不法行為の場合とは異なり、契約においては、締結前に、相手方の資力や信用を調査したり、契約が履行されない場合に備えて、契約内容を検討・交渉の上、合意したり、場合によっては契約を締結しないことにより、リスクヘッジすることができるという観点も示唆にとみます。
■ 本判例の意義
当該事案の原審では、弁護士報酬の損害賠償請求も認められていましたが、最高裁はこれを破棄自判しました。このように、弁護士報酬の損害賠償請求が認められるか否かについては、実務家でも悩み、判断が分かれるケースがありますが、最高裁が示した理由などから、これが認められる場合と認められない場合とがより明確になったといえます。
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (3)
-
2022年 (6)
-
2021年 (30)
-
2020年 (9)
-
2019年 (8)
-
2018年 (43)
-
2017年 (29)
-
2016年 (38)
-
2015年 (59)
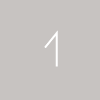
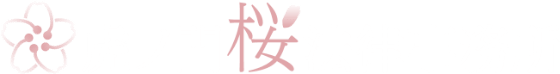
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)