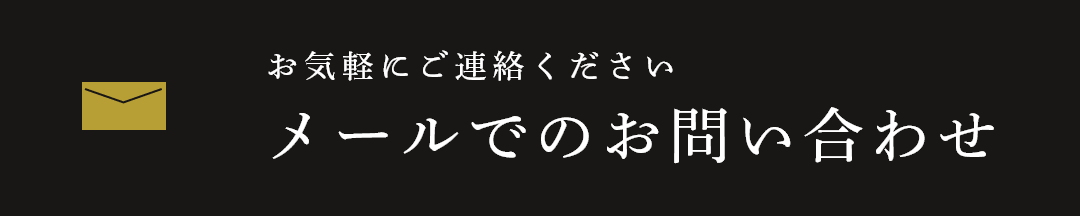-
2019.02.19
【離婚】不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
本日(平成31年2月19日)、不貞行為の慰謝料請求に関し、注目すべき最高裁判決が出ました。
不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を否定したのです。第1審でも、控訴審でも、慰謝料請求が認められたものを、最高裁が破棄自判したのが衝撃的でした。

■事案の概要
Y(不貞相手)は、平成21年6月以降、A(妻)と不貞行為に及ぶようになりました。
平成22年5月ころ、X(夫)は、YとAとの不貞行為を知りましたが、その頃、AはYとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けました。
それから4年近くが経過した平成26年11月ころ、AとXとは別居し、平成27年2月に調停離婚が成立しました。
その後、XがYに対し、不貞行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったとして、離婚に伴う慰謝料請求訴訟を提起したものです。
Xが、離婚をやむなくされたことを理由とし、不貞行為自体を理由とする慰謝料請求をしなかったのは、YとAとの不貞行為を知ってから3年以上が経過しており、消滅時効の援用をされたからと考えられます。
■最高裁判決
最高裁は、次のように判示して、不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を、原則として、否定しました。
「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」
「したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」
一般論として、不貞相手に対する、不貞行為それ自体を理由とする慰謝料請求は認めていることに注意が必要です。これを否定しているわけではありませんので、勘違いしないようにしてください。
そして、不貞相手が例外的に、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負う場合を、「当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示しました。
■考察
上記のような特段の事情が認められるケースは極めて例外的であり、今後、不貞相手に対し、夫婦が離婚したことを理由とする慰謝料請求をするのは難しくなるでしょう。
不貞行為が原因(の1つ)として、夫婦が離婚するに至ったことは、慰謝料額を決める(増額する)考慮要素として主張するしかありません。
いずれにせよ、配偶者の不貞行為を知った時は、消滅時効にかかる前に慰謝料請求すべきです。
-
2019.02.14
【企業法務】顧客情報の利用は、不正競争防止法に違反にするか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
同業他社を退職した従業員を採用したところ、その同業他社から、顧客情報を利用して営業活動を行なっており、これが不正競争防止法に違反するなどと警告を受けた。・・・そんな相談が顧問先から時々寄せられます。 ここでいう顧客情報とは、取引先の名称や住所、電話番号、ファックス番号、担当者の氏名、メールアドレスなどです。

顧客情報の利用が不正競争防止法に違反するか否かは、顧客情報が同法の保護対象となる「営業秘密」に該当するか否かによります。「営業秘密」に該当しなければ、不正競争防止法違反に問うことはできません。
■「営業秘密」とは?
不正競争防止法における「営業秘密」とは、次の3つの要件を全て満たすものとして定義されています(第2条6項)。
① 秘密として管理されていること(秘密管理性)
② 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③ 公然と知られていないものであること(非公知性)
このうち、紛争において最も争点となるのは、①の秘密管理性です。
■秘密管理性を満たす場合とは?
秘密管理性が認められるには、会社や経営者が主観的にその情報を秘密にしたいと考えているだけでは足りません。その情報が客観的に秘密として管理されていると認められる状態にある必要があります。
裁判例では、秘密管理性の判断にあたり、次の2つの要素が考慮されています。
イ 当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
ロ 当該情報にアクセスした者が秘密であることを認識できるようにされていること(認識可能性)
経済産業省の営業秘密管理指針(平成27年1月全面改訂)でも、これら2つが重要な要素とされていますが、それぞれ別個独立の要件ではなく、前者の「アクセス制限」は後者の「認識可能性」を担保する一つの手段であると考えられると説明されています。
したがって、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる場合には、十分なアクセス制限がないということだけを理由に秘密管理性が否定されることはないかもしれません。もっとも、何らの秘密管理措置が取られていない場合には、秘密管理性要件は満たしません。
■裁判例
ここで仕入先情報(仕入先の名称や住所、電話番号、ファックス番号、担当者の氏名、メールアドレス、取扱商品の特徴)に関する、不正競争防止法上の「営業秘密」該当性が問題になった裁判例(東京地裁平成20年11月26日判決)をご紹介させていただきます。
この裁判例は、秘密管理性の認定においては、主として、認識可能性とアクセス制限が判断要素となる旨、従前の判断基準の枠組みを踏襲した上で、
・原告においては、アルバイトを含め従業員でありさえすれば、そのユーザーIDとパスワードを使って、サーバーに接続されたパソコンにより、仕入先情報が記載されたファイルを閲覧することが可能であったこと
・そのファイル自体には、情報漏洩を防ぐための保護手段が何ら講じられていなかったこと
・従業員との間で締結した秘密保持契約も、その対象が抽象的であり、仕入先情報がそれに含まれることの明示がされていないこと
・その他、原告において、従業員に対して、本件仕入先情報が営業秘密に当たることについて、注意喚起をするための特段の措置も講じられていなかったこと
・仕入先情報の内容の多くが、インターネット等により一般に入手できる情報をまとめたものであること
・証拠上、原告に、個々の仕入先を秘匿しなければならない事情も窺われないこと
などを理由に、仕入先情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当することを否定しています。
■秘密保持契約との関係
会社と従業員とが秘密保持契約を締結している場合には、顧客情報の利用が不正競争防止法に違反するか否かとは別に、秘密保持契約に違反するか否かが問題となります。
この点については、別の機会に改めてご説明させていただきます。
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (3)
-
2022年 (6)
-
2021年 (30)
-
2020年 (9)
-
2019年 (8)
-
2018年 (43)
-
2017年 (29)
-
2016年 (38)
-
2015年 (59)
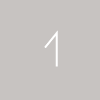
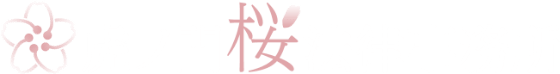
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)