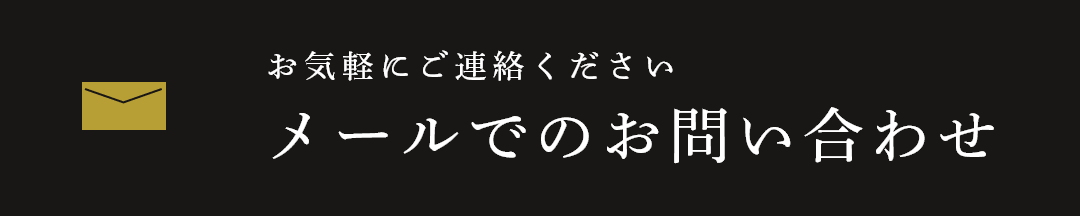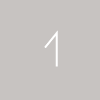二段の推定
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
訴訟において、相手方が、契約書や合意書・覚書など文書の成立の真正を認めるときは、それ以上、その文書が真正に成立したことを立証する必要はありません。しかし、相手方から文書の成立の真正が争われた場合には、挙証者が、その文書が真正に成立したことを立証する必要があります。
もっとも、文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと、事実上推定されます(一段目の推定)。
さらに、この一段目の推定によって、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定める民事訴訟法第228条4項の要件を充足し、文書全体の成立の真正が法律上推定されます(二段目の推定)。
これを民事訴訟法の分野で、「二段の推定」といいます。
ですので、文書が真正に成立したことを争う相手方としては、この二段の推定がされることを妨げ、文書が真正に作成されたのか否かわからない状態にしなければなりません。相手方の反証としては、次のものが考えられます。
①文書に押印された印影が、文書の名義人の印章によって顕出されたものではないとして、一段目の推定の前提事実自体を争う。
②文書の名義人の印章が第三者に盗用された、あるいは、文書の名義人が第三者に印章を預けていたところ、無断で冒用されたなどと、一段目の推定が覆る事情を立証する。
③押印した後に、本文が挿入・削除(文書の変造)されたとして、二段目の推定が覆る立証をする。
ところで、挙証者は、必ず民事訴訟法第228条4項による推定によらなければならないということはありません。他の間接事実や、文書作成に立ち合った第三者の証人尋問等によって、文書が名義人の意思に基づいて作成されたことを直接立証してもよいのです。
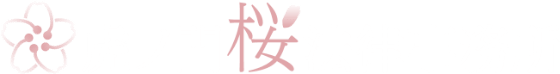
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)