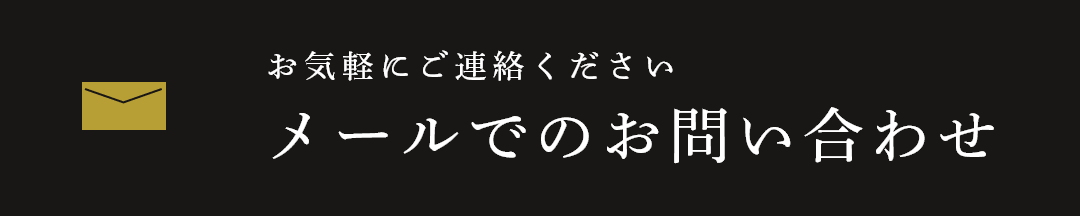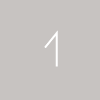司法取引について企業担当者が知っておくべき7つのこと
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
ついに本日平成30年6月1日から、日本で初めて、「司法取引」が導入されました。
司法取引の対象犯罪には、法人への罰金刑のある経済犯罪が広く含まれており、実行役の社員が上司の指示を明かして罪の減免を図るケースなどが想定され、司法取引導入による、企業活動へのインパクトは大きいものがあります。
そこで、今回は、司法取引について、企業の役員や法務担当者が知っておくべき基礎知識について、簡潔にご説明させていただきます。
1 司法取引の概要
今回日本で導入された司法取引は、他人の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、自身の刑事処分を軽くするというものです。
捜査・公判協力型と呼ばれるものであり、情報提供の対象は、あくまで他人の犯罪に関するものに限られます。典型的なものとして、被疑者・被告人が自ら関与した犯罪について、その共犯者に対する訴追に協力することが想定されています。
自己負罪型司法取引を認めている米国と異なり、企業や従業員が自らの犯罪を自白しても、それは司法取引の対象にはなりませんので、ご注意ください。
2 司法取引の対象犯罪
すべての犯罪が司法取引の対象となるわけではなく、司法取引の対象犯罪は、特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪など特定犯罪に限られています。
司法取引の対象となる特定犯罪のうち、企業活動に関係する犯罪としては次のようなものが挙げられます。
贈収賄や詐欺、横領、背任
脱税
独占禁止法違反(談合、カルテル)
金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引)
特許権侵害
不正競争防止法違反
会社法違反(特別背任等)
など
3 司法取引の進め方
捜査機関側で司法取引ができるのは、起訴の権限がある検察だけで、警察はできません。
司法取引は、検察官か、被疑者・被告人、どちら側からでも持ちかけることができます。
もっとも、最高検の方針によれば、検察官は、これまでの捜査手法で成果を得ることが難しい場合に、司法取引の協議の開始を検討するようです。また、検察幹部の話では、取り調べの中で、検察官から司法取引を持ちかけることはないとのことです。
司法取引の話し合いには、一貫して弁護人の同席が必要です。
被疑者と弁護人、検察官が取引に合意すれば、3者が合意した内容を記した書面に署名をして、司法取引の成立となります。
4 被疑者・被告人の捜査・訴追協力の内容
司法取引に際し、被疑者・被告人は、次のような協力をする必要があります。
①検察または警察の取調べに際して、他人の犯罪事実を明らかにするため、真実の供述をすること。
②他人の刑事事件の証人として尋問を受ける場合において、真実の供述をすること。
③他人の犯罪事実を明らかにするため、証拠物を提出すること。
④上記①から③に付随する行為であり、合意の目的を達成するために必要な行為
5 司法取引の見返り
他方、被疑者・被告人が、捜査・訴追に協力した見返りとして、検察官が提供する減免行為としては、次のようなことが挙げられます。
①不起訴にすること、あるいは公訴を取り消すこと。
②軽い罪で起訴したり、軽い罪に訴因を変更すること。
③被告人に軽い刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
④即決裁判手続きや略式命令といった簡易な手続きでの訴追をすること。
6 司法取引が成立しなかった場合
検察官は、被疑者・被告人から、どんな協力が得られるかを聞き、重要な証拠を得られる見込みがなかったり、協議での説明が信用できなかったりする場合には、司法取引に合意しません。このように、一旦協議が開始されても、司法取引が成立しないおそれがあります。
このような場合に、協議の過程で他人の刑事事件について、被疑者・被告人の調書等が作成されていても、これら調書等は他人の刑事事件において証拠として用いることができません。
もっとも、協議の過程で行われた被疑者の供述を手掛かりとして、捜査機関が捜査を行った結果、新たな証拠(派生証拠)が発見した場合、その派生証拠の使用については禁止されませんので、司法取引が成立しない場合には、そのようなリスクがあることも予め考慮した上で、司法取引の協議に臨むことが必要です。
7 会社と社員の利害対立のおそれ
司法取引は、他人の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、自身の刑事処分を軽くするというものですから、司法取引をめぐり、実行役の社員、それを指示した上司、あるいは会社との間で利害が対立するおそれがあります。
このような場合、利益相反との関係で、社員と上司、会社の弁護人を一つの法律事務所に依頼することはできず、複数の法律事務所に分けて依頼をしなければなりません。
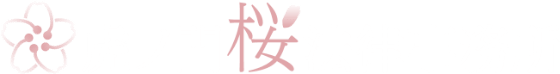
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)