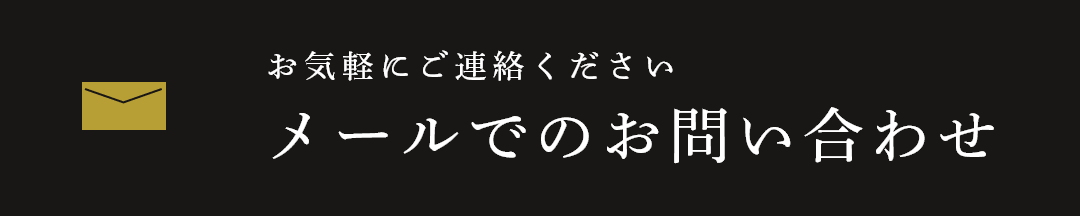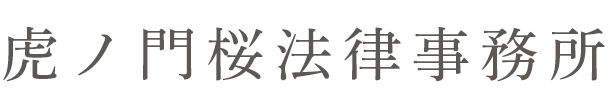-
2016.10.06
銀座のクラブママは労働者?…ではないようです。
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
最近、仕事が忙しくて、ブログの更新ができていないにもかかわらず、HPへのアクセス数が増えていて、少し嬉しい気持ちになりました。
●裁判例の紹介
さて、今回は、銀座のクラブママが、クラブ経営者から契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除されたことから、本件契約は労働契約であり、解雇は無効であると主張して、未払い賃金等の請求をした裁判例(東京地裁平成27年11月5日判決)をご紹介させていただきます。
裁判では、本件契約が労働契約か、それとも業務委託契約(準委任契約)かが争点となりました。
●労働者とは?
労働基準法には、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています(第9条)。
また、労働契約法には、「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されています(第2条1項)。
しかし、この定義だけから、労働者の範囲を明確にするのは、難しいですね。
●裁判の判断のポイント
当該判決では、概略、次のように、判示されています。
①原告(クラブママ)は、あらかじめ顧客にクラブへの来店を勧誘し、来店の約束を取り付けた上で、クラブに来店した顧客を接待していたものであり、原告の顧客が来店する予定のない日には、基本的には、クラブに出勤する必要がないものとされていた。
その上で、被告(クラブ経営者)は、顧客のうちの誰にいつクラブへの来店を勧誘するのか、どのような方法で勧誘するのかといった点について、原告に指示や指導をしておらず、これらの点を専ら原告に任せていたものと解される。
②原告は、顧客に勧誘する来店日時を調整することにより、出勤日及び出勤時刻をほぼ自由に決めることができる立場にあった。原告が被告によって業務遂行の時間を指定・管理されていたということはできない。
③原告の報酬が原告の顧客に対する売上のみに基づいて計算され、原告の稼働時間と連動していなかった。
原告の報酬は、原告がクラブにおいて接客を中心とした業務を行ったことそれ自体の対価というよりも、原告が原告の顧客を勧誘してクラブに来店させることによって、被告の売上げに貢献したことの対価という性格が強いものということができる。
原告の報酬は、接客という労務提供の対価としたならば極めて高額であるということができる。
④当該クラブに在籍する他のホステスの報酬は、出勤日数に応じた日給制等であったのに対し、原告は、報酬や料金システムについて、他のホステスとは違う待遇を受けていた。
⑤被告は、社会保険の関係で原告を労働者として扱っていなかった。
上記事情に照らせば、本件契約について、原告が被告の指揮下において労働をし、その対価とし賃金の支払いを受ける旨の労働契約であったと評価することは困難であり、原告は労働者に該当しないというべきである。
●評価
他方、クラブのホステスについて、労働者性を肯定した裁判例として東京地裁平成22年3月9日判決があります。
使用者の指揮監督の有無や強弱、報酬の労務対償性の有無等を総合評価して判断するということでしょうね。
-
2016.09.28
こういうさりげない、素敵な気遣い
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、東京近郊で仕事があり、その帰り道、町田駅近くのカフェで遅めのランチをとったことがありました。
木のぬくもりが感じられ、清潔感のある店内で、隣の席では、学生らしき女の子が、友達に恋愛の悩みを相談している、そんな雰囲気のお店です。
食後のコーヒーを飲みながら、ふと手元の伝票に目をやると、こんなメッセージが書かれていました。
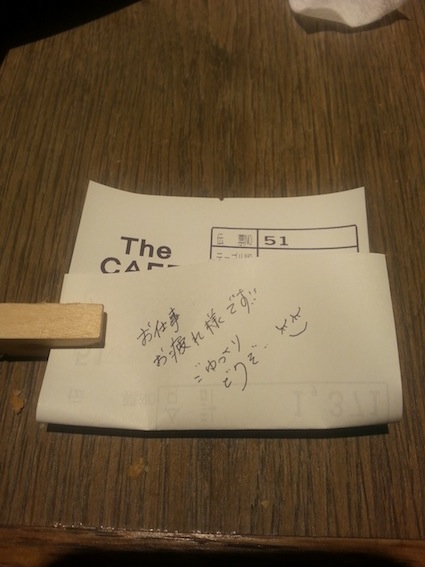
僕が平日の昼下がりに珍しい、スーツにネクタイを締めた男の一人客だったからでしょうが、少し幸せで、ほっこりとした気持ちになりました。
こういうさりげない気遣いって素敵ですね。
仕事柄、ぶっきらぼうな対応をしてしまうことがありますが、常に心に余裕を持ち、このような気配りができればと思います。
-
2016.08.30
従業員が事故に遭った場合、会社も損害賠償請求できるか?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
■ 結論
従業員が事故に遭って死傷するなどし、会社(使用者)にも、まとまりかけていた取引がまとまらなかったであるとか、一定期間売上が落ちたといった損害が生じた場合、加害者に対し、損害賠償請求できるかという問題〜いわゆる企業損害・間接損害の問題〜ですが、原則として、できません。まず認められないものと考えた方がよいでしょう。
■ 理由
損害賠償では、基本的に、直接事故に遭った被害者自身の損害しか認められず、被害者と債権関係(労働契約もその一つです)を有している者の間接損害の賠償は認められていません。
判例は、会社の代表者自身が事故にあったような場合でも、法人とは名ばかりの、俗に言う個人会社であり、その実権が代表者個人に集中して、会社の機関として代替性がなく、経済的に代表者と会社が一体をなすような関係があるような場合に限って、会社の損害賠償請求を認めています(昭和43年11月15日判決)。
まして、一従業員は会社と上記のような経済的に一体の関係にはなく、会社のこうむった間接的な損害の賠償請求が認められるはずがありません。
判例も、富山の薬売りをしている従業員が、その担当地区で絶大な信頼を受け、医療品の配置販売業務に高度に熟練しており、従業員の代替性がない事案においても、従業員が不時の災害を受けても営業に支障を生じないように予め対策を講じておくのが経営者の責任である旨判示して、損害賠償請求を棄却した原審判決(東京高裁昭和54年4月17日判決)を正当なものとして、維持しています(最高裁昭和54年12月13日判決)。
■ 例外的に認められる場合
もっとも、次のような場合には、例外的に、会社の損害賠償請求が認められます。
①会社が従業員のこうむった損害を肩代わりした場合
例えば、会社が従業員の代わりに、治療費や通院交通費を支払ったり、休業中の給与を支払った場合(但し、従業員が入通院のため、有給休暇をしたとき、その有給休暇消化分が従業員自身の休業損害となり、会社に損害が生じたとは言えません)、それは会社が、直接の被害者である従業員がこうむった損害を肩代わりした(直接被害者自身の損害と重なり合う)ものにすぎませんので、損害賠償請求が認められます。
②会社に損害を与える目的で、故意に従業員を襲撃したような場合
このような場合は、事故ではなく、もはや事件ですね。
-
2016.08.26
ダイエットのための食事制限
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
★ダイエット経験
実は、以前、私は、かなり太っていました。十数年間、デブをしていました。しかし、2年半前に劇的に痩せ、この夏もさらにシェイプアップし、MAXで太っていた時に比べ27kgくらい体重を絞り、ウェストも30cmくらい細くなりました。
では、どうやって痩せたかというと、ジム(ライ●●プではありませんよ)で、トレーナーに指導してもらい、筋トレを始めたのがきっかけですが、別に筋トレだけが原因ではないと思っています。私は、自らのダイエット経験から、
●大前提として、食事制限をしないと、体重は落ちない。
●しかし、筋トレをしないと、見た目のきれいな身体にはならない。
●さらに、有酸素運動で、脂肪(特に皮下脂肪)を燃焼させ、仕上げていく。
ものと感じています。
★食事制限の重要性
トレーニングをしてみると分かりますが、人間の身体は燃費が非常によく、ジョギングやエアロバイク等の有酸素運動でカロリーを消費するのはものすごく大変です。例えば、1個500キロカロリー以上あるといわれるメロンパン分のカロリーを消費するには、1時間近く走り続けなければなりません。
それに比べたら、メロンパン1個食べるのを我慢する方がはるかに楽で、ダイエットをするにあたり、食事制限がいかに重要かお分かりいただけるかと思います。
また、私が太りやすい体質だからかもしれませんが、ちょっと油断して、パンケーキやチャーハン、パスタといった糖質や脂質の高い食事をしてしまうと、大きくリバウンドはしないにしても、トレーニングを続けても、しばらく体重が落ちなくなってしまいます。
★正しい食事制限とは?
特に女性とダイエットの話をしていると、食事の量を減らしたり、野菜しか食べないといった、極端な話を聞きます。しかし、それでは、かえって筋肉がやつれ、脂肪が増え、不健康になる危険な食事制限だと思います。
私も、朝昼晩の三食は、基本的に、腹7〜8分くらいにとどめるようにしていますが、その合間にも小腹が空いたら、バナナや玄米ブラン、ゆで卵といったものを口に入れるようにして、けっして空腹を我慢しません。最近は、1日に5,6食くらい食べています。理論的にも、空腹時に食事をすると、血糖値が上がりすぎ、インスリンが大量に分泌され、脂肪を蓄えやすくなってしまうはずです。
また、私は、身体を鍛えているので、朝食やトレーニング後にはプロテインを飲んでいますが、その他にも、サラダチキンや赤身の肉、豆腐、納豆といった食事で、タンパク質を多くとるように心掛けています。
もちろん、サラダや、野菜のお総菜のほか、もずく酢やひじきといった海藻でミネラルもとるようにしています。
食事制限で、とても重要なのは、糖質(炭水化物)を制限することですが、これについては、また別の機会に書かせていただこうと思います。
ただ最後に一言、あくまで糖質を制限(コントロール)するということであって、完全に断つというのは、専門家の指導の下であるとか、1〜2週間程度の短期間でない限り、すべきではありません。やはり危険な食事制限だと思います。
-
2016.08.05
夏期休暇のお知らせ
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
最近、急激に夏らしい陽気になりましたね。
皆さんも、熱中症等にお気を付け下さい。
今年は、8月11日(木)から8月17日(水)までの1週間、夏期休暇をとらせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
-
2016.07.29
プライバシーを侵害するとして、防犯カメラの撤去等が認められた事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
今回は、原告らが、被告が共有する区分所有建物の共用部分である庇等の屋外にカメラ4台を設置していることが、原告らのプライバシーを侵害しているとして、被告に対し、カメラの撤去と損害賠償を請求したのに対し、その請求を一部認めた裁判例(東京地裁平成27年11月5日判決)をご紹介させていただきます。
当該裁判例はまず、最高裁昭和44年12月24日大法廷判決等を引用し、「人はみだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」とした上で、「もっとも、ある者の容ぼう等をその承諾無く撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、撮影の場所、撮影の範囲、撮影の態様、撮影の目的、撮影の必要性、撮影された映像の管理方法等諸般の事情を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を越えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」と判示しました。
そして、撤去を求められているすべてのカメラの設置につき、被告宅の防犯目的が含まれているが、原告らに対する監視目的が含まれているとまでは認められないとしつつ、うち1台のカメラ(カメラ1)について、原告宅玄関入口付近に立っている人が、顔を識別できるほどではないものの、かなり鮮明に映ること、通用口の前付近において上記ほど鮮明ではないものの、少なくとも人が通過していることは映像上認識することが可能であること等を認定し、撮影が常に行われており、原告らの外出や帰宅等という日常生活が常に把握されていること、当該カメラの設置は被告宅の窓付近を撮影して防犯を図るものであるとするが、窓の防犯対策としては二重鍵を設置するなどのその他の代替手段がないわけではないこと等から、これによる撮影に伴う原告らのプライバシーの侵害は社会生活上受忍すべき限度を越えているとして、その撤去を認めました。
他方、残り3台のカメラについては、原告ら所有居室の玄関付近や廊下等、公道に出るための通行路が撮影範囲となっていないことから、原告らのプライバシーが社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害されていることできないとして、請求を棄却しました。
また、カメラ1によるプライバシー侵害に伴う慰謝料額は原告1人あたり10万円(原告4人で計40万円)が認定されています。
その理由として、カメラ1の撮影範囲が原告らのプライバシーを保護すべき場所に及んでいるものの、これらの場所は屋外であって全くの私的空間ではないこと、監視目的で設置された場合に比べると悪質性は低いこと、カメラ1で撮影された映像が約2週間経過後には自動的に上書きされて消去され、映像が永続的に保存・管理されるものではないことが挙げられています。
-
2016.07.28
婚姻費用の算定にあたり、別居後、夫が妻の居住する自宅の住宅ローンを支払っていた事情を考慮した事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
今回は、婚姻費用分担金の算定にあたり、別居後も、夫が、妻の居住する自宅の住宅ローンを全額負担して支払っていた事情を考慮して、標準算定表から導かれる標準的な額から、一定の額を控除するのが相当であると判示した事例(東京家裁平成27年6月17日審判)をご紹介させていただきます。
標準算定表は、別居中の権利者世帯(婚姻費用の支払いを受けられる方)と義務者世帯(婚姻費用を支払わなければならない方)が、統計的数値に照らして標準的な住居費をそれぞれ負担していることを前提として標準的な婚姻費用分担金の額を算定するという考え方に基づいています。
しかし、当該事例では、義務者である夫が、権利者である妻が居住する自宅の住宅ローンを全額負担しており、夫が妻の住居費をも二重に負担していましたので、子の事情を考慮して、当事者の公平を図る必要があります。
問題は、この事情をどのように考慮するかですが、上記審判例は、標準算定表から導かれる標準額から、権利者である妻の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除するという方法を採りました。
なお、住居関係費については、標準算定方式が前提とする家計調査年報(判例タイムズ1111号285頁以下)から認定しています。
-
2016.07.22
被用者の使用者に対する求償を認めた事例
霞が関パートナーズの弁護士伊澤大輔です。
今回は、被用者が使用者所有の自動車を職務のため運転中に事故を起こし、被害者に賠償金を支払った場合において、被用者の使用者に対する求償を認めた裁判例(佐賀地裁平成27年9月11日判決)を紹介させていただきます。
事案の概要は、被用者が、使用者である会社所有の自動車を運転して、業務に従事中、被害者運転の自動車と衝突する交通事故を起こしてしまい、被害者に対して、その修理代金相当額を賠償したことから、使用者に対し、同額の求償をしたというものです。
実は、使用者が、被害者に対し、使用者責任に基づき賠償した場合に、被用者に対し求償できることについては、民法上規定がありますが(民法第715条3項。但し、一般的に、その求償権の行使や求償額は制限されます。)、これとは反対に、被用者が被害者に賠償金を支払った場合に、使用者へ求償(いわゆる逆求償)できるか否かについては、民法上、何ら規定がありません。
上記裁判例は、第三者に対し、被用者と使用者が損害賠償責任を負担した場合、両者の責任は不真正連帯責任の関係にあるといえ、使用者は被用者の活動によって自己の活動領域を拡張しているという関係に立つこと(いわゆる報償責任)から、被用者がその事業の執行について他人に損害を与えた場合には、被用者及び使用者の損害賠償債務については自ずと負担部分が存在することになり、一方が自己負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、その者は、自己の負担部分を超えた部分について他方に対し求償することができると解するのが相当である旨判示しています。
そして、当該事故に関し、使用者と被用者の負担割合を7対3とし、被用者が被害者に支払った賠償金の7割について、使用者に対する求償を認めていますが、その事情としては、
①被用者が九州地方のエリアマネージャーとして雇用されており、使用者の事業拡大を担う立場として業務を行っていたこと、
②被用者の業務の性質上、事故発生の危険性を内包する長距離の自動車運転を予定するものであったこと、
③被用者は、当該事故発生前後の期間、相応の態度で業務に取り組んでおり、その業務量も少なくなかったこと、
④当該事故における被用者の過失の内容は、車両後退時の後方確認不十分であり、自動車運転に伴って通常予想される事故の範囲を超えるものではないこと、
等が総合考慮されています。
なお、上記裁判例は、第一審の鳥栖簡易裁判所が被用者の請求を一部認容したことから、これを不服として使用者が控訴した控訴審判決(控訴棄却)です。さらに、使用者は上告しましたが、上告は棄却され、確定しています。
-
2016.07.01
転貸を目的とする建物賃貸借契約について、期間満了を理由とする明渡請求を認めた事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
このところ、弁護士業務が多忙で久しぶりのブログ更新になってしまいました。忙しいときにも、コンスタントに情報提供をしていかなければと反省しております。申し訳ございませんでした。
さて、今回は、第三者への転貸を目的とする建物の賃貸借契約の期間満了を理由とする明渡請求につき、1年強程度の賃料差額の立退料の支払いをもって、明け渡しを認めた裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)をご紹介させていただきます。
借地借家法第28条には、建物の賃貸人による解約の申し入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の申出等を総合考慮して、正当事由があると認められる場合でなければ、することができない旨定められています。
上記裁判例は、第三者への転貸を目的とする建物の賃貸借契約について、賃借人が当該建物を使用する必要性は転貸による経済的利益に尽きること、契約終了時に賃貸人が転借人の賃借権(転貸人の地位)を引き受ける旨の条項があるため転借人の事情を考慮する必要は無いこと、賃貸人側の事情(当該建物を占有負担のない形で売却するために賃貸借契約を終了させる必要性)は、本来的な意味での自己使用の必要性をいうものではないが、他方、賃借人側にとっても当該建物を使用する強い必要性があるわけではないこと等を理由に、50万円(賃料差額の約15ヶ月分)の立退料をもって、更新拒絶につき正当事由の充足を認めています。
この裁判例では、賃借人の経済的利益が月額3万3000円(転貸収入月13万3000円−保証賃料月10万円)と少額で、賃貸借契約の終了によって賃借人の経営に影響を及ぼすような重大な不利益が生ずるとは認められない旨も判示されていますが、月額わずか数万円と絶対的評価としての経済的利益が低いか否かという問題ではなく、賃借人が行っている全事業のうち、その建物の転貸借事業による収益がどの程度の割合を占め、賃貸借契約の終了により、賃借人の経営に重大な不利益を及ぼすか否かの問題なのではないかと思料します。
- HOME
- ブログ (Page 16)
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (3)
-
2022年 (6)
-
2021年 (33)
-
2020年 (9)
-
2019年 (8)
-
2018年 (43)
-
2017年 (29)
-
2016年 (40)
-
2015年 (87)
-
2014年 (1)
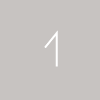
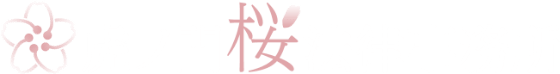
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)