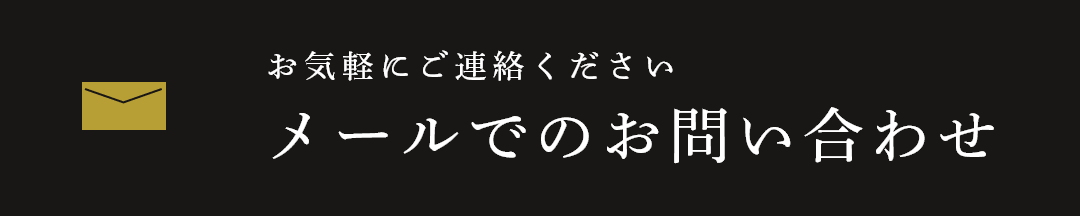-
2021.05.26
【取締役の解任】職務不適任による「正当な理由」が認められるか?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
取締役などの役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。理由のいかんを問いません。
ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができます(同条2項)。
そのため、取締役を解任した場合、会社は、取締役から、損害賠償請求されることが多く、取締役の解任に「正当な理由」があるか否かは、重要な争点となります。
特に職務への不適任を理由とする場合には、「正当な理由」が認められるケースと認められないケースとに分かれ、判断が難しいことががありますので、今回は、その裁判例について紹介させていただきます。
■正当な理由とは?
東京地裁平成29年1月26日判決は、会社法339条2項の「正当な理由」の内容について、会社・株主の利益と解任の対象である役員の利益の調和の観点から決せられるべきものであり、具体的には、会社において、当該役員に役員としての職務執行をゆだねることができないと判断することもやむをえない客観的な事情があることをいうと判示しています。
また、東京地裁平成25年5月30日判決は、正当な理由が存在する場合とは、当該取締役の職務の執行に当たり、
①不正の行為や定款又は法令に違反する行為があった場合
②取締役が経営に失敗して会社に損害を与えた場合
③当該取締役の経営能力の不足により客観的な状況から判断して将来的に会社に損害を与える可能性が高い場合に認められるとし,単に株主と取締役との間で経営方針が異なるというだけでは正当な理由は認められないとしています。
■解任事由の告知の要否・会社の認識
役員の解任について定める会社法339条において、役員を解任するに当たり、会社の故意過失や当該役員への解任事由の告知は要件とされていない上、「正当な理由」を会社が認識していた事情に限定する旨の規定も存在しないことからすれば、正当な理由の根拠となる事情は、解任時点で客観的に存在していれば足り、会社代表者らが認識していることまで要しないとされています(東京地裁平成30年3月29日判決)。
■正当な理由を認めた裁判例
(東京地裁平成30年3月29日判決)
同判決は、以下の事実を認定し、それぞれが単独で解任の正当な理由になるとまではいえないものの、これらを総合勘案すれば、当該事業について取締役会決議などがされていることなどを踏まえても、取締役として著しく不適任であるとされてもやむをえないといえ、解任には正当な理由があると判断しました。
・企業グループ全体の経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事業を企図し実行したこと
・当該事業の実施を決定する取締役会及び当該事業への追加投資を承認する稟議において虚偽説明をしたこと
・子会社に対し虚偽説明を伴って当該事業に係る販売データの購入圧力をかけたこと
・グループ役職員等の電子メールに含まれる情報を不正に取得したこと解任された取締役が企画・実行した事業は、小売店舗の店頭で商品陳列状況を無断で撮影し、その画像をマーケティングに有用な情報にデータ化した上で販売するというものであり、店舗内で隠し撮りをする点で違法と判断される危険性があり、かつ、小売業者との信頼関係を破壊し、グループ全体の経営に悪影響を及ぼしかねないおそれのあるものであって、解任された取締役には、業務を遂行するに当たって要求される手続を軽視する姿勢が顕著に見られ、コンプライアンス意識も欠如していると判示されています。
(東京地裁平成18年8月30日判決)
取締役は、会社代表者から支店への異動を打診された直後から、会社代表者及び副社長の自己に対する人事異動の打診行為について批判し、それにとどまらず、その後は会社及び代表者の数々の問題点、疑問点を挙げ連ねて会社批判を繰り返し、上記打診がある前には全く見受けられなかったところの会社への敵対行動に出ていること、当該取締役は既に会社の情報を訴週刊誌の記者にまで情報提供しているがその必要性はなかったと思われること、会社の内部的な問題は、これをスキャンダルとして週刊誌等に掲載されれば会社の信用を損ね経営に支障を来すことは容易に予期できたものと考えられることなどからすると、当該取締役の行動は、会社の是正というよりも意に沿わない人事異動の打診があったことを契機とした会社と会社代表者への糾弾を中心とする報復措置と受け止められても仕方のないものであったと評価でき、むしろ業務執行を阻害するものというべきであり、現実に会社あるいは会社代表者の信用は損なわれ、取引及び収益の減少も相当程度生じていることから、その解任には正当事由があると判示しています。
(広島地裁平成6年11月29日判決)
正当事由には、経営判断の誤りによって会社に損害を与えた場合も含まれるものというべきであるとし、会社の売上が毎年着実に伸びており、業務の特殊性からして、リスクの大きい株式取引に手を出さなければならない緊急性がなかったにもかかわらず、代表取締役が多額の株式の信用取引や投機性の高い取引を独断で行い、結果的に多額の損失を会社に与えたものであって、これは、代表取締役としての経営判断の誤りと評価されても止むを得ないものであると判示し、解任について正当事由を認めています。
もっとも、同判決は、当該取締役が、脳血栓で二か月もの入院加療を要する状態になり、退院後も長期的な通院治療を必要とし、意識状態は普通であるものの、会話能力や筆記能力が相当程度低下しているのであって、かような状況で取締役として通常どおりの職務の遂行が可能であるとは考え難いというべきことや、当該取締役が、退院してからも、出社して自ら経営者としての職責を全うする態度を見せておらず、却って他の監査役や取締役らの責任追及に対してひたすら弁解に終始するばかりであり、自己の解任が議題になっている株主総会にも出席せず、職務の遂行に対する意欲も失われていたこともあわせて認定して、正当事由を認めたものであり、経営判断の誤りのみによって、正当事由を認めたものではありません。
■正当な理由を否定した裁判例
(東京地裁平成29年1月26日判決)
解任された取締役の次の行為について、各項目ごとに独立して、「正当な理由」があるということはできないと判示しています。
・受嘱承認手続に係る規範の不遵守等
・グループの方針の不遵守
・研修義務不履行者への措置・処分の未策定
・離職者数の多さ
・規程整備への非協力
・業績目標の未達
・アドバイザリー業務体制の検討における非協調姿勢
・独断での新たなQRMプロセスの提案
・パートナーシップの検討における姿勢
・提供を受けたサービスの対価の支払懈怠また、当該取締役の行為や対応が、グループ子会社の代表取締役(社長)の行為として問題のあるものであり、これらを総合すると、代表取締役としての適性に疑念を生じさせる面があることは否定できないとしつつ、他方、業績が低迷して営業力も低い会社の収益を改善し規模を拡大することを目的として招聘されたものであり、当該取締役自身、そのことを十分認識して代表取締役(社長)に就任したものであること、実際、会社の損益は、黒字に転じ、在任中は一応黒字を維持しており、従業員数も、毎年約100人ないし150人ずつ増加していることが認められ、これらの事実を総合すれば、当該取締役が代表取締役として著しく不適任であると断ずることはできず、解任について「正当な理由」があるとまでいうこともできないと判示しています。
(東京地裁平成11年12月24日判決)
正当事由の有無につき検討するに、解任された取締役は、従業員を指導する際、余りにも激しく叱責し、店長や従業員から不満をかうようなことがあったり、会社代表者に苦情を述べる従業員がいたり、各店長から会社代表者に上申書が提出されるようなことがあったり、役員室に内側から施錠して一人役員室にこもって執務することがあるなど従業員らの信頼が十分でなく、当該取締役に適切さを欠く業務執行の態様があったことは否定できないと判示しています。
しかし、従業員に対する叱責に関しては、当該取締役が自己の職務に熱心なあまり、その言動にいきすぎた面があったとも評価できなくもなく、この事実をもって職務への著しい不適任ということはできないし、当該取締役に対する従業員らからの信頼が十分でないことや業務執行の態様にやや不適切な面があったことが、結果として会社の経営にどのような影響を与えたのかも不明であり、業績の悪化、信用失墜等を含めた経営上の支障が会社に生じたことを認めるに足りる証拠もなとして、著しい職務への不適任があったということはできず、正当事由は認められないと判示しています。
-
2021.05.26
【消費者契約法】製品性能の不実告知があったとして、売買契約の取消が認められた裁判例

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、軽自動車の売買契約において、カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして、消費者契約法4条1項による取消しが認められた裁判例(大阪地裁令和3年1月29日判決)を紹介させていただきます。
■事案の概要
三菱自動車等が、軽自動車のカタログ等に、「国交省の定める測定方法等による燃費性能」よりも優れた燃費性能を表示させた上で、販売店らをして、原告らに対して軽自動車を販売させたとして、車両に係る各売買契約を消費者契約法4条1項1号(不実告知)に基づいて取り消したなどと主張した事案です。
■不実告知による取消の要件
消費者契約法4条1項1号は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について、事実と異なることを告げたこと(不実告知)により、消費者が告知された内容を事実であると誤認し、それによって消費者契約の申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができると規定しています。
その要件を整理すると、次の通りとなります。
①事業者と消費者との間の契約であること(消費者契約該当性)。
②事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不実告知をしたか(勧誘及び不実告知該当性)。
③告知された内容は、重要事項に当たるか(重要事項該当性)。
④消費者が告知された内容を真実であると誤認したか、不実告知と誤認、誤認と消費者契約の申込みの意思表示との各間に因果関係があるか(因果関係の有無)。■ ①消費者契約
消費者契約法2条1項の「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいい、個人事業者であっても、事業としてでもなく、事業のためではない目的のために契約の当事者となる場合には、「消費者」となり得ます。
原告の一人であるJは個人事業主でしたが、主にその妻が日常の家事に使用するため、車両(サクラピンクメタリック色)を購入したことが認められ、自らの事業として又は自らの事業のために当該車両を購入したものとは認められないから、Jは、当該車両の売買契約において、「消費者」に該当するというべきであると判示されています。
■ ②勧誘及び不実告知
消費者契約法4条1項1号の「勧誘」とは、事業者が消費者に対し、消費者契約の締結に際し、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の消費者契約の締結に向けた働きかけを行うことをいい、事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような媒体により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合もこれに含まれます。
販売店らによるカタログの交付またはその従業員による説明は、同号の「勧誘」に当たるものと認められます。
また、カタログ等の「燃料消費率(国土交通省審査値)」の表示は、国土交通省の定める測定方法による算出値であるということを意味するものであるところ、国土交通省の定める測定方法による算出値ではないのに同測定方法による算出値であるかのように表示し、かつ、実際の国土交通省の定める測定方法による算出値よりも優良な数値を表示した点において、事実と異なるものであり、カタログ等の表示並びにこれを前提とした販売店らの従業員による説明を確認又は理解した者は、表示された値が国土交通省の定める測定方法による算出値であり、かつ、実際の算出値よりも優良な数値であることについて、事実であるとの誤認を生じさせるものというべきであるから、不実告知に当たると認められます。
■ ③重要事項
消費者契約法4条1項1号の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」(同条4項1号)等であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの(同項柱書)をいいます。
ここで「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」とは、契約締結の時点における社会通念に照らし、その契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が契約を締結するか否かについて、その判断を左右すると客観的に認められるような契約についての基本的事項をいいます。
そして、当該事案において、不実告知の対象事項は、車両の燃費値という「質」に関わるものであるところ、車両の燃費値は、軽自動車を購入しようとする消費者にとって、経済的な観点のみならず、環境問題への配慮がされた車両か否かという売買において購入の一つの重要な要素であり、事業者である三菱自動車おいても、目標燃費値を達成することが車両の売上げ増に直結するものであるとして、車両の開発が行われていたことが認められます。
これらの事情からすると車両の燃費値は、車両の売買契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が車両の売買契約を締結するか否かの判断に通常影響を左右すると客観的に認められるような車両の売買契約についての基本的事項に当たるものといえ、「重要事項」に当たるものと認められています。
■ ④因果関係
原告ら(一部を除く)は、販売店らから交付されたカタログ等又は被告販売店らの従業員の説明により、車両の燃費値が、国土交通省の定める測定方法による算出値であり、かつ、実際の算出値よりも優良な数値であることについて不実告知を受け、この内容を真実であると誤認したことが認められ、これによって車両の売買契約を締結したものと認められています。
-
2021.05.25
【損害賠償】マンション管理について、理事や管理会社の善管注意義務違反を認められるケース

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
一般に、管理組合の役員と管理組合の法律関係については、役員を受任者とし、管理組合を委任者とする委任契約が成立しているものと解され、受任者(理事長その他の役員)は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。
もっとも、どのような場合に善管注意義務違反となるかについては評価の問題であり、悩まれる方もいらっしゃると思います。前回は、裁判例上、善管注意義務違反が認められなかったケースについて、ご紹介させていただきましたので、今回は、裁判例上、善管注意義務違反を認めたケースについて、ご紹介させていただきます。
■会計担当理事の横領に関する他の理事の責任
(会計監査役員)
会計監査役員として、会計担当理事Aが作成した前年度の収支決算報告書を確認・点検し、会計業務が適正に行われていることを確認すべき義務があったにもかかわらず、Aから示された虚偽の収支決算報告書の記載とAが偽造した残高証明書の残高等を確認するだけで、預金口座の通帳の確認をせず、Aによる横領行為を看過したものであった。そして、Aが示した預金口座の残高証明書は、Aが自分のワープロで偽造したというものであって、その体裁等からして真実の銀行発行の預金口座の残高証明書の原本とはかなり異なるものであったことが推認され、このような偽造された残高証明書を安易に信用し、Aが保管しており、その確認が容易である預金口座の預金通帳によって残高を確認しようとしなかった会計監査役員には、善管注意義務違反があったと認めざるを得ない(東京地裁平成27年3月30日判決)。(理事長)
理事長として、前年度の収支決算報告書を作成して総会で自治会員に報告する義務を負っていたものである。したがって、たとえ会計については会計担当理事に委託しており、また、会計監査役員による会計監査が行われていたとしても、やはり理事長が自治会員に対して収支決算報告をすべき最終的な責任者であることに照らすと、会計担当理事Aが作成した収支決算報告書を確認・点検して適正に行われていることを確認すべき義務があったといわざるを得ない。それにもかかわらず、理事長は、Aに預金口座の管理、その預金通帳及び銀行用印鑑の保管を任せていたにもかかわらず、会計の報告につき、定期総会の直前にAから簡単な説明を受けるのみであって、預金口座の通帳の残高を確認することなく、また、会計監査役員に対し、預金口座の通帳を確認するなどの適正な監査をすべき指示を出したり、適正な監査をしているかを確認したりすることもなく、その結果、Aによる会計業務の具体的内容について十分な確認をしないままとしていたものであって、このような理事長には、善管注意義務違反があったと認めざるを得ない(同上)。(副理事長・責任否定)
副理事長においては、規約上も実際の職務分担のいずれにおいても、自治会の会計事務について具体的に何らかの権限が与えられていたものではないところ、このような副理事長において、会計事務について何らかの措置を講ずべき場合とは、理事長が会計に関して行っていた行為について何らの補佐をしなければならない状況が存在することになった場合又は理事長に事故があった場合であると解される。しかるところ、当時、副理事長自身はもちろん、理事長やその他の自治会関係者においても、自治会の会計事務において副理事長が何らかの措置を講ずべき状況にあると認識されておらず、また、理事長に事故があるとの状況にもなかったことに照らすと、会計担当理事の横領行為につき、副理事長において予見して何らかの措置を講ずべきであったということはできず、副理事長に自治会に対する善管注意義務違反があったと認めることはできない(同上)。■監査報告書の無断作成
理事長は、管理組合の監事から委任を受けていないにもかかわらず、監事を代理して監査報告書を作成したものであるところ、監事は、理事による業務執行が適正に行われているか監査するための機関であることにも鑑みれば、理事長が、監事が作成した監査報告書を議案書に添付せずに、自ら無権限で作成した監査報告書を添付して組合員に交付したことは、管理組合の理事長としての善管注意義務に違反する(ただし、これによる管理組合への損害の発生については否定。東京地裁令和2年7月10日判決)。
■監事候補者の不実記載
理事長は、Gが管理組合の監事に立候補していることを認識していたのであり、管理規約によれば、理事長は、総会を招集するものとされ、その際には、会議の目的を示して組合員に通知を発しなければならないとされているのであるから、Gが監事に立候補していることを通常総会の議案に記載すべき義務を負っていたと認めることができ、理事長がこれを故意に議案に記載しなかったことは、理事長としての善管注意義務に違反する(ただし、これによる管理組合への損害の発生については否定。東京地裁令和2年7月10日判決)。
■共用部分の総会決議を経ない賃貸
マンションのラウンジであったところをRの店舗をして賃貸することとなったのであり、賃貸部分は従来の用途を全く変えたものといえるから、共用部分の変更に当たる。共用部分の変更をするためには管理組合の総会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議を経る必要があるから、理事長は、Rとの間で、賃貸借契約を締結するにあたり、総会での決議を経る必要があった。しかし、理事長は、賃貸借契約を締結するに際し、総会での決議を経ていない。理事長は、マンションの業務を法律や規約に従って行わなければならない。そうすると、理事長が総会での決議を経ないまま賃貸借契約を締結したことは、善管注意義務に反する(福岡地裁平成30年3月7日判決)。
■共用部分の管理
変色の生じた外壁部分は、共用部分に当たるところ、管理組合は、規約上敷地及び共用部分等の管理責任を負っている。したがって、管理組合は、同外壁部分につき管理責任を負い、その原因や修理経過、今後の修理計画について把握する義務がある。この義務が個々の組合員に対して負うものかはともかく、管理組合は、原告が、当時の管理組合理事長に対し、工事の実施に関する資料の提出を要求した際、一切の資料がないとして、この要求に応じなかったことからすれば、それ以前に外壁の補修工事が行われた事実を含め、変色の原因につき詳細を把握していなかったと認められ、したがって、上記義務を怠ったことが認められる(ただし、マンションの価値下落との因果関係は否定。横浜地裁平成13年12月28日判決)。
-
2021.05.24
【損害賠償】マンション管理について、理事や管理会社の善管注意義務違反が認められないケース

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
一般に、管理組合の役員と管理組合の法律関係については、役員を受任者とし、管理組合を委任者とする委任契約が成立しているものと解され、受任者(理事長その他の役員)は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。
また、管理会社は、管理組合に対し、管理委託契約上の善管注意義務を負っています。
もっとも、どのような場合に善管注意義務違反となるかについては評価の問題であり、悩まれる方もいらっしゃると思いますので、その参考にしていただくため、今回は、裁判例上、善管注意義務違反が認められなかったケースについて、ご紹介させていただきます。
なお、今回は、理事や管理会社が管理組合に対し、具体的にどのような善管注意義務を負うかや、どのような場合に、その善管注意義務に違反したと評価できるかについて判示した裁判例を紹介するものであり、事実認定について争いがあった裁判例(例えば、横領行為があったか否かなど)については、取り扱いません。
■相見積をとったり、費用の妥当性を検証しなかった場合
東京地裁平成31年1月24日判決は、管理組合の役員となる資格は管理組合の組合員であることのみであり、特別な知識、素養等を要求されていないことからすれば、誠実義務は、管理組合の意思決定機関である総会の決議に従って、その執行を行うことを基本とするものであって、マンションの管理業務を業者に外注するに際して、複数の業者から相見積りを取得して比較検討したり、周辺相場を確認できる資料を取得したりするなどして費用の妥当性を検証すべき法的な義務が常に課されていると解することはできないと判示しています。
■交換周期よりも早い工事の実施
東京地裁令和2年7月10日判決は、国土交通省策定のマンション管理標準指針コメントは、各備品の一般的な耐用年数等によって改修の周期の一つの目安を示しているにすぎず、郵便受け工事は、従前の郵便受けが老朽化したとして交換したものではなく、郵便物の大型化などによって、その使用に不都合が生じるようになったために交換したと認められるのであり、郵便受けの一般的な耐用年数経過前の交換であったとしても、マンションの居住者の要望に応じてされた適切な工事であったとし、総会決議を得て、これよりも早く交換をしたからといって、直ちに理事長としての善管注意義務に違反することにはならない旨判示しています。
また、同判決は、交換周期よりも早い自転車置場の工事についても、大規模修繕に向けた建物調査診断報告書には、駐輪設備に腐食が見られる旨の指摘があること、改修前の駐輪設備では、登録された自転車の台数も賄えない状態となっている上、2段式ラックの上段も使用できない部分が多く、居住者からも駐輪場整備の要望が寄せられていたことから、マンションの居住者の要望に応じてされた適切な工事であったと認められるとして、善管注意義務違反を否定しています。
■割高なリース契約の更新
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理組合が従前の防犯カメラを利用していればリース料が安く済んだ旨主張するが、防犯カメラ更新によるリース料が、一般的な相場を離れて不相当に高額であったとか、新たな支出が従前の防犯カメラと更新後の防犯カメラの機能面の違いに明らかに見合っていないとの主張立証はないとし、防犯カメラには、価格や機器の質の面で様々なものがあり得るところ、機能面での違いを無視して、最も安価なものを選ばなければ直ちに理事長としての善管注意義務違反になるわけではない旨判示しています。
■修繕工事の優先順位の判断
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理組合が大規模修繕工事の際、屋上防水工事を実施しなかったことを問題にしたことについて、各工事等は有効な総会決議を経て実施されているのであるから、工事等の優先順位は管理組合の組合員の総意により定められたものというべきであることに加えて、大規模修繕に向けた建物調査診断報告書の総合所見にも、屋上防水には大きな問題は見られないが、耐用年数を迎えていることから、大規模修繕工事と同時に全面改修をすることを勧める旨の記載がされているのであって、屋上防水工事を直ちに実施しなければならない旨の指摘もされていないことから、大規模修繕工事の際に屋上防水工事を実施しなかったことをもって、理事長としての善管注意義務違反があったと認めることはできないと判示しています。
■総会議案書の記載
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理会社が、臨時総会の議案書において、将来の修繕予定項目を列挙した中の一つとして、機械式駐車場に関する工事を挙げたことが認められるが、当該記載は、屋上及びルーフバルコニーの防水工事の議案説明のために、今後、予想される支出を列挙したものにすぎないし、仮に、将来、当該支出が議案として提出された場合に、管理組合において、問題であると考えるのであれば、その支出を承認しなければ足りるものであるから、そのような記載することが、善管注意義務違反に当たるとは認められない旨判示しています。
■総会議事録の記載
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理規約により、議事録は、総会の議長である理事長が作成することとされており、管理会社は、単にその素案を作成したにすぎないものであるし、管理組合が虚偽であると指摘する具体的内容は、「一生懸命やってこられたと信じたい」と記載すべきところを「やられてきたことには問題が無い」と記載したというものであって、結局、総会出席者の発言内容の要約が不適切であったというものにすぎず、理事長が、署名に当たって訂正すれば足りる程度のものであって、現にそのようにされているのであるから、上記をもって、管理会社に善管注意義務違反があるとは認められない旨判示しています。
■理事を解任された者に対する理事会資料の送信(情報漏えい)
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理会社が、理事を解任された元理事長に対し、理事会の資料を送信したことについて、これらは、管理組合の運営にかかる理事会の資料等の案文等にすぎないものであって、これらの文書の中にいかなる秘密が含まれ、これを元理事長に開示することがいかなる意味で管理組合の管理運営に支障を来すのかについて、具体的な主張立証はないから、これらを管理組合の組合員である元理事長に対して開示することが直ちに守秘義務違反に当たるとはいえないし、これらの書面の交付がおこなわれたのは、元理事長が臨時総会で解任されてから間もない、未だ混乱した状況下での行為であることにも鑑みれば、管理会社に管理委託契約上の善管注意義務違反があったとは認められない旨判示しています。
■大雨による駐車場に止めていた自動車の浸水事故
東京地裁平成28年9月12日判決は、マンションの居住者かつ区分所有者が、マンションの機械式駐車場の地下部分に自己所有の自動車を駐車していたところ、台風に伴う大雨による駐車場の浸水事故により、自動車を廃車処分せざるをえなくなったとして、マンションの管理業者に対し、被害者の主張する通知義務、警報装置設置等義務及び土嚢設置等義務は、いずれも自動車の浸水事故を未然に防止するために何らかの措置をとることを内容とするものであるところ、当該管理業務契約においては、予め浸水事故防止措置をとることに関する定めはないことや、当該駐車場では、過去に自動車の浸水事故が発生したことはなく、管理業務契約に定められている業務内容を超えて、浸水事故を防止するための措置をとる義務の存在を基礎づける事情はないとして、損害賠償請求を否定しました。
-
2021.05.18
【建築トラブル】施工業者が破産した場合、どうする?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近も、アパートの階段崩落事故に関連して、施工業者が破産しましたが、施工業者(請負人)が破産して、建築工事がストップしてしまうことは度々起こることででして、私も相談を受けることがあります。
思いがけず、このような事態に陥って、お困りの注文者の方もいらっしゃるのでしょうから、今回は、施工業者が破産した場合の対応方について、ご説明させていただきます。
■「住宅完成保証制度」加入の有無の確認
「住宅完成保証制度」とは、施工業者が破産し工事を継続できなくなった場合に、住宅の完成に向けた工事費用や破産などにより戻ってこないお金(前払金等)の損失を保証したり、引き継ぎ業者をあっせんすることができる任意加入の保証制度です。
破産した施工業者がこの保険に加入していた場合には、その保険金により救済を受けられる場合がありますので、まず、この点を確認してください。
ただし、保証限度額が定められていたり、増嵩工事費用(未履行部分の工事を別の業者が代わりに施工した場合で、手戻り工事費や既施工部分の検査などを行う費用)の限度額が定められており、全額の保証を受けられるとは限りません。
なお、「住宅完成保証制度」と「住宅瑕疵担保責任保険」とは、別のものですので、注意が必要です。
後者の「住宅瑕疵担保責任保険」は、引き渡された新築住宅に特定の瑕疵があった場合に、補修等を行った施工業者や住宅販売業者に保険金が支払われる制度です。施工業者が破産した場合に、工事を続行するためにこの保険制度を利用することはできません。
■「住宅完成保証制度」に加入している場合の注意点
一般的に、次のような事実が発生したときには、発注者は、保険会社に対し、遅滞なく、通知することが求められています。
・建築工事の全部または一部の施工の中止を知ったとき。
・施工業者が倒産等、建築工事が継続できなくなる事実が発生したことを知ったとき。
・施工業者につき、破産、民事再生、会社更生手続開始の申し立てがあったことを知ったとき。
・発注者が、建築工事請負契約を解除しようとするとき(書面での通知)。
正当な理由なく、これら通知義務を履行しないと、保険会社による保証債務の履行を受けられなくなる場合がありますので、注意が必要です。
また、施工業者が倒産等した場合、保険会社(の依頼を受けた鑑定人)が、当初締結した請負金額に係る見積単価に基づき、出来高の算定を行うことになります。
■その他、初動で行うべきこと
(工事の進捗状況の撮影)
後述の通り、破産管財人が請負契約を解除する場合には、工事の出来高の査定が必要不可欠になりますので、速やかに、工事現場で、工事の進捗状況を詳細に撮影し、証拠を保全すべきです。(出来高の査定)
また、施工業者の従業員や、他の専門業者の協力を得て、出来高の査定を行ってください。なお、工事現場の占有は施工業者(破産後は、破産管財人)にあると考えられますので、工事現場に立ち入る場合には、破産管財人に立ち会ってもらうか、破産管財人の同意を得て行うべきです。
(建築中の建物の保全)
工事途中の建物を長期間放置しておくと、風雨によって建物が劣化してしまうような場合には、応急措置としてブルーシートをかけるなどの保全行為については、損害の拡大を防ぐために許されると考えられますが、念のため、破産管財人の了承を得て行ってください。■破産管財人からの解除
工事が未完の場合、基本的に、施工業者の破産管財人は、請負契約を解除するか、あるいは残りの工事を履行して、注文者に対し、残りの請負代金を請求するか、選ぶことができます(破産法53条1項)。ただし、その工事が破産をした施工業者にしか完成することができない工事の場合には、同条は適用されません(最高裁昭和62年11月26日判決) 。
破産管財人としては、工事を継続する方が支払う経費よりも、入ってくる請負残代金の方が多く、破産財団の増殖が見込める場合は、工事の継続を選択し、工事の完成を目指すことになります。
もっとも、一般的には、契約不適合や、事故発生時の労災補償の問題などから、工事継続は難しく、解除を選択することが多いと考えられます。
他方、注文者は、破産管財人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に、請負契約を解除するか、それとも工事を遂行して請負代金を請求するのか確答するよう催告することができます。これは、どちらかを選ぶよう催告することであり、残工事を履行せよと催告したり、請負契約を解除せよと催告することではありません。
破産管財人が、その期間内に確答しないときは、請負契約は解除したものとみなされます(同条2項)。
■請負契約が解除された場合の取扱
(出来高が前払金よりも多い場合)
契約が解除されたとき、施工業者が既にした工事のうち可分な部分の給付によっても、注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされます。この場合、破産管財人は、注文者に対し、注文者が受ける利益の割合に応じて残代金を請求することができます(改正民法634条)。
(前払金が出来高よりも多い場合)
他方、出来高を査定した結果、注文者が施工業者に対し支払っていた前払金の方が、出来高よりも多い場合は、注文者は、破産財団に対し、その超過額について、施工業者に支払った代金が破産財団中に現存するときは、その返還を求めることができますし、現存しないときは、その価額について、財団債権として保護され(破産法54条2項)、破産債権よりも優先して弁済を受けることができます。
ただし、財団債権として保護されるのは、あくまで出来高よりも多く支払った前払金の超過額のみです。
破産管財人により、契約が解除された場合、例えば次のような、注文者が被った損害は、破産債権として権利行使することしかできません(同条1項)。
・建物や設備の劣化を防ぐため、注文者が支出した工事の保全費用
・他の施工業者に、残りの工事を引き継がせたことにより、総額の工事費用が増えた分
・工事が遅れたことによる損害破産債権の配当が受けられるかは、財団財産がどれだけ形成されるかによりますが、実際には、全く配当を受けられないか、配当を受けられても、破産管財人により認容された破産債権額の数パーセント程度のことがほとんどなので、あてにはせず、いくらかでも配当を受けられたら儲けもの程度に考えておいた方がよいでしょう。
■工事出来高の査定方法
工事の出来高は、工事代金の内訳明細書や、工程表、その他関係資料等を参考に、工事費目ごとの進捗率に応じて算定します。
破産管財人としては、破産会社の従業員などの協力を得て、工事の出来高の査定をしていくことになります。
これに対し、注文者からは、引継業者が見積もった残工事費用を、当初の工事代金から控除して、既施工部分の現在価値を出来高とすべきとする主張をすることもありますが、このような主張は、本来、破産債権となるにすぎない増加工事費用を相殺的処理により優先弁済受けるのと同様の処理になりますので、破産管財人により認められないでしょう。
■違約金の請求・相殺の可否
破産管財人により、破産法53条に基づき、請負契約が解除された場合、注文者は、破産管財人(破産財団)に対し、請負契約書の違約金条項に基づき、違約金を請求することができるでしょうか?
裁判実務では、違約金請求ができないとする裁判例が多く存在します(東京地裁平成27年6月12日判決、札幌高裁平成25年8月22日判決等)。
同条による解除権は、法によって破産管財人に与えられた特別の法定解除権であり、違約金条項の適用はないと考えられるからです。
また、仮に、違約金が発生する場合でも、その違約金は、破産手続開始決定後に発生した破産債権ですので(54条1項)、注文者が、これと請負代金支払債務などと相殺主張することはできない(67条1項)と考えられます。
■下請業者や設備業者が所有権を主張する場合
工材や設備を納品した下請業者や設備業者が、破産した施工業者から代金が支払われていないことから、これらの所有権を主張して張り紙をしたりする場合があります。
この点、いったん納品した以上、これらの所有権や占有は、施工業者に移転しており、下請業者らが、同意なく引き揚げてくることは自力救済行為として許されません。
もっとも、設備など動産の売主には、動産売買の先取特権が認められ(民法321条)、破産法上、別除権として保護され(破産法2条9号)、破産手続きによらずして、破産管財人の同意を得て、引き揚げることができますので(同法65条)、破産管財人と下請業者らとの話し合い次第となります。
ただし、下請業者らは、既に木材等が建物として組み上げられた場合、施工業者の注文者に対する請負代金債権について、原則として、物上代位権を行使することはできません。
例外的に、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分の請負代金債権に対して物上代位権を行使することができます(最高裁平成10年12月18日決定)。
また、下請業者らと、注文者はとの間には、直接の契約関係がなく、下請業者らは、注文者に対し、直接、下請代金を請求することはできません。
■残りの工事の進め方
破産管財人により請負契約が解除された場合、残りの工事を施工してもらえる業者を探し、改めて請負契約を締結することになります。
この場合、それまで工事を進めていた下請業者などが信頼できるところであれば、そこと直接契約を締結したり、破産した施工業者の社員(現場監督)と直接、工事監督ないしコンサルティング契約を締結したり、足場などのリース業者と直接リース契約を締結したりして、いったん中断した工事を継続する方が、関係者が事情を知っていて、時間もコストも節約することができる場合があります。
実際に、そのようにして、リカバリーされる方もいらっしゃいます。
-
2021.05.14
【不動産売買】中古住宅の雨漏り等による契約不適合責任

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
新築住宅で、雨漏りや漏水があれば、それは当然に瑕疵(契約に適合しない)であるといえ、契約不適合責任を追及することができます。
それでは、中古住宅の場合はどうでしょうか?
買主としては、買って1年もしないうちに、雨漏り等が生じた場合には、瑕疵があるんだから、売主に対し修繕や損害賠償請求することができると思うかもしれません。
しかし、必ずしもそうはなりませんので注意が必要です。なお、【損害賠償】契約不適合による損害賠償請求の要件については、こちら、
また、【不動産売買】契約不適合責任の免責条項とその有効性については、こちらを、それぞれご参照ください。
■雨漏りが契約書等で明示されている場合
中古住宅の売買において、雨漏りの事実や、瑕疵、劣化、損傷の程度が、売買契約書や重要事項説明書等で明示的に示されていて、買主がこれを容認して売買契約が締結された場合には、それらは契約の内容になっており、そもそも契約不適合には該当しません。
東京地裁平成25年9月26日判決も、売買契約において、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないこと、建物及びその設備は経年変化により老朽化・機能低下がみられ、これを原因として補修・修繕等が必要となり、その費用がかかる可能性があることが容認事項とされていたこと、不動産の引渡しは現況有姿のままされること、売主・買主間で雨漏りを修繕する旨の合意がないこと、買主は雨漏りの存在を事前に認識していたというべきであるから、その他、売主が雨漏りを修繕する義務を負うことを認めるに足りる根拠はないと判示して、買主側の請求を棄却しています。
■雨漏りが契約書等で明示されていない場合
旧民法下の瑕疵担保責任について、裁判例は、売買の目的物が通常保有すべきことを取引上一般に期待されている品質・性能を欠く場合,目的物に隠れた瑕疵があるとして、売主はその瑕疵について責任を負う。そして、中古住宅が売買契約の目的物である場合,売買契約当時,経年変化等により一定程度の損傷等が存在することは当然前提とされて値段が決められるのであるから,当該中古住宅として通常有すべき品質・性能を基準として,これを超える程度の損傷等がある場合にこれを「瑕疵」というべきであると判示しています(東京地裁平成17年9月28日判決)。
この考え方は、契約不適合責任においても、該当します。
したがって、中古住宅に雨漏り等が生じた場合に、それが契約不適合に当たるか否かは、次のようなメルクマールで判断されます。
・当該中古住宅に、同種・類似の建物と比べ、通常有すべき品質・性能を基準として,これを超える程度の損傷等があったか。
・売買契約前に、大規模なリノベーションがなされていたか否か。
・売買代金が、当該中古住宅の価格として相場か、それとも高額か。以下、損害賠償を否定した裁判例と、肯定した裁判例をいくつかご紹介させていただきます。
■損害賠償責任を否定した裁判例
(東京地裁令和元年10月17日判決)
ビルを購入したところ、地下受水槽から漏水が発生していることなどが判明したとして、瑕疵担保責任等に基づき、損害賠償した事案につき、当該ビルは、築22年を経た中古ビルであり、現状有姿のまま引き渡すことに当事者双方が合意しているから、当該ビルに経年劣化による様々な不具合が生じていることは、売買契約を締結する上で当然の前提として売買代金等の条件に織り込み済みであると考えられる。したがって、当該ビルに不具合があっても、それが建物の安全性等、建物自体の使用の可否に関わるような重大なものではなく、経年劣化により通常生じ得るようなものである場合には、当該不具合をもって、瑕疵に当たるということはできないというべきであるとして、地下駐車場ピット内に地下水が浸出し、結露が発生するなどしていることについて、ビル自体の使用の可否に関わる重要なものであるとも、経年劣化により通常生じ得る程度を超えるものとも認められないから、ビルの瑕疵に当たるということはできないと判示しています。
(東京地裁平成27年11月30日判決)
買主が中古アパートである建物及びその敷地を買い受けた際、売主らから、雨漏りや腐食は発見されていない旨の説明を受けたにもかかわらず、引渡し後に雨漏りや腐食が発見され、修理費用などの損害を被ったと主張して、売主らに対し、瑕疵担保責任又は説明義務違反に基づき損害賠償請求した事案につき、売買契約に際し、「現在まで雨漏りは発見していない」、腐食を「発見していない」と明記した本件物件状況等報告書を交付したとしてもこの記載は、売主の当該建物の状況に関する認識を示したものにすぎず、これをもって直ちに過去に雨漏りや腐食が生じた物件ではないことを、自己の法律上の責任として保証したとまでは認められない。そして、過去に雨漏りや腐食があったこと自体は、それによって売買契約当時の建物の利用に支障を生じさせるものではなく、売買契約当時、当該建物が23年以上経年していたことも考慮すれば、瑕疵ということはできない旨判示しています。
(東京地裁平成26年1月15日判決)
売主は、契約締結に際し、買主に対して物件状況等報告書を交付し、その中で、物件には経過年数に伴う変化や、通常使用による摩耗、損耗があることを告知している一方、建物躯体及び窓やドアのアルミサッシの品質性能について契約上特段の合意がされたとか、売主が特段の品質性能を保証した事実はないことによると、契約上、売主と買主との間で、売買目的物である当該建物について合意された品質と性能は、築38年の分譲マンションが通常有する程度のものであったということができ、「瑕疵」の該当性も、そのような品質性能を欠いているか否かという観点から判断すべきである。当該建物で壁紙に雨水が浸透する不具合は、建物躯体のひび割れが原因であるとは認められるものの、大規模修繕が行われていない限り、経年により建物躯体に雨漏りを生じるようなひび割れが生じることは一般にあり得ることと認められるなどと判示して、損害賠償請求を棄却しています。
■損害賠償請求を認めた裁判例
(東京地裁平成30年7月20日判決)
売買契約の目的物である建物は、昭和35年新築の中古物件ではあるものの、売買契約が締結される直前に、設備、水回り、電気、内装、外装その他について大規模なリノベーション工事が行われていること、売買代金が築50年以上の建物としては高額であること、売主は、前所有者から、瑕疵担保責任を負担しないという条件で建物を取得している一方で、買主に対し、瑕疵担保責任を負担していることが認められ、そうすると、当該建物は、現状有姿で売買されたのではなく、社会通念に照らし、少なくとも住宅としての最低限の基準を満たす品質・性能を有するものとして売買された、すなわち、雨漏りのしない建物として売買されたとみるのが相当であるとして、洗面室の周囲の雨漏りについては、瑕疵にあたると判示しています。
(東京地裁平成25年3月18日判決)
降雨があった場合に、本件建物部分のうち書斎及び居間にルーフバルコニー側から浸水する状態にあったところ、当該サッシからの浸水が室内の絨毯や畳の交換を要する程度に及んでいることに照らせば、当該サッシの老朽化の程度は、築後30年の経年劣化を考慮しても、通常有する品質性能を欠くものであり、当該建物部分の瑕疵であるというべきである(なお、当該サッシがマンションの共用部分に属するが、当該サッシの瑕疵が当該建物部分の使用収益に直接影響を与えるものである以上は、売買における目的物の瑕疵として売主が瑕疵担保責任を負うべきものと解される)と判示しています。
(東京地裁平成20年6月4日判決)
買主らが、建物の柱等に雨漏りによる腐食とシロアリによる侵食があったところ、売主らが腐食及び侵食を知りつつこれを秘し、腐食及び侵食を容易に知ることができたのに十分な調査をしないで、当該建物を売却したと主張して、売主らに対し、瑕疵担保責任、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償請求した事案につき、ある程度の年数を経た木造建物に雨漏りによる腐食の跡やシロアリによる侵食の跡があったとしても、それが当該建物の土台、柱等の躯体部分にあるのではなく、又は、その程度が軽微なものにとどまるときは、必ずしもこれをもって当該建物の瑕疵ということができない場合があることは否定できないが、当該建物のうち、とりわけサンルームの部分については、土台や柱といった躯体部分に雨漏りによる腐食とシロアリによる侵食があり、その範囲が柱の上部にまで及び、その程度も木材の内部が空洞化するまでに至っており、現に雨漏りがする状態であるというのであるから、当該建物が売買契約締結時において築後12年が経過した木造建物であることを考慮しても、同部分に建物としての瑕疵があることは明らかというべきであるとして、損害賠償請求を認めています。
-
2021.05.10
【損害賠償】歩行者同士の衝突事故

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
私もかつて代理人として示談交渉をしたことがありますが、歩行者同士の衝突事故でも、被害者が思わぬ怪我を負い、損害賠償額が高額になることがあります。
そこで、今回は歩行者同士の衝突事故について、ご紹介させていただきます。
なお、自分でも気づかないうちに、このような歩行者同士の事故についても、対象となる賠償責任保険に加入している場合がありますので、万一、加害者になってしまった方は、保険会社に確認されることをお勧めします。不幸にも、被害者になってしまった方も、加害者に対し、そのような保険に加入してないか確認されることをお勧めします。
■大分地裁令和3年3月15日判決
(事案の概要)
登校中の事故当時13歳の中学2年生の女子(被告)が、対面歩行してきた79歳の女性(原告)と衝突し、原告が尻もちをつくような形で後ろ向きに転倒し、第1腰椎椎体骨折の傷害を負ったという事案です。
(損害賠償責任を肯定)
判決は、次のように判示して、被告の損害賠償責任を認め、約792万円の損害賠償を認めました。
事故は中学校付近の歩道上で発生したものであるところ、当時は被告を含む中学校の生徒が登校する時間帯であり、かつ、歩道は車道外側線から測定しても約220cmの幅員しかなかったのであるから、その当時その場所においては歩行者同士が衝突する危険が具体的に発生していたものといえる。そして、被告は、事故当時、歩道の前方を歩行していた生徒4名を追い抜こうとしていたところ、上記生徒らは2列縦隊で進行しており、上記生徒らの前方の見通しは悪かったのであるから、このような場合、上記生徒らの前方から対向してくる歩行者と衝突して危害を加えることのないよう、対向歩行者の有無及び安全に十分留意しながら歩行すべき注意義務を負っていたものというべきである。
しかるに、被告は、対向歩行者の有無及びその安全に留意することなく、漫然とIの後に追従して前方を歩行していた生徒4名の追い抜きを開始し、対向してきた原告の存在に気付かないまま衝突して事故を惹起したのであるから、被告には上記注意義務を怠った過失があるというべきである。
(過失相殺を否定)
原告は、事故当時、両手に荷物を持った状態ではあったものの、歩道を歩行していたにすぎず、その態様が対向歩行者と衝突する危険を生じさせるようなものであったものとはうかがわれない。として、過失相殺を否定しています。
(素因減額3割)
もっとも、事故の態様は、被告が対面歩行中の原告に衝突したことにより、原告が尻もちをつくような形で後ろ向きに転倒したというものにすぎず、そのような事故態様から重篤な後遺障害が生じることは通常は想定することができず、原告が事故当時79歳の女性であり、骨粗鬆症が加齢的変性により生じたものと考えられることなどの事情を考慮すると、素因減額の割合は30%とするのが相当である。
■東京高裁平成18年10月18日判決
(事案の概要)
交通規制により車両の進入が規制されていた交差点内において、91歳の女性(被控訴人)が南から北に向かって歩行中、同じく本件交差点内を西から東に向かって歩行していた25歳の女性(控訴人)と接触して転倒し、右大腿骨頚部骨折などの傷害を負った事案です。
(損害賠償責任を否定)
判決は、次のように判示して、控訴人の損害賠償責任を否定しました。
事故は、控訴人が知人と並んで、人の流れに従ってゆっくりと歩いて交差点の中央付近に至り、目指す店舗を探そうと首を左後方に向け歩みを止めかかった瞬間、控訴人の右肩から背中、腰にかけて被控訴人が接触したというものである。そして、事故当時交差点内は通行人が非常に多く、混み合っていた上、店を探しながら立ち止まる人も多かったのであるから、このような中で人の流れに従ってゆっくり歩行していた控訴人が、店舗を探そうと左後方を向いて歩みを止めようとし、被控訴人が控訴人の右肩から背中、腰にかけて接触し、その瞬間、控訴人及び同伴の知人が被控訴人の手ないし日傘をつかんで支えようとした事実関係の下において、事故前後における控訴人の歩行ないし店舗の物色行為等に有責性を見出すことは困難であるから、控訴人に注意義務違反があったとは認められないというべきである。
■東京地裁平成4年5月29日判決
(事案の概要)
44歳の女性(原告)が、駅の階段の踊り場から二、三段降りかけたところ、後方より段階の手すりに手を掛けながら駆け降りてきた小学6年生の男子(被告)にいきなり激突され転落し、助骨亀裂骨折等の傷害を負ったという事案です。
(損害賠償責任を肯定)
判決は、被告は、多数の公衆が昇り降りする狭い駅階段では、他人にいきなりぶつかることのないよう通行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失があるものといわざるを得ないとして、約98万円の損害賠償を認めました。
他方、被告の両親の責任については、事故の態様は、被告の過失行為に起因するものであり、原告主張のような無謀な行為であるとはいえないばかりでなく、被告がかねてより素行が悪いと評判の子であり、かつ、事故につき、両親が親権者として監督義務を怠った過失があるとまで認定することは困難であるとして、否定しています。
■東京地裁平成1年3月31日判決
(事案の概要)
浅草寺境内において、不審人物を追いかけて来た警備員(被告)に接触・転倒した通行人(原告)が負傷した事案です。
(損害賠償責任を肯定)
判決は、事故当時、道路は人通りも多く、走行すれば勢い余って通行人に衝突、接触する危険があったといえるから、被告としては、警備員という立場もさることながら、危険を十分弁え、不法行為者を発見し追跡するとしても、通行人の動向に十分配慮を払い危険の発生を未然に防止すべき注意義務があったというべきである。ところが、被告は、これを怠り、不法行為に及んだ者が逃走するや、同人とはもともと顔見知りで、しかも、行為の態様・程度からしても直ちに追跡しなければならない緊急の事態とはいい難いのに、同人の動静のみに注意を奪われ、その追走を急ぐ余り、単なる通行人にすぎない原告に接触したと認められるから、被告には注意義務違背の過失があったといわざるを得ないとして、約690万円の損害賠償を認めました。
■まとめ
以上から、通常に歩行してだけの場合には、損害賠償責任を負いませんが、加害者とされる者が小走りをしていたり、前方不注視があった場合には、損害賠償責任を負う場合がありますので、注意が必要です。
-
2021.05.05
【損害賠償】契約不適合による損害賠償請求の要件

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
ネット上でも、契約不適合に関する解説はたくさんありますが、契約不適合を理由とする損害賠償請求の要件について、正確に、というか詳細に解説にするものが見当たらなかったので、私自身の備忘録的な意味も兼ねて(笑)、今回は、この点について、説明させていただきます。
なお、契約不適合責任の免責条項とその有効性については、こちらをご参照ください。
■契約不適合
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、契約不適合責任を追及することができます。その責任追及の手段の1つとして、損害賠償請求があるのです(民法564条、415条1項)。
目的物の「種類」に関する契約不適合とは、品名、形状・色彩、産地、製造業者等に関して合意した内容と異なること、「品質」に関する契約不適合とは、性質、効用、企画、価値等について合意した基準に満たないことをそれぞれ意味します。もっとも、いずれの契約不適合であっても、効果に変わりはありませんので、両者を区別する実益はありません。
また、目的物に数量不足があったすべての場合に、「数量」に関する契約不適合があったことになるわけではありません。契約当事者が、その契約において、「数量」に特別な意味を与え、その数量を基礎として代金額が決定されたような場合にはじめて、「数量」に関する契約不適合があったことになります。
契約不適合に該当するか否かの判断枠組みは、
・当該売買契約が具体的にどのような物を対象としていたか確定する段階と、
・実際に引き渡された物がその契約内容に適合する性質を有していたかを判断する段階
の2段階からなります。売買の目的物が契約の内容に適合しないことについての主張・立証責任は、債務不履行を主張する買主が負います。
■損害と因果関係
また、契約不適合により、買主が損害を被ったこと、契約不適合とその損害との間に相当因果関係があることも要件となります。これらについての主張・立証責任も買主が負います。
■売主の責めに帰すことができない事由
買主は、売主に対し契約不適合責任を追及するにあたり、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によって生じたことを主張・立証する必要はありません。
これに対し、損害賠償請求を受けた売主は、抗弁として、契約不適合が「債務者(売主)の責めに帰すことができない事由」によるものであったことを主張・立証して損害賠償責任を免れることができます(415条2項)。
もっとも、売主に帰責事由がないとして、損害賠償責任を免れるのは、実務上、不可抗力など例外的な場合に限られます。
■追完の催告の要否
契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(562条1項)。
※ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完請求をすることができません(同条2項)。
そこで、買主が売主に対し、契約不適合炉理由として、損害賠償請求をするにあたり、予め、履行の追完を請求する必要があるか、損害賠償請求権と追完請求権との関係が問題となります。
(追完とともにする損害賠償の場合)
まず、売主により追完されても、填補されない損害(たとえば、遅延損害金の賠償や、転売する機会を失ったことによる得べかりし営業利益)の賠償については、追完請求と両立するものであり、予め追完の催告をしなくても、損害賠償請求することができます。
(追完に代わる損害賠償の場合)
これに対し、買主自らが費用をかけて目的物を修補したり、他から適合する目的物を調達した費用など、追完請求とは両立しない損害賠償の請求については、諸説あります。
代金減額請求権も解除権も、原則として追完の催告を要求していることから、損害賠償請求においても、原則として、売主に対し、まずは追完の請求をし、売主に追完する機会を保証しなければならず、それでも売主が追完しなかった場合にはじめて、損害賠償請求することができるとされています(追完請求権の優位性)。
ただし、次の場合は、例外的に、追完の催告は不要となります(563条2項)。
・履行の追完が不能であるとき。
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
・これらの場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。また、契約不適合に関する規定は任意規定ですので、追完の催告を要せず、直ちに、追完に代わる損害賠償請求をすることができる旨の特約は有効です。そこで、買主がこれを望むのであれば、予め売買契約書にこのような特約を明記しておく必要があるわけです。
■権利行使期間
(種類・品質の契約不適合の場合)
買主は、売買目的物に種類ないし品質に関する契約不適合があったことを知った場合、それを知った時(※引渡時からではありません)から1年以内に、売主に対し、不適合の事実を通知する必要があり、この通知をしないと損害賠償請求をはじめ、責任を追及することができなくなります(566条本文)。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、期間の制限を受けません(同条但書)。また、同条は任意規定ですので、特約でこれと異なる定めを設けることができます。
通知は、単に「契約不適合がある」旨抽象的に告げただけでは足りず、細目にわたるまで告げる必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に不適合の種類・範囲を告げる必要があります。他方、不適合責任を追及する意思を明確に告げて、損害額の根拠まで示す必要はありません。
上記権利行使期間の定めは、債権の消滅時効に関する一般準則の適用を排除するものではありませんので、買主が契約不適合の事実を知った時(主観的起算点)から5年、売買目的物の引渡しを受けて(客観的起算点)から10年で消滅時効にかかります(166条1項)。
(数量・権利の契約不適合の場合)
数量ないし権利に関する契約不適合については、特別な権利行使期間の制限の規定はありません。その結果、債権の消滅時効に関する一般準則が適用され、買主が契約不適合の事実を知った時から5年、売買目的物の引渡しを受けてから10年で消滅時効にかかります(166条1項)。
■損害賠償請求権と解除権との関係
買主が契約不適合を理由に売買契約を解除しても、損害賠償請求権は失われるものではなく、損害賠償請求することができます(545条4項)。
また、買主が買主に対し、追完に代わる損害賠償を請求しても、実際に、その弁済を受ける(あるいは損害賠償請求権が他の債務と相殺される)までは、解除権や代金減額請求権は失われません。
- HOME
- ブログ
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (3)
-
2022年 (6)
-
2021年 (33)
-
2020年 (9)
-
2019年 (8)
-
2018年 (43)
-
2017年 (29)
-
2016年 (40)
-
2015年 (87)
-
2014年 (1)
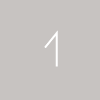
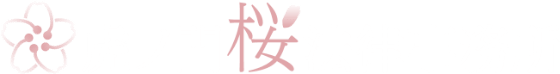
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)