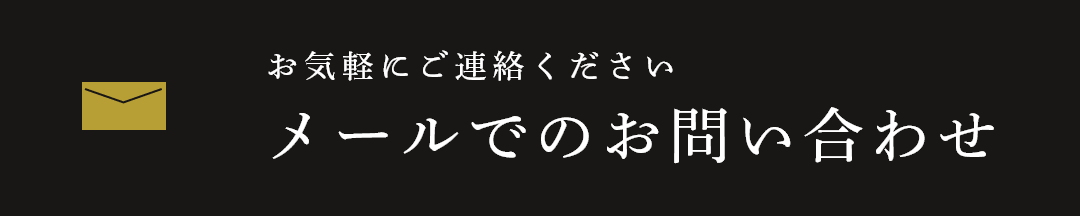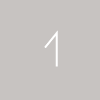特別縁故者であると認められなかった事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
亡くなられた方(被相続人)に、相続人がいない場合、家庭裁判所の決定により、被相続人と特別の縁故があった方(特別縁故者)に対し、相続財産の全部又は一部が与えられることがあります。
今回は、この制度に関し、被相続人Aの従姉の養子であった者Xが、Aとは、生前、本家と分家として親戚づきあいがあった、Aに後事を託された、Aの死後、Aの葬祭や供養等を行うために多額の費用を支出した、A宅の庭木等の維持管理をしたなどと主張し、特別縁故者として相続財産の分与を求めましたが、認められなかった裁判例(東京高裁平成26年1月15日決定)を紹介させていただきます。
裁判所は、XとAとは、生前、通常の親戚づきあいを越える交流があったとは認められず、生前の身分関係及び交流に、Aの境遇(婚姻をせず、子もなく、兄弟姉妹も先に亡くなっている)や、Aの死後のXの貢献を加えて検討しても、XをAと「特別の縁故があった者」と認めることはできないと判断しました。
民法第958条の3、1項において、特別縁故者とは、次のように規定されています。
①被相続人と生計を同じくしていた者(生計同一者)
②被相続人の療養看護につとめた者(療養看護者)
③その他被相続人と特別の縁故があった者
そもそも、この規定ができたのは、遺言があまり行われていない我が国の現状から、被相続人の意思を推測すれば、遺贈を受ける関係にあったと考えられる者に財産を分与することが望ましいことや、特別縁故者となることが多い内縁配偶者や事実上の養子の保護を図るべきことが背景としてあったためです。
そのため、特別縁故者と言えるには、このような制度創設の趣旨に照らし、被相続人との間に生計同一者あるいは療養看護者に準ずる程度の具体的かつ現実的な交渉があり、その者に相続財産の全部又は一部を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる程度に被相続人と密接な関係があったことを要すると解されています(大阪高裁昭和46年5月18日判決)。
今回ご紹介した事例のような関係では、特別縁故者として認められなかったとしても、やむを得ませんね。
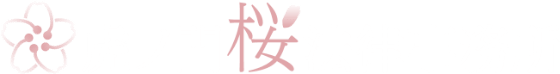
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)