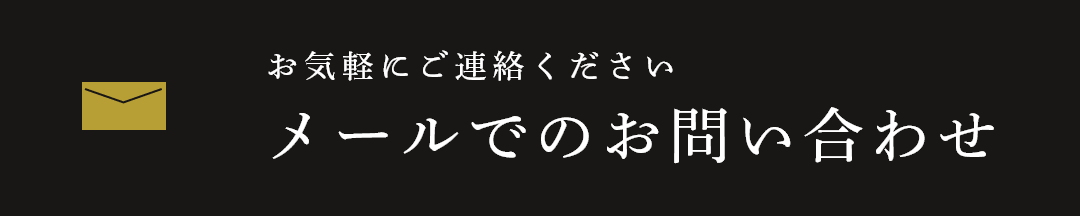-
2021.06.18
【賃貸借】オフィスの原状回復義務

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近、オフィスの賃貸借契約に関し、どこまで原状回復をする必要があるのかというご相談がありましたので、今回は、裁判例を概観しながら、オフィスの賃貸借契約における原状回復の範囲や、諸問題について説明させていただきます。
居住用のアパート・マンションと異なり、オフィスの賃貸借に関しては、消費者保護を考慮する必要がありませんし、市場性原理と経済合理性の支配するオフィスビルの賃貸借では、比較的、賃借人の原状回復義務が認められやすい傾向にはあります。
しかしながら、実務的には、オフィスビルが新築か中古か、オフィスビルの規模、原状回復条項の内容等を個別に検討する必要があります。
■通常損耗・汚損についても原状回復義務を負うか?
(東京高裁平成12年12月27日判決)
当該判決は、以下のように判示して、オフィスビルを新築の状態で借り受けた賃借人には、「契約が終了するときは、賃借人は賃貸借期間終了までに造作その他を契約締結時の原状に回復しなければならない。」旨の原状回復条項に基づき、通常の使用による損耗、汚損をも除去し、建物を賃借当時の状態にまで原状回復して返還する義務があるとしています。
一般に、オフィスビルの賃貸借においては、次の賃借人に賃貸する必要から、契約終了に際し、賃借人に賃貸物件のクロスや床板、照明器具などを取り替え、場合によっては天井を塗り替えることまでの原状回復義務を課する旨の特約が付される場合が多いことが認められる。オフィスビルの原状回復費用の額は、賃借人の建物の使用方法によっても異なり、損耗の状況によっては相当高額になることがあるが、使用方法によって異なる原状回復費用は賃借人の負担とするのが相当であることが、かかる特約がなされる理由である。
もしそうしない場合には、原状回復費用は自ずから賃料の額に反映し、賃料額の高騰につながるだけでなく、賃借人が入居している期間は専ら賃借人側の事情によって左右され、賃貸人においてこれを予測することは困難であるため、適正な原状回復費用をあらかじめ賃料に含めて徴収することは現実的には不可能であることから、原状回復費用を賃料に含めないで、賃借人が退去する際に賃借時と同等の状態にまで原状回復させる義務を負わせる旨の特約を定めることは、経済的にも合理性があると考えられる。
(最高裁平成17年12月16日判決)
しかしながら、その後、最高裁平成17年12月16日判決は、次のように判示しました。
賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。
それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。
そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
これは居住用賃貸借のケースですが、賃貸借の契約の本質から論じており、その考えは、オフィスの賃貸借にも適用されると考えられます。実際、次の大阪高裁判決をはじめ、多くの下級審裁判例において、最高裁平成17年判決の法理が、オフィスの賃貸借にも適用されることが認められています。
(大阪高裁平成1 8年5月23日判決)
賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであって、営業用物件であるからといって、通常損耗に係る投下資本の減価の回収を、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行うことが不可能であるということはできず、また、被控訴人が主張する賃貸借契約の条項を検討しても、賃借人が通常損耗について補修費用を負担することが明確に合意されているということはできない。
(東京簡裁平成21年4月10日判決)
また、東京簡裁の上記判決は、次のように判示して、オフィスビルの賃貸借においても、賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるためには、明確な合意が必要であるとしています。
オフィスビルの賃貸借契約においても、通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、原則として、賃料の支払を受けることによって行われるべきものである。賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせることは賃借人にとって二重の負担になるので、オフィスビルの賃貸借契約においても、賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるためには、原状回復義務を負うことになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、賃貸人がそのことについて口頭で説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解すべきであり、このことは居住用の建物の賃貸借契約の場合と異ならないというべきである。
(東京簡裁平成17年8月26日判決)
東京簡裁平成17年8月26日判決は、次のように判示して、事務所としての利用であっても、利用実態として、居住用の賃貸借契約と変わらないような場合には、ガイドラインに沿って原状回復費用を算定すべきとしています。
東京高裁平成12年12月27日判決における賃貸物件は保証金1200万円という典型的オフィスビルであり、しかも新築物件である。それに比して、本件物件は、仕様は居住用の小規模マンション(賃貸面積34.64㎡)であり、築年数も20年弱という中古物件である。また、賃料は12万8600円、敷金は25万7200円であって、事務所として利用するために本件物件に設置した物は、コピー機及びパソコンであり、事務員も二人ということである。このように本件賃貸借契約はその実態において居住用の賃貸借契約と変わらず、これをオフィスビルの賃貸借契約と見ることは相当ではない。すなわち、本件賃貸借契約はそれを居住用マンションの賃貸借契約と捉えて、原状回復費用は、いわゆるガイドラインにそって算定し、敷金は、その算定された金額と相殺されるべきである。
■原状とはスケルトン状態か?オフィスの標準仕様か?
東京地裁平成29年3月27日判決判決は、賃貸借契約締結前の状態がスケルトン状態であったのに対し、契約書案の別紙区分表には、具体的なオフィスの標準仕様が定められており、どちらの状態に戻すのが原状回復かが争われた事案につき、
契約が定める原状回復義務は、「区分表における標準仕様」を「原状」とみなして、これを前提とする原状回復義務を賃借人に負わせるものであるところ、この区分表の標準仕様としては、オフィス仕様の建築・内装、設備が具体的に指定されており、かつ、この区分表は、契約書(案)の別紙として事前に賃借人の取締役にメール送付されていることが認められるるとして、賃借人は、原状回復とは契約締結前の状態(スケルトン状態)に戻すものにほかならないと主張するが、これと異なる明示の合意がされている以上、当該合意に従うべきことは当然であり、賃借人の上記主張は採用できないとし、賃借人は、原状回復義務として、賃借人の主張するスケルトン状態への回復ではなく、賃貸人の主張するオフィス仕様に変更する工事を行う必要があったというべきであると判示しています。
■賃貸人は、未施工の原状回復費用を保証金から控除できるか?
東京地裁平成29年9月6日判決は、原状回復条項には、賃借人が建物の明渡し時に原状回復の処置を執らなかったときは、賃貸人が賃借人の費用で原状回復の処置を執ることができる旨を定められていたが、賃貸人が原状回復工事をすることなく新賃借人に建物を貸し渡し、新賃借人が新内装工事をし、賃貸人が原状回復費を現実に支出しなかったという事案ですが、
未施工の原状回復工事に係る原状回復費を保証金から控除することができると解する合理的な理由は見当たらないとして、賃貸人が、未施工の原状回復費用を保証金から控除することを否定しています。
■賃貸人が賃借人の代わりに行った原状回復工事の費用は少しでも安価でなければならないか?
東京地裁平成29年1月18日判決は、原状回復工事は、本来であれば賃借人において行うべき工事を賃貸人が行ったものであり、賃貸人において少しでも安価な費用で工事を行う義務があるとはいえないから、その費用が不相当に高額でない限り、原状回復費用を敷金から控除することが許されると判示しています。
-
2021.06.16
【不動産】公有地の時効取得に関する判例等

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近、公有地の時効所得の可否が問題となるご相談を受けましたので、今回は、判例等をご紹介させていただきます。
結論から申し上げますと、公有地でも、公用が廃止されていれば、時効取得することができます。
公用の廃止は、明示的なものに限らず、黙示的なものでも構いません。
ただし、公有地の取得時効が認められるためには、占有者が、自主占有を開始した時までに(黙示的にも)公用が廃止されていなければなりません。
また、占有者の行為によって公有地としての形態、機能を失ったにすぎないような場合には、公有地として維持すべき理由がなくなっていたとはいえません。
■ 黙示的な公用廃止が認められる条件
黙示的な公用廃止に関しては、リーディングケースとなる、最高裁昭和51年12月24日判決がありまして、
公共用財産が、
① 長年の間事実上公の目的に供されることなく放置され、
② 公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
③ その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、
④ もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないと判示しています。
当該事案は、係争地は、公図上水路として表示されている国有地であったが、古くから水田、あるいは畦畔に作りかえられ、田あるいはその畦畔の一部となり、水路としての外観を全く喪失し、係争地及び田は、被上告人の祖父が借り受けて小作していた当時から、幅の細い畦畔によつて合計四五枚の水田に区分けされていたというものです。
■ その他の最高裁判例
(最高裁昭和52年4月28日判決)
対象土地を隣接地とともに買い受け、所有の意思をもつてその占有を始め当時、対象土地は、既に隣接地と一体をなして宅地の一部と化し、道路として利用されることもその必要もなくなっていたこと、その後間もなく対象土地と隣接地に跨って二棟の建物を建築し、当初の占有者の死亡後も対象土地はその承継人らによって建物の敷地の一部として平穏かつ公然に占有を継続されてきたが、現在に至るまで対象土地が道路として利用された形跡は全く存しないことが認められるから、対象土地は黙示的に公用が廃止されたものというべきであると判示しています。
(最高裁平成17年12月16日判決)
長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきであり、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となるというべきであると判示しています。
(最高裁昭和61年12月16日判決)
ちなみに、黙示の公用廃止が問題になった事案ではなく、満潮時に海面下に没し,干潮時に海面上に現れる干潟が民法86条1項の土地に当たるか否かが争われた事案において,上記最高裁判決は、
海は,特定人による排他的支配の許されないものであること,現行法上,海の一定範囲を区画してこれに所有権を設定することを認めた実定法規はないことなどを理由に,海は,海水に覆われたままの状態では,所有権の客体たる土地に当たらないと判示しています。
■ 肯定した裁判例
下級審裁判例のうち、公有地の時効取得を認めたものとしては、次のものがあります。
(大阪高裁平成15年6月24日判決)
控訴人らが、国有の里道の一部について取得時効を主張し、国に対して、その所有権の確認を請求した事案において、旧国鉄が新幹線用地の代替地として係争地を含む土地を提供する必要があったことから、国としては、係争地については、いずれ明示の公用廃止をする意思であり、そのために旧国鉄による係争地の整地を了承・承認していたものと考えるのが自然かつ合理的であるから、係争地について黙示の公用廃止がされたものと認めるのが相当であるとして、取得時効の完成を認めています。
(東京地裁平成10年2月23日判決)
取得時効の対象となる道路は、昭和27年に東京都道となり、翌昭和28年、目黒区が東京都から都道の一括移管を受けて特別区道として路線の認定をし、供用を開始した結果、目黒区の特別区道となったものです。
当該道路上に建物が存在し、その東端がコンクリート壁で閉鎖されている以上は、当該道路は道路としての形態をもはや有してはおらず、また、道路としての機能も失われている、付近の建物が当該道路を必要としていない現状からして、黙示的に効用が喪失されたと認められると判示しています。
なお、土地の占有者が、所有権者である国に対し、いったんはそれらの払下げを受けることを希望する旨の意向を表明した後に、取得時効を援用する旨の意思表示をした場合について、占有者が時効を援用するに至ったのが国から払下げを拒否されたためであるとの事情が認められることを理由に、占有者は時効援用権を喪失していない旨判示しています。
(東京地裁昭和63年8月25日判決)
係争地付近は完全に宅地化されており、それぞれの居住住民の敷地のほかに周辺に道路が存在したことをうかがわせる痕跡すらない状況にあることが認められ、係争地は、公共用財産としての形態、機能を全く喪失しており、前所有者の時代以前から引き続き私人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのために実際上公の目的が害されることもなかったことが明らかであるから、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなったものというべきであり、係争地については黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となりうるものと判示しています。
(東京地裁昭和6 0年9月25日判決)
被告は、本件係争地は里道であり公共用財産であるから取得時効の対象にならない、と主張する。そして、証拠によれば、本件係争地が里道であつたことがうかがえなくもない。
しかしながら、公共用財産であつても、それが、長年の間、事実上公の目的に供されることなく放置され、公共用財産としての形態及び機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したにもかかわらず、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないものというべきであると判示しています。
■ 否定した裁判例
他方、下級審裁判例のうち、公有地の時効取得を認めなかったものとしては、以下のものがあります。
(東京高裁平成26年5月28日判決)
当該裁判例は、次のように判示しています。
本件の市有通路のように、予定公物であって、現に道路としての形態及び機能を有しており、かつ黙示の公用開始決定があった道路は、取得時効期間の起算点たる占有開始の時までに黙示的に公用が廃止されたと認められるような特段の事情がない限り、取得時効の規定の適用がない(取得時効が成立しない。)と解するべきである。なぜならば、このような財産は、現に公共の用に供されている公有財産であるので、取得時効の規定の適用に関しては、実質的には行政財産と同じように扱うのが適当であるからである。
本件についてこれをみるのに、係争地(構築物敷地部分を含む。)は、被控訴人が構築物を設置して構築物敷地部分の排他的占有を開始するまでの間、道路としての形態、機能を維持して公衆の自由な通行という公共目的に供用され続けていたにもかかわらず、被控訴人による構築物敷地部分の排他的占有開始により、公衆の自由な通行の妨害という公共の利益に反する事態が現実に発生したほか、被控訴人の時効取得を認めると構築物敷地部分の道路法上の道路(行政財産)としての供用開始という公共目的が実現不可能になるという事情が認められる。そうすると、係争地(構築物敷地部分を含む。)は、市有地となってからの構築物の設置までの期間の占有開始を原因とする取得時効を主張しても、取得時効の規定の適用はなく、取得時効が成立しないというべきである。
(さいたま地裁平成17年6月8日判決)
当時、水路状の窪地が土地上に存在ししたこと、一斉測量調査時に土地と周囲の境界に境界杭が埋設されその土地の境界が確認され公共用財産として認識されていたこと、その後、原告が土地を土盛りし埋立整形したことにより完全に水路状の窪地が存在しなくなってしまったことが認められ、このような経緯にも鑑みると、原告の土地占有開始時において、土地の水路が長い間事実上公の目的に供用されることなく放置されていたとまではいえず、原告のその後の行為によって公共用財産としての形態、機能を失ったにすぎないから、公共用財産として維持すべき理由がなくなっていたともいえず、そうすると、当該土地が原告占有開始時に黙示の公用廃止が認められるべき要件が満たされていたとはいえないと判示しています。
(東京高裁平成3年2月26日判決)
当該裁判例は、次のように判示しています。
公共用財産の取得時効が認められるためには、自主占有開始の時点までに黙示的に公用が廃止されていなければならない。
公共用財産としての形態・機能が失われ、黙示的な公用廃止の状況にあつたというためには、係争の部分だけに着目するのではなく、公用財産が供用された目的に即して地域的広がりを持つた全体として観察し、原状回復が可能であるかどうかを判断しなければならない。
・係争地が買収直後に、土地台帳に官有道路成、除租と記載されている事実
・道路の路面と土地との間には約2メートル程度の高低差がある事実
・係争地は、明治44年ないし昭和17年には、道路の路面から土地までの間の道路の構成部分としての法面又は道路の維持保全に必要な道路敷地として現実に使用されたものと推認することができること。
・係争地の占有を開始した当時、上記事実があったからといって各土地部分について道路の法面としての形態と機能を喪失するにいたったものと認めることはできない。したがって、係争地は占有開始当時未だ公共用財産としての形態、機能を全く喪失したものとはいえず、また係争地について公共用財産として維持すべき必要性がなくなったともいい得ないから、係争地につき黙示の公用廃止があったと認めることはできない。
(東京高裁昭和63年9月22日判決)
当該裁判例は次のように判示しています。
本件土地は、旧市道が耕地整理事業によって拡幅されることになり、その拡幅部分の道路敷として被控訴人の所有とされたもの、すなわち公共用財産とすることを予定してそれに備えた工事を施行し、ただ、府県道とする認定あるいは拡幅にともなう市道区域の変更、供用の開始の手続だけが未了の状態の土地であったのであり、しかも、既に公共の用に供されていた旧市道の法面ともなっていたのであって、このような土地については、公共用財産に準じて原則として取得時効が成立しないものと解すべきである。
戦時中に本件土地にも防火用水が掘られたとはいっても、それは緊急的一時的なものであって、その土地本来の用法を変更する態のものでないことはいうまでもない。
-
2021.06.08
【不動産】土地の時効取得における占有とは?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近、土地の時効取得が問題となる事案について、ご相談を受けましたので、今回は時効取得が認められる要件の中でも、「占有」とは何かについてご説明し、裁判例を紹介させていただきます。
■時効取得の要件
まず、前提ですが、所有権の時効取得の要件は次の通りです(民法162条1項)。
これら要件をすべて満たす場合には、対象物の所有権を時効取得することができます。・20年間
・所有の意思をもって
・平穏かつ公然と
・他人の物を
・占有するまた、占有の開始時に、自分の物であると信じて占有をし、そう信じたことに過失がない場合には、10年間で時効取得することができます(同条2項)。
■占有とは?
この点については、リーディングケースとなる最高裁昭和46年3月30日判決があって、「一定範囲の土地の占有を継続したというためには、その部分につき、客観的に明確な程度に排他的な支配状態を続けなければならない」と判示しています。
ちなみに、上記最高裁判決では、山林の一部に、「杉苗多数を植えつけ、その後その刈払い等の手入れを続けて植林の育成に努めてきた」り、「係争地内から桑葉を採取した」というだけでは、占有を否定しています。
■占有を肯定した裁判例
(東京地裁昭和4 7年3月30日判決)
代々、対象土地が畑作等に利用され、鶏舎、物置その他の附属施設を設けて使用されていた事案で、継続的な占有、時効取得を認めています。
■占有を否定した裁判例
(大阪地裁平成10年12月8日判決)
原告は、本件土地と被告土地との間に鉄条網を設置したり本件土地を測量するなどしているが、昭和42年ころ以降は、本件土地において野菜等の作付けがされたことはなく、シュロなどの雑木が雑然と植えられているにすぎないのであるから、仮に、原告が年に一度その木の枝打ちをするなどして管理をした事実があったとしても、それが、本件土地についての客観的に明確な程度の排他的な支配状態を示すものとはいえないから、このような占有に基づいて取得時効の成立を認めることはできないと判示しています。
(東京地裁昭和62年1月27日判決)
係争山林につき、当初ある程度の明認方法を施したほかは、ある期間バスを置いて境界線の一部に鉄条網を張り、立札を立て、境界石を埋設するなどの行為をしたとか、時々現地を訪れて様子を見たというに過ぎないときには、時効取得の基礎となる占有があったとは認められないと判示しています。
(宮崎地裁昭和59年4月16日判決)
山林の時効取得の要件としての占有は、成長した杉立木の年数回の見回り、木払いとか、数年に一回の間伐などをなしたのみでは足りず、適当な場所に標木を立てこれに目印をするなどしていわゆる明認方法を施すとか、立木周辺に棚を認けるなどのように他人が立木が何人の支配に属するかを知り得るような施設をなし、もつて排他的支配の意思を明確に表示するなどして客観的に明確な程度に排他的な支配状態を続けることを要すると解すべきところ、全証拠によるもこれを認めるに足りないとして、時効取得を否定しています。
(東京高裁昭和55年12月16日判決)
当事者双方が係争地に苗の植付をし、その後下刈を行つている等、当該土地の管理占有が競合してなされていたものと認められる場合には、取得時効の要件たる占有継続はないと判示しています。
(札幌高裁昭和53年12月21日判決)
畑にバラス(砕石)を散布していたという事案について、移動の困難な建物、石標等と異なり、地表に散布されたバラスは、通常は人為的に容易にこれを除去、移動させることができるし、また自然に散逸、移動することもあり得るから、バラスの散布範囲が10年間全く変化しなかったと推認することは、特段の事情がないかぎり、経験則に照らし相当ではないとして、占有範囲が不明確であるとして、原審に差し戻しをしています。
(その他の裁判例)
その他、次のようなケースでは、時効取得の基礎となる占有があったとは認められないと判示されています。
・土地にある泉から他に水を引用すること(大審院大正8年5月5日判決)
・通行と隣地の古井戸使用のため利用すること(東京高裁昭和48年8月28日判決)
・通行の際に土地の状態を観察・監視すること(札幌高裁昭和57年7月19日判決)
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2022年 (3)
-
2021年 (11)
-
2016年 (1)
-
2015年 (9)
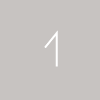
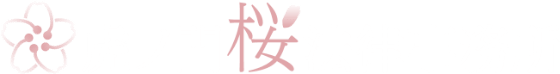
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)