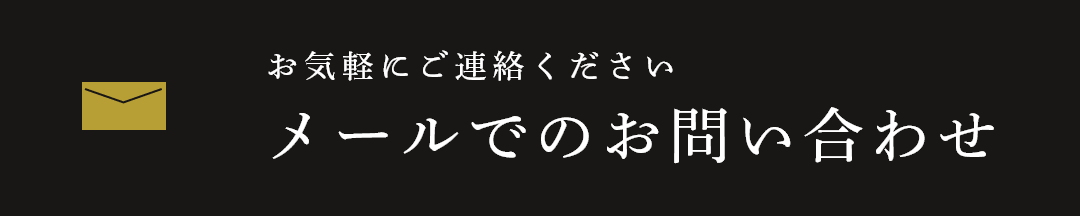-
2021.05.25
【損害賠償】マンション管理について、理事や管理会社の善管注意義務違反を認められるケース

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
一般に、管理組合の役員と管理組合の法律関係については、役員を受任者とし、管理組合を委任者とする委任契約が成立しているものと解され、受任者(理事長その他の役員)は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。
もっとも、どのような場合に善管注意義務違反となるかについては評価の問題であり、悩まれる方もいらっしゃると思います。前回は、裁判例上、善管注意義務違反が認められなかったケースについて、ご紹介させていただきましたので、今回は、裁判例上、善管注意義務違反を認めたケースについて、ご紹介させていただきます。
■会計担当理事の横領に関する他の理事の責任
(会計監査役員)
会計監査役員として、会計担当理事Aが作成した前年度の収支決算報告書を確認・点検し、会計業務が適正に行われていることを確認すべき義務があったにもかかわらず、Aから示された虚偽の収支決算報告書の記載とAが偽造した残高証明書の残高等を確認するだけで、預金口座の通帳の確認をせず、Aによる横領行為を看過したものであった。そして、Aが示した預金口座の残高証明書は、Aが自分のワープロで偽造したというものであって、その体裁等からして真実の銀行発行の預金口座の残高証明書の原本とはかなり異なるものであったことが推認され、このような偽造された残高証明書を安易に信用し、Aが保管しており、その確認が容易である預金口座の預金通帳によって残高を確認しようとしなかった会計監査役員には、善管注意義務違反があったと認めざるを得ない(東京地裁平成27年3月30日判決)。(理事長)
理事長として、前年度の収支決算報告書を作成して総会で自治会員に報告する義務を負っていたものである。したがって、たとえ会計については会計担当理事に委託しており、また、会計監査役員による会計監査が行われていたとしても、やはり理事長が自治会員に対して収支決算報告をすべき最終的な責任者であることに照らすと、会計担当理事Aが作成した収支決算報告書を確認・点検して適正に行われていることを確認すべき義務があったといわざるを得ない。それにもかかわらず、理事長は、Aに預金口座の管理、その預金通帳及び銀行用印鑑の保管を任せていたにもかかわらず、会計の報告につき、定期総会の直前にAから簡単な説明を受けるのみであって、預金口座の通帳の残高を確認することなく、また、会計監査役員に対し、預金口座の通帳を確認するなどの適正な監査をすべき指示を出したり、適正な監査をしているかを確認したりすることもなく、その結果、Aによる会計業務の具体的内容について十分な確認をしないままとしていたものであって、このような理事長には、善管注意義務違反があったと認めざるを得ない(同上)。(副理事長・責任否定)
副理事長においては、規約上も実際の職務分担のいずれにおいても、自治会の会計事務について具体的に何らかの権限が与えられていたものではないところ、このような副理事長において、会計事務について何らかの措置を講ずべき場合とは、理事長が会計に関して行っていた行為について何らの補佐をしなければならない状況が存在することになった場合又は理事長に事故があった場合であると解される。しかるところ、当時、副理事長自身はもちろん、理事長やその他の自治会関係者においても、自治会の会計事務において副理事長が何らかの措置を講ずべき状況にあると認識されておらず、また、理事長に事故があるとの状況にもなかったことに照らすと、会計担当理事の横領行為につき、副理事長において予見して何らかの措置を講ずべきであったということはできず、副理事長に自治会に対する善管注意義務違反があったと認めることはできない(同上)。■監査報告書の無断作成
理事長は、管理組合の監事から委任を受けていないにもかかわらず、監事を代理して監査報告書を作成したものであるところ、監事は、理事による業務執行が適正に行われているか監査するための機関であることにも鑑みれば、理事長が、監事が作成した監査報告書を議案書に添付せずに、自ら無権限で作成した監査報告書を添付して組合員に交付したことは、管理組合の理事長としての善管注意義務に違反する(ただし、これによる管理組合への損害の発生については否定。東京地裁令和2年7月10日判決)。
■監事候補者の不実記載
理事長は、Gが管理組合の監事に立候補していることを認識していたのであり、管理規約によれば、理事長は、総会を招集するものとされ、その際には、会議の目的を示して組合員に通知を発しなければならないとされているのであるから、Gが監事に立候補していることを通常総会の議案に記載すべき義務を負っていたと認めることができ、理事長がこれを故意に議案に記載しなかったことは、理事長としての善管注意義務に違反する(ただし、これによる管理組合への損害の発生については否定。東京地裁令和2年7月10日判決)。
■共用部分の総会決議を経ない賃貸
マンションのラウンジであったところをRの店舗をして賃貸することとなったのであり、賃貸部分は従来の用途を全く変えたものといえるから、共用部分の変更に当たる。共用部分の変更をするためには管理組合の総会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議を経る必要があるから、理事長は、Rとの間で、賃貸借契約を締結するにあたり、総会での決議を経る必要があった。しかし、理事長は、賃貸借契約を締結するに際し、総会での決議を経ていない。理事長は、マンションの業務を法律や規約に従って行わなければならない。そうすると、理事長が総会での決議を経ないまま賃貸借契約を締結したことは、善管注意義務に反する(福岡地裁平成30年3月7日判決)。
■共用部分の管理
変色の生じた外壁部分は、共用部分に当たるところ、管理組合は、規約上敷地及び共用部分等の管理責任を負っている。したがって、管理組合は、同外壁部分につき管理責任を負い、その原因や修理経過、今後の修理計画について把握する義務がある。この義務が個々の組合員に対して負うものかはともかく、管理組合は、原告が、当時の管理組合理事長に対し、工事の実施に関する資料の提出を要求した際、一切の資料がないとして、この要求に応じなかったことからすれば、それ以前に外壁の補修工事が行われた事実を含め、変色の原因につき詳細を把握していなかったと認められ、したがって、上記義務を怠ったことが認められる(ただし、マンションの価値下落との因果関係は否定。横浜地裁平成13年12月28日判決)。
-
2021.05.24
【損害賠償】マンション管理について、理事や管理会社の善管注意義務違反が認められないケース

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
一般に、管理組合の役員と管理組合の法律関係については、役員を受任者とし、管理組合を委任者とする委任契約が成立しているものと解され、受任者(理事長その他の役員)は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。
また、管理会社は、管理組合に対し、管理委託契約上の善管注意義務を負っています。
もっとも、どのような場合に善管注意義務違反となるかについては評価の問題であり、悩まれる方もいらっしゃると思いますので、その参考にしていただくため、今回は、裁判例上、善管注意義務違反が認められなかったケースについて、ご紹介させていただきます。
なお、今回は、理事や管理会社が管理組合に対し、具体的にどのような善管注意義務を負うかや、どのような場合に、その善管注意義務に違反したと評価できるかについて判示した裁判例を紹介するものであり、事実認定について争いがあった裁判例(例えば、横領行為があったか否かなど)については、取り扱いません。
■相見積をとったり、費用の妥当性を検証しなかった場合
東京地裁平成31年1月24日判決は、管理組合の役員となる資格は管理組合の組合員であることのみであり、特別な知識、素養等を要求されていないことからすれば、誠実義務は、管理組合の意思決定機関である総会の決議に従って、その執行を行うことを基本とするものであって、マンションの管理業務を業者に外注するに際して、複数の業者から相見積りを取得して比較検討したり、周辺相場を確認できる資料を取得したりするなどして費用の妥当性を検証すべき法的な義務が常に課されていると解することはできないと判示しています。
■交換周期よりも早い工事の実施
東京地裁令和2年7月10日判決は、国土交通省策定のマンション管理標準指針コメントは、各備品の一般的な耐用年数等によって改修の周期の一つの目安を示しているにすぎず、郵便受け工事は、従前の郵便受けが老朽化したとして交換したものではなく、郵便物の大型化などによって、その使用に不都合が生じるようになったために交換したと認められるのであり、郵便受けの一般的な耐用年数経過前の交換であったとしても、マンションの居住者の要望に応じてされた適切な工事であったとし、総会決議を得て、これよりも早く交換をしたからといって、直ちに理事長としての善管注意義務に違反することにはならない旨判示しています。
また、同判決は、交換周期よりも早い自転車置場の工事についても、大規模修繕に向けた建物調査診断報告書には、駐輪設備に腐食が見られる旨の指摘があること、改修前の駐輪設備では、登録された自転車の台数も賄えない状態となっている上、2段式ラックの上段も使用できない部分が多く、居住者からも駐輪場整備の要望が寄せられていたことから、マンションの居住者の要望に応じてされた適切な工事であったと認められるとして、善管注意義務違反を否定しています。
■割高なリース契約の更新
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理組合が従前の防犯カメラを利用していればリース料が安く済んだ旨主張するが、防犯カメラ更新によるリース料が、一般的な相場を離れて不相当に高額であったとか、新たな支出が従前の防犯カメラと更新後の防犯カメラの機能面の違いに明らかに見合っていないとの主張立証はないとし、防犯カメラには、価格や機器の質の面で様々なものがあり得るところ、機能面での違いを無視して、最も安価なものを選ばなければ直ちに理事長としての善管注意義務違反になるわけではない旨判示しています。
■修繕工事の優先順位の判断
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理組合が大規模修繕工事の際、屋上防水工事を実施しなかったことを問題にしたことについて、各工事等は有効な総会決議を経て実施されているのであるから、工事等の優先順位は管理組合の組合員の総意により定められたものというべきであることに加えて、大規模修繕に向けた建物調査診断報告書の総合所見にも、屋上防水には大きな問題は見られないが、耐用年数を迎えていることから、大規模修繕工事と同時に全面改修をすることを勧める旨の記載がされているのであって、屋上防水工事を直ちに実施しなければならない旨の指摘もされていないことから、大規模修繕工事の際に屋上防水工事を実施しなかったことをもって、理事長としての善管注意義務違反があったと認めることはできないと判示しています。
■総会議案書の記載
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理会社が、臨時総会の議案書において、将来の修繕予定項目を列挙した中の一つとして、機械式駐車場に関する工事を挙げたことが認められるが、当該記載は、屋上及びルーフバルコニーの防水工事の議案説明のために、今後、予想される支出を列挙したものにすぎないし、仮に、将来、当該支出が議案として提出された場合に、管理組合において、問題であると考えるのであれば、その支出を承認しなければ足りるものであるから、そのような記載することが、善管注意義務違反に当たるとは認められない旨判示しています。
■総会議事録の記載
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理規約により、議事録は、総会の議長である理事長が作成することとされており、管理会社は、単にその素案を作成したにすぎないものであるし、管理組合が虚偽であると指摘する具体的内容は、「一生懸命やってこられたと信じたい」と記載すべきところを「やられてきたことには問題が無い」と記載したというものであって、結局、総会出席者の発言内容の要約が不適切であったというものにすぎず、理事長が、署名に当たって訂正すれば足りる程度のものであって、現にそのようにされているのであるから、上記をもって、管理会社に善管注意義務違反があるとは認められない旨判示しています。
■理事を解任された者に対する理事会資料の送信(情報漏えい)
東京地裁令和2年7月10日判決は、管理会社が、理事を解任された元理事長に対し、理事会の資料を送信したことについて、これらは、管理組合の運営にかかる理事会の資料等の案文等にすぎないものであって、これらの文書の中にいかなる秘密が含まれ、これを元理事長に開示することがいかなる意味で管理組合の管理運営に支障を来すのかについて、具体的な主張立証はないから、これらを管理組合の組合員である元理事長に対して開示することが直ちに守秘義務違反に当たるとはいえないし、これらの書面の交付がおこなわれたのは、元理事長が臨時総会で解任されてから間もない、未だ混乱した状況下での行為であることにも鑑みれば、管理会社に管理委託契約上の善管注意義務違反があったとは認められない旨判示しています。
■大雨による駐車場に止めていた自動車の浸水事故
東京地裁平成28年9月12日判決は、マンションの居住者かつ区分所有者が、マンションの機械式駐車場の地下部分に自己所有の自動車を駐車していたところ、台風に伴う大雨による駐車場の浸水事故により、自動車を廃車処分せざるをえなくなったとして、マンションの管理業者に対し、被害者の主張する通知義務、警報装置設置等義務及び土嚢設置等義務は、いずれも自動車の浸水事故を未然に防止するために何らかの措置をとることを内容とするものであるところ、当該管理業務契約においては、予め浸水事故防止措置をとることに関する定めはないことや、当該駐車場では、過去に自動車の浸水事故が発生したことはなく、管理業務契約に定められている業務内容を超えて、浸水事故を防止するための措置をとる義務の存在を基礎づける事情はないとして、損害賠償請求を否定しました。
-
2021.05.18
【建築トラブル】施工業者が破産した場合、どうする?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近も、アパートの階段崩落事故に関連して、施工業者が破産しましたが、施工業者(請負人)が破産して、建築工事がストップしてしまうことは度々起こることででして、私も相談を受けることがあります。
思いがけず、このような事態に陥って、お困りの注文者の方もいらっしゃるのでしょうから、今回は、施工業者が破産した場合の対応方について、ご説明させていただきます。
■「住宅完成保証制度」加入の有無の確認
「住宅完成保証制度」とは、施工業者が破産し工事を継続できなくなった場合に、住宅の完成に向けた工事費用や破産などにより戻ってこないお金(前払金等)の損失を保証したり、引き継ぎ業者をあっせんすることができる任意加入の保証制度です。
破産した施工業者がこの保険に加入していた場合には、その保険金により救済を受けられる場合がありますので、まず、この点を確認してください。
ただし、保証限度額が定められていたり、増嵩工事費用(未履行部分の工事を別の業者が代わりに施工した場合で、手戻り工事費や既施工部分の検査などを行う費用)の限度額が定められており、全額の保証を受けられるとは限りません。
なお、「住宅完成保証制度」と「住宅瑕疵担保責任保険」とは、別のものですので、注意が必要です。
後者の「住宅瑕疵担保責任保険」は、引き渡された新築住宅に特定の瑕疵があった場合に、補修等を行った施工業者や住宅販売業者に保険金が支払われる制度です。施工業者が破産した場合に、工事を続行するためにこの保険制度を利用することはできません。
■「住宅完成保証制度」に加入している場合の注意点
一般的に、次のような事実が発生したときには、発注者は、保険会社に対し、遅滞なく、通知することが求められています。
・建築工事の全部または一部の施工の中止を知ったとき。
・施工業者が倒産等、建築工事が継続できなくなる事実が発生したことを知ったとき。
・施工業者につき、破産、民事再生、会社更生手続開始の申し立てがあったことを知ったとき。
・発注者が、建築工事請負契約を解除しようとするとき(書面での通知)。
正当な理由なく、これら通知義務を履行しないと、保険会社による保証債務の履行を受けられなくなる場合がありますので、注意が必要です。
また、施工業者が倒産等した場合、保険会社(の依頼を受けた鑑定人)が、当初締結した請負金額に係る見積単価に基づき、出来高の算定を行うことになります。
■その他、初動で行うべきこと
(工事の進捗状況の撮影)
後述の通り、破産管財人が請負契約を解除する場合には、工事の出来高の査定が必要不可欠になりますので、速やかに、工事現場で、工事の進捗状況を詳細に撮影し、証拠を保全すべきです。(出来高の査定)
また、施工業者の従業員や、他の専門業者の協力を得て、出来高の査定を行ってください。なお、工事現場の占有は施工業者(破産後は、破産管財人)にあると考えられますので、工事現場に立ち入る場合には、破産管財人に立ち会ってもらうか、破産管財人の同意を得て行うべきです。
(建築中の建物の保全)
工事途中の建物を長期間放置しておくと、風雨によって建物が劣化してしまうような場合には、応急措置としてブルーシートをかけるなどの保全行為については、損害の拡大を防ぐために許されると考えられますが、念のため、破産管財人の了承を得て行ってください。■破産管財人からの解除
工事が未完の場合、基本的に、施工業者の破産管財人は、請負契約を解除するか、あるいは残りの工事を履行して、注文者に対し、残りの請負代金を請求するか、選ぶことができます(破産法53条1項)。ただし、その工事が破産をした施工業者にしか完成することができない工事の場合には、同条は適用されません(最高裁昭和62年11月26日判決) 。
破産管財人としては、工事を継続する方が支払う経費よりも、入ってくる請負残代金の方が多く、破産財団の増殖が見込める場合は、工事の継続を選択し、工事の完成を目指すことになります。
もっとも、一般的には、契約不適合や、事故発生時の労災補償の問題などから、工事継続は難しく、解除を選択することが多いと考えられます。
他方、注文者は、破産管財人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に、請負契約を解除するか、それとも工事を遂行して請負代金を請求するのか確答するよう催告することができます。これは、どちらかを選ぶよう催告することであり、残工事を履行せよと催告したり、請負契約を解除せよと催告することではありません。
破産管財人が、その期間内に確答しないときは、請負契約は解除したものとみなされます(同条2項)。
■請負契約が解除された場合の取扱
(出来高が前払金よりも多い場合)
契約が解除されたとき、施工業者が既にした工事のうち可分な部分の給付によっても、注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされます。この場合、破産管財人は、注文者に対し、注文者が受ける利益の割合に応じて残代金を請求することができます(改正民法634条)。
(前払金が出来高よりも多い場合)
他方、出来高を査定した結果、注文者が施工業者に対し支払っていた前払金の方が、出来高よりも多い場合は、注文者は、破産財団に対し、その超過額について、施工業者に支払った代金が破産財団中に現存するときは、その返還を求めることができますし、現存しないときは、その価額について、財団債権として保護され(破産法54条2項)、破産債権よりも優先して弁済を受けることができます。
ただし、財団債権として保護されるのは、あくまで出来高よりも多く支払った前払金の超過額のみです。
破産管財人により、契約が解除された場合、例えば次のような、注文者が被った損害は、破産債権として権利行使することしかできません(同条1項)。
・建物や設備の劣化を防ぐため、注文者が支出した工事の保全費用
・他の施工業者に、残りの工事を引き継がせたことにより、総額の工事費用が増えた分
・工事が遅れたことによる損害破産債権の配当が受けられるかは、財団財産がどれだけ形成されるかによりますが、実際には、全く配当を受けられないか、配当を受けられても、破産管財人により認容された破産債権額の数パーセント程度のことがほとんどなので、あてにはせず、いくらかでも配当を受けられたら儲けもの程度に考えておいた方がよいでしょう。
■工事出来高の査定方法
工事の出来高は、工事代金の内訳明細書や、工程表、その他関係資料等を参考に、工事費目ごとの進捗率に応じて算定します。
破産管財人としては、破産会社の従業員などの協力を得て、工事の出来高の査定をしていくことになります。
これに対し、注文者からは、引継業者が見積もった残工事費用を、当初の工事代金から控除して、既施工部分の現在価値を出来高とすべきとする主張をすることもありますが、このような主張は、本来、破産債権となるにすぎない増加工事費用を相殺的処理により優先弁済受けるのと同様の処理になりますので、破産管財人により認められないでしょう。
■違約金の請求・相殺の可否
破産管財人により、破産法53条に基づき、請負契約が解除された場合、注文者は、破産管財人(破産財団)に対し、請負契約書の違約金条項に基づき、違約金を請求することができるでしょうか?
裁判実務では、違約金請求ができないとする裁判例が多く存在します(東京地裁平成27年6月12日判決、札幌高裁平成25年8月22日判決等)。
同条による解除権は、法によって破産管財人に与えられた特別の法定解除権であり、違約金条項の適用はないと考えられるからです。
また、仮に、違約金が発生する場合でも、その違約金は、破産手続開始決定後に発生した破産債権ですので(54条1項)、注文者が、これと請負代金支払債務などと相殺主張することはできない(67条1項)と考えられます。
■下請業者や設備業者が所有権を主張する場合
工材や設備を納品した下請業者や設備業者が、破産した施工業者から代金が支払われていないことから、これらの所有権を主張して張り紙をしたりする場合があります。
この点、いったん納品した以上、これらの所有権や占有は、施工業者に移転しており、下請業者らが、同意なく引き揚げてくることは自力救済行為として許されません。
もっとも、設備など動産の売主には、動産売買の先取特権が認められ(民法321条)、破産法上、別除権として保護され(破産法2条9号)、破産手続きによらずして、破産管財人の同意を得て、引き揚げることができますので(同法65条)、破産管財人と下請業者らとの話し合い次第となります。
ただし、下請業者らは、既に木材等が建物として組み上げられた場合、施工業者の注文者に対する請負代金債権について、原則として、物上代位権を行使することはできません。
例外的に、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分の請負代金債権に対して物上代位権を行使することができます(最高裁平成10年12月18日決定)。
また、下請業者らと、注文者はとの間には、直接の契約関係がなく、下請業者らは、注文者に対し、直接、下請代金を請求することはできません。
■残りの工事の進め方
破産管財人により請負契約が解除された場合、残りの工事を施工してもらえる業者を探し、改めて請負契約を締結することになります。
この場合、それまで工事を進めていた下請業者などが信頼できるところであれば、そこと直接契約を締結したり、破産した施工業者の社員(現場監督)と直接、工事監督ないしコンサルティング契約を締結したり、足場などのリース業者と直接リース契約を締結したりして、いったん中断した工事を継続する方が、関係者が事情を知っていて、時間もコストも節約することができる場合があります。
実際に、そのようにして、リカバリーされる方もいらっしゃいます。
-
2021.05.14
【不動産売買】中古住宅の雨漏り等による契約不適合責任

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
新築住宅で、雨漏りや漏水があれば、それは当然に瑕疵(契約に適合しない)であるといえ、契約不適合責任を追及することができます。
それでは、中古住宅の場合はどうでしょうか?
買主としては、買って1年もしないうちに、雨漏り等が生じた場合には、瑕疵があるんだから、売主に対し修繕や損害賠償請求することができると思うかもしれません。
しかし、必ずしもそうはなりませんので注意が必要です。なお、【損害賠償】契約不適合による損害賠償請求の要件については、こちら、
また、【不動産売買】契約不適合責任の免責条項とその有効性については、こちらを、それぞれご参照ください。
■雨漏りが契約書等で明示されている場合
中古住宅の売買において、雨漏りの事実や、瑕疵、劣化、損傷の程度が、売買契約書や重要事項説明書等で明示的に示されていて、買主がこれを容認して売買契約が締結された場合には、それらは契約の内容になっており、そもそも契約不適合には該当しません。
東京地裁平成25年9月26日判決も、売買契約において、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないこと、建物及びその設備は経年変化により老朽化・機能低下がみられ、これを原因として補修・修繕等が必要となり、その費用がかかる可能性があることが容認事項とされていたこと、不動産の引渡しは現況有姿のままされること、売主・買主間で雨漏りを修繕する旨の合意がないこと、買主は雨漏りの存在を事前に認識していたというべきであるから、その他、売主が雨漏りを修繕する義務を負うことを認めるに足りる根拠はないと判示して、買主側の請求を棄却しています。
■雨漏りが契約書等で明示されていない場合
旧民法下の瑕疵担保責任について、裁判例は、売買の目的物が通常保有すべきことを取引上一般に期待されている品質・性能を欠く場合,目的物に隠れた瑕疵があるとして、売主はその瑕疵について責任を負う。そして、中古住宅が売買契約の目的物である場合,売買契約当時,経年変化等により一定程度の損傷等が存在することは当然前提とされて値段が決められるのであるから,当該中古住宅として通常有すべき品質・性能を基準として,これを超える程度の損傷等がある場合にこれを「瑕疵」というべきであると判示しています(東京地裁平成17年9月28日判決)。
この考え方は、契約不適合責任においても、該当します。
したがって、中古住宅に雨漏り等が生じた場合に、それが契約不適合に当たるか否かは、次のようなメルクマールで判断されます。
・当該中古住宅に、同種・類似の建物と比べ、通常有すべき品質・性能を基準として,これを超える程度の損傷等があったか。
・売買契約前に、大規模なリノベーションがなされていたか否か。
・売買代金が、当該中古住宅の価格として相場か、それとも高額か。以下、損害賠償を否定した裁判例と、肯定した裁判例をいくつかご紹介させていただきます。
■損害賠償責任を否定した裁判例
(東京地裁令和元年10月17日判決)
ビルを購入したところ、地下受水槽から漏水が発生していることなどが判明したとして、瑕疵担保責任等に基づき、損害賠償した事案につき、当該ビルは、築22年を経た中古ビルであり、現状有姿のまま引き渡すことに当事者双方が合意しているから、当該ビルに経年劣化による様々な不具合が生じていることは、売買契約を締結する上で当然の前提として売買代金等の条件に織り込み済みであると考えられる。したがって、当該ビルに不具合があっても、それが建物の安全性等、建物自体の使用の可否に関わるような重大なものではなく、経年劣化により通常生じ得るようなものである場合には、当該不具合をもって、瑕疵に当たるということはできないというべきであるとして、地下駐車場ピット内に地下水が浸出し、結露が発生するなどしていることについて、ビル自体の使用の可否に関わる重要なものであるとも、経年劣化により通常生じ得る程度を超えるものとも認められないから、ビルの瑕疵に当たるということはできないと判示しています。
(東京地裁平成27年11月30日判決)
買主が中古アパートである建物及びその敷地を買い受けた際、売主らから、雨漏りや腐食は発見されていない旨の説明を受けたにもかかわらず、引渡し後に雨漏りや腐食が発見され、修理費用などの損害を被ったと主張して、売主らに対し、瑕疵担保責任又は説明義務違反に基づき損害賠償請求した事案につき、売買契約に際し、「現在まで雨漏りは発見していない」、腐食を「発見していない」と明記した本件物件状況等報告書を交付したとしてもこの記載は、売主の当該建物の状況に関する認識を示したものにすぎず、これをもって直ちに過去に雨漏りや腐食が生じた物件ではないことを、自己の法律上の責任として保証したとまでは認められない。そして、過去に雨漏りや腐食があったこと自体は、それによって売買契約当時の建物の利用に支障を生じさせるものではなく、売買契約当時、当該建物が23年以上経年していたことも考慮すれば、瑕疵ということはできない旨判示しています。
(東京地裁平成26年1月15日判決)
売主は、契約締結に際し、買主に対して物件状況等報告書を交付し、その中で、物件には経過年数に伴う変化や、通常使用による摩耗、損耗があることを告知している一方、建物躯体及び窓やドアのアルミサッシの品質性能について契約上特段の合意がされたとか、売主が特段の品質性能を保証した事実はないことによると、契約上、売主と買主との間で、売買目的物である当該建物について合意された品質と性能は、築38年の分譲マンションが通常有する程度のものであったということができ、「瑕疵」の該当性も、そのような品質性能を欠いているか否かという観点から判断すべきである。当該建物で壁紙に雨水が浸透する不具合は、建物躯体のひび割れが原因であるとは認められるものの、大規模修繕が行われていない限り、経年により建物躯体に雨漏りを生じるようなひび割れが生じることは一般にあり得ることと認められるなどと判示して、損害賠償請求を棄却しています。
■損害賠償請求を認めた裁判例
(東京地裁平成30年7月20日判決)
売買契約の目的物である建物は、昭和35年新築の中古物件ではあるものの、売買契約が締結される直前に、設備、水回り、電気、内装、外装その他について大規模なリノベーション工事が行われていること、売買代金が築50年以上の建物としては高額であること、売主は、前所有者から、瑕疵担保責任を負担しないという条件で建物を取得している一方で、買主に対し、瑕疵担保責任を負担していることが認められ、そうすると、当該建物は、現状有姿で売買されたのではなく、社会通念に照らし、少なくとも住宅としての最低限の基準を満たす品質・性能を有するものとして売買された、すなわち、雨漏りのしない建物として売買されたとみるのが相当であるとして、洗面室の周囲の雨漏りについては、瑕疵にあたると判示しています。
(東京地裁平成25年3月18日判決)
降雨があった場合に、本件建物部分のうち書斎及び居間にルーフバルコニー側から浸水する状態にあったところ、当該サッシからの浸水が室内の絨毯や畳の交換を要する程度に及んでいることに照らせば、当該サッシの老朽化の程度は、築後30年の経年劣化を考慮しても、通常有する品質性能を欠くものであり、当該建物部分の瑕疵であるというべきである(なお、当該サッシがマンションの共用部分に属するが、当該サッシの瑕疵が当該建物部分の使用収益に直接影響を与えるものである以上は、売買における目的物の瑕疵として売主が瑕疵担保責任を負うべきものと解される)と判示しています。
(東京地裁平成20年6月4日判決)
買主らが、建物の柱等に雨漏りによる腐食とシロアリによる侵食があったところ、売主らが腐食及び侵食を知りつつこれを秘し、腐食及び侵食を容易に知ることができたのに十分な調査をしないで、当該建物を売却したと主張して、売主らに対し、瑕疵担保責任、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償請求した事案につき、ある程度の年数を経た木造建物に雨漏りによる腐食の跡やシロアリによる侵食の跡があったとしても、それが当該建物の土台、柱等の躯体部分にあるのではなく、又は、その程度が軽微なものにとどまるときは、必ずしもこれをもって当該建物の瑕疵ということができない場合があることは否定できないが、当該建物のうち、とりわけサンルームの部分については、土台や柱といった躯体部分に雨漏りによる腐食とシロアリによる侵食があり、その範囲が柱の上部にまで及び、その程度も木材の内部が空洞化するまでに至っており、現に雨漏りがする状態であるというのであるから、当該建物が売買契約締結時において築後12年が経過した木造建物であることを考慮しても、同部分に建物としての瑕疵があることは明らかというべきであるとして、損害賠償請求を認めています。
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2022年 (3)
-
2021年 (11)
-
2016年 (1)
-
2015年 (9)
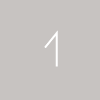
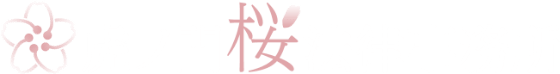
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)