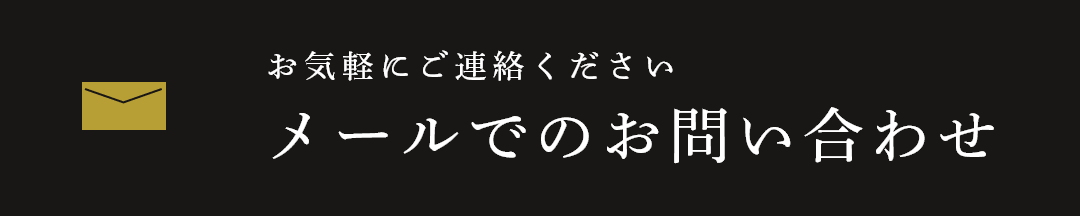-
2021.01.27
【借地非訟】建物の朽廃とは?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
借地権譲渡許可の申し立てをすると、地主側から、借地上の建物は朽廃(きゅうはい)しており、借地権は消滅しているから、申立は棄却されるべきである旨の主張がなされることがあります。これは、借地法第2条1項但書(第5条1項後段で準用)に基づく主張です。
●建物の朽廃とは
朽廃とは、時の経過によって自然に建物の効用が失われた場合をいいます。
法律上、朽廃と滅失とは異なる概念であり、滅失は、建物が物理的に消滅する場合であり、借地法上、朽廃の場合には借地権は消滅しますが、それ以外の理由により建物が滅失した場合には借地権は消滅しません(再築可能)。
●朽廃の判断基準
建物が朽廃したと言えるためには、「自然的に達したことが必要であって、火災、風水害や地震により一挙に建物としての効用を失うに至ったり、取壊しのように人為的に建物の効用を失われた場合は『朽廃』には当たらない」と判示されています(東京地裁平成24年11月28日)。
また、朽廃に至ったかどうかは、「建物を全体的に観察し、特に柱、梁、桁、基礎、土台等の構造部分に腐朽損傷があるかどうか等を中心に、建物保全のための通常の修繕によっては存続が不可能になっていないかどうかを検討して判断」します(東京地裁平成14年8月29日判決)。
●朽廃が認められる事例
建物が使用できる状態であれば、朽廃には至らないとされ、朽廃が認められるケースは多くありません。
裁判例上、朽廃が認められる場合は、次のような場合です。
・かろうじて倒壊を免れている状況で、いつ倒壊するかわからない危険な状態となっている。
・基礎等建物の構造部分にほぼ全面的な補修をしなければならず、新築同様の費用が必要となる状態である。
・建築後60年が経過し、10年間雨漏りが放置され主要構造部分に相当程度の腐食が認められる居住できるような状態ではない。
●朽廃を否定した判例
これに対し、最高裁昭和42年7月18日判決は、築26年経過した建物について、「部分的にみるときは、その骨格部分ともいうべき土台、柱脚部及び外廻り壁下地板、屋根裏下地板等に相当甚しい損耗があり、また、屋根瓦にも同程度の損耗があり、内部造作材も老化しているが、同時に、また一個の構成物である建物全体としてみるときは、自力によって屋根を支え独立して地上に存在し、その内部への人の出入りに危険を感ぜしめることはなく、局部的応急修理の上維持保全の処置を講じるならば建物としての耐久力は安定且つ平衡性を維持し場合によっては増大される状態にあつて、いまだ建物としての社会的経済的効用を失う程度に至つていない、というのであるから、本件建物は借地法にいう朽廃の程度には達していないものと解すべき」と判示しています。
-
2021.01.22
【損害賠償】民法改正による法定利率変更の影響
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
令和2年4月1日に施行された改正民法により、法定利率について、それまで年5%で固定されていたものが、変動性に改正されましたが、これにより損害賠償実務にも大きな影響があります。そこで、今回は、その影響について解説させていただきます。

●法定利率変更のポイント
今回の民法改正による法定利率の変更点は次の通りです。
・当初の法定利率は3%とする(改正民法第404条2項)。
・法定利率は、その後3年ごとに見直す(同3項)。
・各期の法定利率は、過去5年の毎月の短期貸付平均利率の平均として法務大臣が公示した割合を「基準割合」とし、直近変動期の基準割合との差が1%を超えたときに、その差の1%未満を切り捨てて、整数の単位で法定利率に反映する(同4、5項)。すなわち、4%とか、2%という利率になり、4.5%とか、2.35%といった利率にはなりません。
なお、年6%とされていた商事法定利率(商法514条)は、今回の改正により削除され、商行為にも、民法の法定利率が適用されるようになりました。
●いつの時点の法定利率が適用されるか?
法定利率は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって、定められます(同第419条本文)。
不法行為に基づく損害賠償は、不法行為時から、遅滞の責を負いますので、その時点の法定利率が適用されることになります。
いったん法定利率が決まれば、その後、法定利率が変更されても、影響を受けることはありません。例えば、不法行為時の法定利率が3%であった場合、その後、1%に変更されていたとしても、請求できる遅延損害金は年3%のままです。
●経過措置
改正民法による法定利率は、令和2年4月1日以降に生じた損害賠償請求権に適用されます。
これに対し、令和2年3月31日以前に生じた損害賠償請求権の遅延損害金は年5%のままとなります。
そのため、訴状記載のよって書きの記載は次の通りとなります。
(令和2年4月1日以降に生じた損害賠償請求の場合、当面の間)
「金○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済まで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。」
(令和2年3月31日以前に生じた損害賠償請求の場合)
「金○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済まで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。」
●中間利息控除
損害賠償実務上、後遺症に基づく逸失利益の請求については、本来であれば将来得られるはずの収入を一時金で先に支払う場合に、中間利息控除が行われています。
従前(令和2年3月31日以前に)生じた損害賠償請求において、後遺障害逸失利益を算定する場合、労働能力喪失期間に対応する年5%の利率によるライプニッツ係数を乗ずる方法によって算定されていました。
これに対し、令和2年4月1日以降に生じた損害賠償の場合、その請求権が生じた時点における法定利率によって中間利息が控除されることになりました(同第417条の2第1項)。
すなわち、不法行為時(事件・事故時)の法定利率が3%であった場合には、その後、後遺障害の症状固定時の法定利率が2%になっていたとしても、不法行為時の法定利率である年3%で中間利息が控除されることになります。
但し、中間利息控除の計算期間(労働能力喪失期間)の始期については、従前の運用通り、症状固定時となります。
-
2021.01.08
周辺住民らによる開発工事の差止請求を棄却した事例
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、周辺住民らによる、開発工事の差止請求等を棄却した裁判例(神戸地裁尼崎支部令和元年12月17日判決)をご紹介させていただきます。

●事案の概要
本件は、兵庫県西宮市内にある高塚山と呼ばれる小高い丘にある土地の所有者が事業主、建設会社が工事施行者となって、宅地分譲のための開発を行っていることについて、周辺住民らが、人格権から導かれる「まちづくり権」などを侵害されたと主張して、開発工事の差止や、損害賠償を請求した事案です。
●「まちづくり権」
周辺住民(原告)らは、「まちづくり権」について、「より暮らしやすい、自らの幸福を追求しうる生活環境を自ら決定する権利、自らの住む地域のあり方を自らが決定する権利」であると定義した上で、これは人格権が具体化したものであり、法的権利として認められるなどと主張しました。
この点について、本判決は、「まちづくり権」について、法的権利性を有し、工事差止等が認められるためには、
①権利として客観的に認知されていること、
②その内容や効力が及ぶ範囲、発生の根拠、権利主体などについて、一義的な判断を下すことができる程度の明確な実態をすること
が必要であるとした上で、原告らが主張する「まちづくり権」は、
①土地所有権等を制約するものとして客観的に認知されているということはできないし、
②どの範囲の住民が、どのような相手方に対して、差止等の権利行使を行うことができるのかといった具体的内容も全く不明である
などと判示して、その法的権利性を否定しました。
●都市計画法や条例違反の主張
また、原告らは、当該開発許可手続において、原告ら住民に対する十分な住民参加手続が履践されなかった結果、当該開発工事は、都市計画法や条例に違反するものになったと主張しました。
この点について、本判決は、都市計画法や条例によるまちづくりに対する住民関与の手続きは、主として市等の地方公共団体の責務とされているものであって、
都市計画法上の開発許可を受けた者は、当該開発許可に重大かつ明白な違法が存し、無効であるような場合の他は、取消訴訟によって取り消されない限り、開発工事を実施することは行政法上適法であることからしても、
事業主ないし施工業者との関係で、住民らがまちづくりに自らが参加し、自らの住む地域のあり方を自らが決定する利益が、法的利益として認められるとまでいうことはできないと判示しました。
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (3)
-
2022年 (6)
-
2021年 (26)
-
2016年 (2)
-
2015年 (28)
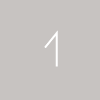
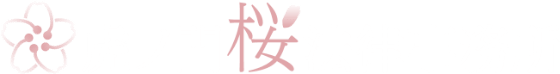
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)