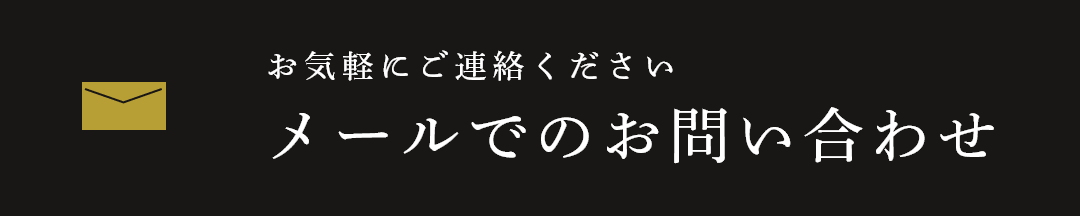-
2024.03.27
フランチャイズ契約における違約金の妥当額
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
フランチャイズ・システムの構築を進めている顧問先から、加盟店がフランチャイズ契約を中途解約した場合などに備え、違約金の定めを設ける予定であるが、法的に問題はないか、いくらくらいが妥当か相談を受けましたので、文献や裁判例をリサーチした結果を踏まえ、ご説明させていただきます。
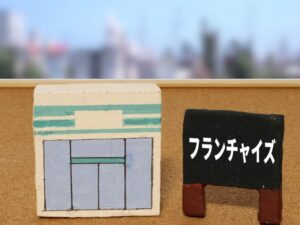
■問題の所在
本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して、違約金を課すこと自体は、直ちに、独占禁止法上問題にはなりませんし、違法とも言えません。
ただし、違約金が著しく高額で、これにより事実上、加盟店側からの中途解約が制限されるような場合には、優越的地位の濫用に該当し、独禁法上、問題となり、公序良俗に反し、無効となるおそれがあります。
■違約金規定を有効と判示した裁判例
【東京地裁令和2年2月27日判決】
歯のホワイトニング、口内のアロママッサージ等のデンタルエステサービスを提供するフランチャイズ・チェーンを運営している本部が、フランチャイズ契約を締結した歯科医師(加盟店)に対し、フランチャイジーによる中途解約を理由とする違約金を請求した事案
当該フランチャイズ契約において、契約期間は店舗の開店から10年間とされ、解約日から起算して3箇月以上かつ6箇月未満前の文書による予告に基づく中途解約の場合には、固定ロイヤリティ(月額20万円)の2年分の約定解約金の支払が必要と定められていました。
加盟店が、当該違約金規定は、公序良俗に違反し、無効であると主張したのに対し、
判決は、
・加盟店は、独立した事業者として、自己の判断と責任においてフランチャイズシステムに加入し、本部との関係を継続しながら利潤を追求しようとするものであるところ、加盟店としても、加盟店の地位を取得することによって、自己の経済的利益を確保、増大させるとの利害得失を考慮して、解約金の定めに関する約定の存在も承知した上で、フランチャイズ契約を締結したと考えられること、
・違約金条項は、本部からフランチャイズ契約を中途解約する場合の解約金の金額も同額とされており、解約金の金額において、フランチャイザーとフランチャイジーとの間で条件の違いはないこと、
・フランチャイズの契約が終了したとされた日から本来の契約期間の満了まで4年程度残存していたこと、
・加盟店は、本部から受領した収支計算方法について説明した資料に依拠して、契約期間中、赤字であった旨主張するが、そもそも、契約書では、本部が加盟店の売上や利益を予測しないことが明記され、実際に、フランチャイズ契約の締結に当たって、本部は、加盟店に対して、売上予測等を示していない以上、本部の誤った情報提供により加盟店が損害を被ったとはいえないこと
などといった事情に鑑みると、解約金が社会的に相当と認められる範囲を超えて著しく高額なものであるとか、一方的にフランチャイジーたる加盟店の利益を害するものとまでいうことはできず、
違約金規定が公序良俗に反して無効であるということはできない旨判示しています。【東京地裁平成28年2月23日判決】
宅配弁当事業のフランチャイズ契約を締結していたところ、加盟店が食材売掛金の未払を起こし、かつ、突然店舗経営を放棄したことを理由に本部が契約を解除した事案。
フランチャイズ契約には、契約書所定の解除事由により、本部から、契約が解除されたときは、加盟店は損害賠償(残存期間についての逸失利益を含む)として、解除日直近の12ヶ月間(12ヶ月未満のときは経過月)の店舗経営の実績に基づく平均月間営業総売上(1ヶ月未満のときは本部の示す初年度の予想平均月間営業総売上)に基づき算出した本部ロイヤリティー相当額の48ヶ月分を本部に支払うものとする旨の違約金条項が定められていました。
判決は、加盟店には契約上の解除事由が存在し、本部の解除請求は認められるとし、上記違約金条項に基づき、ロイヤリティーの平均額48ヶ月分の損害賠償請求を認めました。
■違約金規定を一部制限した裁判例
【東京地裁平成30年6月19日判決】
エステ事業のフランチャイズ契約において、加盟店が、当該フランチャイズ契約に違反した場合は、本部に対し、違約金として500万円を支払う旨の違約金条項が定められていたところ、本部が、これはフランチャイズ契約に違反する行為ごとに違約金支払義務が発生する旨を定めたものであり、加盟店は、2回に渡り、競業避止義務違反行為をしたから、違約金として1000万円の支払義務を負うと主張したのに対し、
判決は、次のとおり判示しています。
・違約金条項には、違反行為ごとに違約金支払義務が発生するとは明記されていないこと。
・フランチャイズ契約書は、その体裁から本部が条項の原案を作成したことが明らかであるところ、違約金の定めは、フランチャイジーである加盟店のみが負担することとされ、フランチャイザーである本部については同様の定めは規定されていないこと。
・以上の諸事情によれば、違約金条項を加盟店に不利益に緩やかに解釈することは相当ではなく、違反行為ごとに違約金支払義務が発生するとは明記されておらず、しかも、別に損害賠償請求の余地を残すものである以上、本件違約金条項に基づき、加盟店が違約金の支払義務を負うのは、その文言どおり500万円にとどまると解するのが相当である。【東京高裁平成8年3月28日判決】
同判決は、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約につき、違約金(損害賠償の予定額)を定めておくことには合理的な理由があることを認めつつ、
違約金の約定を一律に適用すると、事案の具体的事情に照らし、その損害賠償の予定額が社会的に相当と認められる額を超えて著しく高額となって、損害賠償額の予定の趣旨を逸脱し、著しく不公正であるような場合には、社会的に相当と認められる額を超える部分は公序良俗に反するものとして無効というべきであるとし、
違約金がロイヤリティの120ヶ月分(契約期間の10年分)と定めれれていることにつき、解除後の契約期間がどの程度残存しているか、本部側において契約期間の残存期間中、フランチャイザーとしての義務を履行し得る状況にあるかということにかかわりなく、常に全契約期間中のロイヤリティに相当する損害賠償を請求し得るということは社会的に相当とはいえないと判示しています。
この事案の第一審判決(東京地裁平成6年1月12日判決)は、解除原因の内容及び態様、フランチャイザーの被った実損の額、その他の具体的事情に関係なく、違約金に関する約定を一律に適用することは著しく不公正であって、当該事案における適正な賠償予定額は、各店舗毎に30か月分のロイヤリティ相当額をもって相当とし、その余の部分は無効であると解するのが相当であると判示しましたが、控訴審もこれを維持しました。
■違約金規定を無効と判示した裁判例
【東京高裁平成7年2月27日判決】
クリーニング店のフランチャイズ契約において、解約に際し加盟店から本部側に500万円の解約一時金を支払わなければならないとの約定について、
・加盟店がグループ組織加盟に際し本部と契約した当時は、加盟店は自由になんらの負担なく契約関係を終了することができたこと、
・違約金条項を含む会員契約書の作成に当たり、本部から各条項についての説明がなかったこと、
・契約当時、加盟店はグループ組織の一員として営業すべく多額の投資を行ったばかりで、契約を拒むことは事実上困難であったこと、
・解約一時金の金額が下限のみ500万円と定められ、上限の定めがないこともあって、加盟店からの期間満了による契約関係の終了を著しく困難なものとし、会員契約の継続を相当程度強制する結果となること
・従前解約一時金は特段の事情がない限り免除されるのが例であったのに、本部に対しては会員契約上その他の業務に関係した非違とは直接関係のない理由で免除しないこととされたことが明らかであること
から、加盟店に500万円の解約一時金の支払を強制することは、著しく正義に反し、公序良俗に違反し、無効である旨判示しています。■まとめ
以上の裁判例から、次のようなことが言えます。
・フランチャイズ契約が中途解約された場合、(平均ないし固定)ロイヤリティの2〜4年分の違約金の定めは有効と解される可能性が高い。
・他方、フランチャイズ契約の残期間がどのくらい残っているかに関係なく、ロイヤリティの120ヶ月(10年分)の違約金の定めは無効となる可能性が高い。
・解約一時金の下限額のみが定められ、上限の定めがない場合には、定めがあいまいで無効と解される可能性がある。
・違約金条項に明記されていなければ、違反行為が複数回あったとしても、違約金を複数回分請求できるわけではない。
・違約金の規定が、本部(フランチャイジー)及び加盟店(フランチャイザー)双方に公平・平等に適用される場合には、有効と解される要素となる。
■募集時の情報提供にも注意
本部が、加盟店を募集するに当たり、フランチャイズ契約を中途解約する場合には実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行わないと、ぎまん的顧客誘引の顧客に誤認させること」(一般指定8項)に該当するおそれがありますので、注意が必要です。
上記の「誤認させること」には、顧客にとってメリットと誤認される事項を積極的に情報提供する行為のみならず、顧客にとってデメリットとなる事項をあえて顧客に情報提供しないという不作為も含まれうるからです。
-
2024.03.13
退職後の競業行為に関する損害賠償の可否
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
顧問先等から、役員や従業員による退職後の競業行為や、従業員や顧客の引き抜き行為に関する相談を受けることが、そこそこあります。
この点、退職後の競業行為等を禁止する合意書や誓約書、就業規則が存在する場合には、その内容や有効性を判断することになります。
退職後の従業員に競業避止義務を負わせることは、その者の職業選択の自由を制約することになりますので、公序良俗に反し無効となる場合もありますが、今回はどのような場合に合意が有効で、どのような場合に無効になるかという問題には立ち入りません。
今回は、このような退職後の競業避止義務等に関する合意がない場合において、判例や裁判例を概観し、どのような行為が違法とされ、損害賠償請求できるかについて説明させていただきます。

■不法行為等の成立を認めた裁判例
【東京地裁昭和51年12月22日判決】
会社の取締役らが在職中から新会社の設立を企図し、突然にしかもいつせいに退職して退職した会社と営業の一部競合する新会社を設立し、従来からの会社の得意先に対し、同社と同一もしくは類似した商品の販売を開始した事案について、次のように判断しています。
被告らが原告会社と競合する被告会社を設立することは自由であると言っても、その設立については原告会社に必要以上の損害を与えないように、退職の時期を考えるとか、相当期間をおいてその旨を予告するとか、さらには被告会社で取扱う製品の選定やその販売先などにつき十分配慮するなどのことが当然に要請されるのであってて、いたずらに自らの利益のみを求めて他を顧みないという態度は許されない。しかるに前記認定事実からすれば、被告らは原告会社在職中から被告会社の設立を企図し、突然にしかも一斉に同社を退職して同社と営業の一部競合する被告会社を設立し、従来からの原告会社の得意先に対し、同社と同一若しくは類似した商品の販売を開始したというのであるから、同人らのかかる行為は先に述べたことからして著しく信義を欠くものと言わざるを得ず、もはや自由競争として許される範囲を逸脱した違法なものと言わざるを得ない。
【東京地裁平成5年1月28日判決】(チェスコム秘書センター事件)
原則的には、営業の自由の観点からしても労働(雇傭)契約終了後はこれらの義務を負担するものではないというべきではあるが、すくなくとも、労働契約継続中に獲得した取引の相手方に関する知識を利用して、使用者が取引継続中のものに働きかけをして競業を行うことは許されないものと解するのが相当であり、そのような働きかけをした場合には、労働契約上の債務不履行となるものとみるべきである。
【横浜地裁平成20年3月27日判決】(ことぶき事件)
美容室の総店長として勤務していた者が、退職時に無断で顧客カードを持ち出し、他店で勤務する際に利用していたという事案について、次のように判断しています。
顧客カードの管理状況について見ると、リプル店において、顧客カードは、リプル店の顧客が自由にこれを見ることができるような状態に置かれてはいなかったものの、単に輸ゴムで束ねられ、カウンターの下の三段ボックスや顧客の荷物置場に保管されていたにすぎず、これに秘密とする旨の格別の表記等もされず、被告が顧客カードを持ち出した当時、これが施錠できる場所に保管されていたわけではなく、また、パソコンに入力されていた顧客情報についても、パスワードの設定がされておらず、従業員が自由に顧客情報にアクセスすることができる状態に置かれていたものと認められるのである。そうすると、顧客カードは、秘密に管理され、情報の漏洩防止のための客観的な管理下に置かれていたとは認め難いから、顧客カードにつき、上記の秘密管理性を認めることはできない。
顧客カードは「営業秘密」に当たらないから、被告が顧客カードを持ち出した行為を不正競争防止法2条1項4号の「不正競争」と認めることはできないが、その有用性及び非公知性は肯認されるのであって、たとえ従業員であってもこれを原告の承諾なく持ち出して、リプル店の営業活動以外の目的で使用するのは、不法行為に当たるというべきである。
■不法行為等の成立を否定した裁判例
【最高裁平成22年3月25日判決】
工作機械部品等製造会社を競業避止義務特約の定めなく退職した従業員が、別会社を事業主体として同種の事業を営み、退職した会社の取引先から継続的に仕事を受注した行為につき、退職のあいさつの際などに取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のことはしているものの、取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて、退職した会社の営業秘密に係る情報を用いたり、信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったものではなく、また、退職直後に会社の営業が弱体化した状況を利用したともいい難い等の諸事情を総合し、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものとはいえず、不法行為に当たらないとされた事例。
【東京地裁平成20年11月7日判決】(スタートレーディング事件)
従業員は退職後に使用者に対して競業避止義務を負うものではなく、自由競争を逸脱するような方法で使用者の顧客を奪取したような場合に例外的に不法行為が成立する余地があるにすぎない。
被告Bは、原告の顧客に対し、退職の挨拶をする際に新たに会社を始めることを告げたところ、求められるままに価格表等を提示してこれによって取引が開始されたことが認められる。そうすると、被告Bは、原告における営業担当者であったことを活用して顧客を獲得したという面があることは否定できない。ただ、その際、原告よりも極端に取引条件を有利にしたとか、原告との取引を止めるよう執拗に勧めたとか、原告について何か虚偽の事実を告げたとか等の事情は認められない。また、これら顧客としても、長年取引のあった原告との取引を中止し、新たな業者と取引を開始することは相応の危険を伴うことであり、顧客が取引に応じたということは、顧客自身の選択でもある。そのように考えると、被告Bないし被告会社の行なった取引が自由競争を逸脱した取引であるとは認められない。
【東京地裁平成20年7月24日判決】
被告は、原告を退職後、新会社の設立準備中に、偶々、Gからプロジェクトのコンペに参加するよう打診を受け、被告が原告の従業員として稼働していた際に知り得た業務上又は技術上の秘密等を利用することなく、退職後に自ら行った現地調査や周辺環境の調査等を元に、それまで培った知識・経験等を生かして企画書を作成・提出し、顧客のコンペにおいて最も高い評価を得たがために、受注に至ったのであって、これを自由競争の範囲を逸脱した違法なものということはできない。
【大阪地裁平成12年9月22日判決】
すでに被告会社を退職していた被告石井が,被告会社と競合する新規事業を計画し,その遂行に必要な従業員を確保し契約園を募るなどした結果,被告会社の従業員の一部がこれに応じて被告会社を退職し,被告会社が受託していた幼稚園の一部が被告会社との契約を解消したとしても,そのような被告石井の競業行為やこれに呼応した従業員の行為が当然に被告会社に対する背任行為等として不法行為となるものではない。
■まとめ
以上から、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で、元雇用者の顧客を奪取したとみられる場合には、元従業員の行為が違法と判断され、損害賠償を受ける可能性があります。
それでは、具体的にどのような場合に、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱する」と評価されるおそれがあるかといいますと、次のような行為が挙げられます。
・退職した会社の営業秘密に係る情報を用いて営業活動を行う。
・退職した会社について虚偽の事実を告げたり、その信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行う。
・退職直後に退職した会社の営業が弱体化した状況を利用して営業活動を行う。
・顧客に対し、退職した会社よりも極端に取引条件を有利にする。
・顧客に対し、退職した会社との取引を止めるよう執拗に勧める。
他方、次のような行為については、自由競争の範囲内と解されます。
・退職のあいさつの際などに取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のこと
・取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用する程度
・退職後に、それまで培った知識・経験等を生かして企画書を作成・提出し、顧客のコンペにおいて評価を得て、受注に至った場合
-
2022.01.28
【企業法務】人材紹介において内定を取消した場合の紹介手数料請求を認めた事例

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所には、顧問先の1つに人材紹介会社もありますが、人材紹介契約に関し、参考となる裁判例(東京地裁令和2年11月6日判決)がありましたので、ご紹介させていただきます。
■事案の概要
人材派遣等を業とする原告が、病院等を経営する被告に対し、求職者Aを紹介しましたが、被告がAの採用内定後に内定を取り消したことから、この内定取消しは被告の都合によるものと主張して、かかる場合でも紹介手数料を支払うべきことを定めた人材紹介取引契約の条項に基づき、紹介手数料や遅延損害金の支払を求めた事案です。
■争点
人材紹介契約(本件契約2条6項)には、被告は、内定通知を行いAがこれを受諾した後、「被告の都合」により内定を取り消した場合でも、原告に手数料を支払うものとする旨の条項が定められていたことから、内定取消が「被告の都合」に該当するか否かが争われました。
この点、判決は、「本件契約3条1項が、専ら入職者の責めに帰すべき事由により退職した場合に限り返金を認めているところ、解雇により退職した場合には、法令に則った正当な解雇の場合に限っていることを踏まえると、客観的に合理的で社会通念上も相当なものとして是認することができない内定取消しについては、本件契約2条6項にいう被告の都合による内定取消しに当たるものとして、紹介手数料の支払を免れないものと解するのが相当である。」と判示しました。
要は、
客観的に合理的で社会通念上も相当なものとして是認できる内定取消の場合には、人材紹介料を払わなくても良いが、
客観的に合理的で社会通念上も相当なものとして是認できない内定取消の場合には、人材紹介料を支払わなければならない
と判示したのです。
■被告の主張
上記争点について、被告は、次のように主張しました。
被告が求めていた人材は、健診センターのチーフマネージャーであり、極めて重要な職位であるところ、Aは、履歴書返送時の送り状において、被告の名称も間違えていた。
また、履歴書及び職務経歴書を確認してみたところ、現在の勤務先について齟齬、矛盾のある記載を見つけた。このように、Aが被告に提出した履歴書や職務経歴書には、本人しか確認しえない学歴、職歴について誤謬、虚偽、矛盾した標記が何か所にもわたって存在しており、一般常識人として求められる真面目さ、正確さの欠落した注意力散漫かつずさんな性格のみならず、論理的思考力の弱さ、思考回路の混乱の疑いが、内定予定後に一挙に露顕した。これを受けて、被告は、Aは、健診センターのチーフマネージャーとしての適格性を欠くと判断し、採用を見送ったものである。
よって、内定を取り消したのは、専らAの過誤、過失に起因するものであって、被告の都合によって内定を取り消した場合に当たらない。
■裁判所の判断
この被告の主張について、裁判所は次のように判断し、人材紹介料や遅延損害金の支払いを命じました。
確かに、履歴書と職歴経歴書には、誤記や、齟齬・矛盾のある記載が認められる。しかしながら、年齢の記載、職歴欄と自己PR欄の齟齬は、Aが以前に使用した履歴書や職歴経歴書を上書きせずに使いまわしたことから生ずる誤記と推認でき、経歴を詐称しようとするなどの悪質な意図に出たものとは認められない。その他の誤記についても、注意力がやや欠落している点は否めないものの、単純な誤りであって、虚偽の経歴を意図的に記載したとまでは認めるに足りない。また、履歴書返送時の送り状の誤記についても、漢字の変換ミスにとどまるものである。
そして、被告は、面接時には、すでに、履歴書と職務経歴書のうち、入学・卒業の各年度と年齢の記載に誤りがあることに気づいており、それ以外の誤記も、通常の注意をもって読めば、内定決定前に気づくことが十分可能であったといえる。
そうすると、被告がAの採用内定を取り消した事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であったとはいえず、解約権留保の趣旨、目的に照らしてみたときに、被告の内定取消しが、客観的に合理的で社会通念上も相当なものとまではいえない。
-
2022.01.12
【企業法務】代表取締役を解職された場合、損害賠償請求できるか?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
取締役などの役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。理由のいかんを問いません。
ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができる旨が会社法に定められています(同条2項)。
詳しくは、【取締役の解任】職務不適任を理由とする「正当な理由」の該当性をご参照ください。
■問題点
それでは、取締役会において、代表取締役を解職された場合、任期の間、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額について、損害賠償請求できるのでしょうか?
最近、このようなご相談を受けましたので、調べてみましたが、この点について解説をしている文献はあまり多くはなく、裁判例を1つ見つけました。
法律上の根拠としては、会社と代表取締役とは委任の関係にあるところ(会社法330条)、民法651条2項は、委任においては、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない旨定めていることから、代表取締役の解職決議に民法651条の適用があり、同条2項に基づき損害賠償請求できるかが問題となります。
■富山地裁高岡支部平成31年4月17日判決
当該判決は、次のように判示して、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額に関する損害賠償請求を否定しています。
代表取締役の解職の手続に、委任解除の規定である民法651条が適用されるかは一つの問題ではあるが、仮にその適用があるとしても、同条2項における「相手方に不利な時期」とは、委任に係る事務処理自体との関連において不利な時期をいうものと解され、また、同項にいう損害とは、解除の時期の不当なことによる損害をいうものと解される。
そして、報酬を支払う旨の約定のある有償の委任契約においては、解除により将来の報酬債権が生じないことは当然であって、委任は各当事者がいつでも解除することができるものである以上、受任者が将来得べかりし報酬は、当然には解除の時期の不当なことによる損害として上記損害に含まれるものではないというべきである。
なお、当該訴訟において、原告は、代表取締役はその役職に伴う重責を背負いながら、他方で、いつ、いかなる理由であろうと解職され、報酬請求権を失うというのでは、代表取締役は極めて不安定な立場に置かれ、不当である旨主張していますが、この点について、当該判決は、次のように判示しています。
明文上、代表取締役の報酬を保護する規定はないうえ、代表取締役が代表の地位を退き、これに伴う報酬の減額があったとしても、取締役としての地位を失うものではなく、これに対応する報酬請求権は得られるのであるから、著しく酷というものではなく、それが不当であるということはできない。
■会社法339条2項の類推適用
もっとも、代表取締役を解職された場合にも、取締役が解任された場合の会社法339条2項の類推適用がされるか否かについては争いがあり、これを肯定し、正当な理由なく解職された代表取締役は会社に対し、損害賠償請求できるとする見解も存在します。
-
2021.07.02
【労務管理】人事評価の違法性を否定した裁判例

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、従業員に対する査定制度の結果に基づいて賞与・給与の額が決定されていた場合に、その査定制度やそれに基づく人事評価についての違法性を否定した裁判例(横浜地裁令和2年3月24日判決)をご紹介させていただきます。
なお、当該裁判例では、個人面談における、上司による従業員に対する退職勧奨の違法性がメインで争われており、慰謝料として20万円が認容されています。
■査定制度に関する原告の主張
被告である会社には、グローバル・パフォーマンス・マネージメント(GPM)と呼ばれる評価制度が導入されていましたが、これについて、原告である従業員は、
・GPM評価制度が相対評価であること
・評価自体が上長の「期待」という主観的要素を基準としていること
・評価者が上長1名のみであり複数の評価者による客観的評価が担保されていないことなどから、GPM評価制度が不公正な制度であり、制度自体が違法なものであると主張しました。
■査定制度に関する裁判所の判示
これに対し、裁判所は、
・人事評価において、相対評価を採用することが、およそ直ちに違法となるか自体疑問がある
・その点を措くとしても、GPM制度が相対評価であると認めるに足りる的確な証拠はない
・少なくとも、原告に対する評価は他の従業員と比較してされているわけではないから、原告に対する人事評価が相対評価であるから違法であるとの原告の主張は、その前提を誤るものであって採用できない。・従業員が従事する業務の内容及び性質によっては、客観的に算出することができる数値等のみによってその業務の正当な評価を行うことができない場合があることは明らかであり、評価基準に主観的な要素が含まれているからといって、直ちにこれを不公正で違法なものということはできない。
・そもそも被告のGMP評価における「期待」というのは、上長の純粋に個人的・主観的な期待を意味するものではなく、その役職に対して一般的・客観的に期待されるレベルを意味するものと解するのが相当である。
・被告のGPM制度においては、まずは直属の上長が評価を行い、その後、上位上長及び人事部門を入れた処遇会議において、上長が評価の理由について説明し、上位上長及び人事部門が承認をすることにより、最終的な評価が決定されるのであるから、上長1名のみによる恣意的な評価を許容するものであるとも認められない。
したがって、GPM評価制度そのものを不公正かつ違法な制度であるということはできないと判示しました。
■各年度の人事評価について
また、会社による最終考課は、原告が
・会議に出席した際に意見を述べなかったこと、
・業績検討会議における報告内容が検証不足であったこと、
・作業の引継ぎが不十分であったこと、
・マニュアル連携業務の実質的な取りまとめ作業を部長報告も含めて関連子会社に任せたこと、
・社内サイトにおける活動を実施するための仕組みを運用に乗せることができなかったことなどをその理由とするものであり、原告が外されたと主張する業務を行わなかったことや、原告の担当した業務量が少なかったことを理由とするものとは認められないから、成果を上げる前提を欠いていたのに低い評価をされたという原告の主張は当たらないとして、
各年度のGPM評価は、人事評価に関する使用者の裁量を逸脱濫用したものとは認められないと判示しています。■人事評価の裁量権
賃金の決定、計算方法等は、就業規則の絶対的必要的記載事項であり(労働基準法89条2号)、就業規則(給与規定)中に、査定を行って賃金や賞与の額を決定する旨の査定条項が置かれている場合があります。
人事評価は、使用者の裁量的判断に委ねられており、その裁量権を逸脱・濫用した場合でなければ、違法とはなりません。
当該裁判例は、人事評価について、使用者の裁量権の逸脱・濫用はないと判断した一事例です。
-
2021.06.22
【企業法務】取締役の法令違反と任務懈怠責任

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
取締役などの役員等は、その任務を怠ったときは、会社に対し、損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。
また、役員等がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に対しても損害賠償責任を負います(同法429条1項)。
会社法には、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。」と定められおり(355条)、取締役は法令遵守義務を負っているわけですが、
取締役が、何かしらの法令に違反した場合には、当然に、会社ないし第三者に対し任務懈怠責任を負うのかというのが、今回の問題です。
■最高裁平成12年7月7日判決(野村証券損失補填事件・否定)
この点、上記最高裁判例は、ここでいう「法令」とは、取締役を名あて人として、取締役が職務上遵守すべき義務に限らず、さらに、商法その他の法令中の、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定もこれに含まれると判事しています。
その理由については、会社が法令を遵守すべきことは当然であるところ、取締役が、会社の業務執行を決定し、その執行に当たる立場にあるものであることからすれば、会社をして法令に違反させることのないようにするため、その職務遂行に際して会社を名あて人とする規定を遵守することもまた、取締役の会社に対する職務上の義務に属するというべきだからであるとしています。
もっとも、当該事案は、証券会社が一部の顧客に対し、損失補填をした事案であり、独占禁止法(不当な利益による顧客誘引)に違反するとはされましたが、当該行為が行われた当時、証券会社のみならず、監督当局である大蔵省や公正取引委員会も、損失補填が独占禁止法に違反するという見解を採っていなかったことから、取締役らが損失補填が独占禁止法に違反するという認識を有していないくても止むを得ない事情があり、過失がないとして、損害賠償責任を否定しています。
■知財高裁平成23年6月23日判決(不正競争防止法違反・肯定)
他社に対し、営業誹謗行為を行ったことにつき、会社の行為は不正競争(不正競争防止法2条1項14号)に該当するものであるところ、会社の代表取締役は、会社の代表者としての任務に反して、自ら上記不正競争を行ったのであるから、会社法429条1項の規定により。他社に発生した損害を賠償する責任があるというべきであると判示しています。
■大阪地裁平成21年1月15日判決(労働基準法違反・肯定)
別件判決で認められた割増賃金の支払を受けていない労働者らが、当時の代表取締役、取締役、監査役に対し行った割増賃金相当額等の損害賠償請求につき、
取締役及び監査役には会社に対する善管注意義務ないし忠実義務として会社に労働基準法37条を遵守させ被用者に対し割増賃金を支払わせる義務があるにもかかわらず、当該代表取締役らは悪意又は重過失によりこの任務を怠ったのであり、
この任務懈怠と当該労働者らが被った損害の間には相当因果関係が認められるとして、
平成17年改正前の商法266条の3(会社法280条1項)に基づき割増賃金相当額と遅延損害金の限度で労働者らの請求を認めています。
■大阪地裁平成17年12月8日判決(商標法・否定)
インターネットのウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして登録商標と類似する標章を記載し、その結果、検索サイトにおいて、トップページの説明として、登録商標と類似する標章が表示されていた事案において、商標権侵害を肯定しつつ、
一般に、商標について、その登録の事実が、特許電子図書館の商標検索のサイトを利用することにより、容易に検索可能であるとしても、その事実自体が一般に広く知られているとも、標章を使用する際にはこれを調査するのが当然とされているとも認められないから、商標実務を業としているものでもない取締役において、原告主張の方法により各商標が登録されているか否かを確認しなかったからといって、重過失があったとまでいうことはできないとして、取締役の対第三者責任を否定しています。
■東京地裁平成8年6月20日判決(関税法、外為法違反・肯定)
ジェット戦闘機に用いられる加速度計・ジャイロスコープ及びミサイルの部分品を関税法・(外為法)所定の各手続きを経ないで不正に売却・輸出したことが取締役の善管注意義務・忠実義務に違反する行為であり、これにより罰金・制裁金の支払いのほか売上高の減少・棚卸資産の廃棄等の損害を生じさせたとして、株主が、取締役らに対し、株主代表訴訟により損害賠償の請求をした事案です。
関税法及び外国為替管理法に違反する不正取引・不正輸出について、取締役がその事実を認識しながら支持・承認したものについては、取締役の善管注意義務・忠実義務に違反するとされました。
他方、一部の取引については、取締役会の決裁事項や報告事項になっていなかった上に、国内取引の形態をとり、製品が加速度計・ジャイロスコープであることや最終仕向地がイランであることが判らないような方法で、従業員らにより秘密裡に進められていた等の事情の下で、取締役がその事実に気付かなかったとしても、取締役の善管注意義務・忠実義務に違反するとはいえないと判示されています。
■東京地裁平成6年12月22日判決(贈賄行為・肯定)
取締役が行った贈賄行為について、株主代表訴訟が提起された事案について、次のように判示しています。
とりわけ贈賄のような反社会性の強い刑法上の犯罪を営業の手段とするようなことがおよそ許されるべきでないのは当然である。それにより会社に利益がもたらされるとか、慣習化し同業者がやっているため贈賄をしないと仕事をとれないおそれがあるといった理由で、営業活動としての贈賄行為を正当化し得るものではない。
したがって、贈賄行為は、たとえ会社の業績の向上に役立ち、会社のための営業活動の一環であるとの意識の下に行われたものであったとしても、定款の目的の範囲内の行為と認める余地はなく、取締役の正当な業務執行権限を逸脱するものであり、かつ、贈賄行為を禁ずる刑法規範は、取締役が業務を執行するに当たり従うべき法規の一環をなすものとして、商法266条1項5号の「法令」に当たるというべきである。
そうすると、被告の贈賄行為は、それが同時に政治資金規正法に違反するかどうかにかかわらず、法令及び定款に違反する行為として、会社に対する損害賠償責任を生じさせることになる。
■大阪地裁平成12年9月20日判決(外国の法令・肯定)
大和銀行ニューヨーク支店において、同行の行員が、10年以上の間、同行に無断かつ簿外で米国財務省証券の取引を行って約11億ドルの損失を出し、その損失を隠ぺいするために顧客、大和銀行所有の財務省証券を無断かつ簿外で売却して、大和銀行に約11億ドルの損害が発生したことを米国当局に隠匿していたなどとして、米国において、刑事訴追を受け、罰金3億4000万ドルを支払った損害を、同行に賠償するよう求めた株主代表訴訟の事案です。
外国法令にしたがうことは、取締役の善管注意義務の内容をなし、不正な取引の事実を知りながら、米国法が要求する当局への届出をしなかった取締役及び届け出るように他の取締役に働きかけなかった取締役に、善管注意義務違反の責任が認められています。
■まとめ
以上かすると、取締役が法令違反による任務懈怠責任に基づき、会社や第三者に対し、損害賠償責任を負うのは、法令違反をしただけでなく、法令違反になることを認識していた(過失はおろか故意があったような)場合と考えられます。
-
2021.06.17
【損害賠償】営業権侵害における不法行為の成否

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
営業活動が許される自由競争の範囲を逸脱した違法な行為については、不法競争防止法において「不正競争」として規制されています。
それでは、不法競争防止法の定める「不正競争」に該当しない行為についても、不法行為(民法709条)にあたるとして、同条に基づく損害賠償請求をすることができるでしょうか?
■ 営業権とは?
営業権ないし営業上の利益とは、権利として保護される範囲が固定されたものではありませんし、絶対的・排他的性質をもつ権利ではありません。
営業権が権利として保護すべきか否かは、競業者の営業の自由(営業権)、職業選択の自由、その他の権利との衡量をする必要があります。
■ 最高裁平成23年12月8日判決(北朝鮮映画事件)
この問題を考えるにあたって、営業権の問題ではなく、著作権に関するものですが、著作権法に定める著作物に該当しない著作物の利用行為について、原則的に、不法行為の成立を否定した最高裁平成23年12月8日判決(北朝鮮映画事件)が参考になります。同判決は次のように判示しています。
著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。
同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって、ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。
したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない。
■ 知財高裁平成24年8月8日判決
また、知財高裁平成24年8月8日判決は、不正競争防止法も、事業者間の公正な競争等を確保するため不正競争行為の発生原因、内容、範囲等を定め、周知商品等表示について混同を惹起する行為の限界を明らかにしており、ある行為が不正競争行為に該当しないものである場合、商品等表示を独占的に利用する権利は、原則として法的保護の対象とはならないとし、不正競争防止法が規律の対象とする周知商品等表示の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である旨判示しています。
■ 不正競争防止法が定める「不正競争」
不正競争防止法第2条1項に定められている「不正競争」は限定列挙であり、例示列挙ではありません。
同法を制定するにあたり、利害関係のある当事者各層の権利・利益、公共の利益等を総合考慮して、法規制の対象とする行為と、法規制の対象としない行為とを切り分けて判断したはずです。
すると、同法の定めが不正競争法秩序のもとでの競業行為に対する価値判断としては最終的であり、「不正競争」に該当しない行為については、法的に積極的に許容されていると考えられます(潮見佳男『不法行為法Ⅰ〔第2版〕』参照)。
■ 結論
以上から、不法競争防止法の定める「不正競争」に該当しない行為については、不法行為(民法709条)は成立せず、同条に基づく損害賠償請求もできないと考えられます。
-
2021.06.03
【企業法務】会社の役員等に対する責任追及訴訟の手続き

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(役員等)が、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(会社法423条1項)、会社が役員等に対し、その責任を追求する訴訟を提起する場合には、通常の訴訟とは異なる手続きが必要となります。
令和3年3月1日施行の改正会社法により改正がなされた点もありますので、うっかり手続ミスをしないように、今回は会社が役員等に対し責任追及をする訴えを提起する場合の手続き等について、説明させていただきます。
なお、今回は株主代表訴訟については対象外とさせていただきます。
■責任追及訴訟において会社を代表する者
取締役の責任を追及する訴えについては、監査役が会社を代表します(386条1項1号)。
ただし、業務監査権限を有する監査役が置かれていない会社では代表取締役が会社を代表します。
また、委員会設置会社では、監査委員(訴えの相手方となる場合を除く)が会社を代表します(408条3項1号)。
■訴えの管轄
責任追及等の訴えは、株式会社(または株式交換等完全子会社)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属しますので、それ以外の裁判所に訴訟提起することはできません(848条)。
■公告または株主への通知
株式会社は、責任追及の訴えを提起したときは、遅滞なく、その旨を公告し、または株主に通知しなければなりません(849条5項)。
株式会社が、株主から、責任追及の訴えを提起したとして、訴訟告知を受けたときも同様です。
ただし、公開会社でない株式会社の場合は、株主への通知で足ります(同条9項)。
これらは、会社と取締役との馴れ合い訴訟を防止するとともに、和解が適切に行われることを担保するものです。
■訴訟参加
原則として、株主又は株式会社は、共同訴訟人として、または当事者の一方を補助するため、責任追及訴訟に参加することができます(849条1項本文)。
■和解をする場合
令和3年3月1日施行の改正会社法により、株式会社等が、その取締役(監査等委員及び監査委員を除く)や元取締役の責任を追及する訴訟において和解をする場合には、次の者の同意を得なければならなくなりました(849条の2)。
・監査役設置会社の場合、監査役(監査役が二人以上の場合には、各監査役)
・監査等委員会設置会社の場合、各監査等委員
・指名委員会等設置会社の場合、各監査委員 -
2021.05.26
【取締役の解任】職務不適任による「正当な理由」が認められるか?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
取締役などの役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。理由のいかんを問いません。
ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができます(同条2項)。
そのため、取締役を解任した場合、会社は、取締役から、損害賠償請求されることが多く、取締役の解任に「正当な理由」があるか否かは、重要な争点となります。
特に職務への不適任を理由とする場合には、「正当な理由」が認められるケースと認められないケースとに分かれ、判断が難しいことががありますので、今回は、その裁判例について紹介させていただきます。
■正当な理由とは?
東京地裁平成29年1月26日判決は、会社法339条2項の「正当な理由」の内容について、会社・株主の利益と解任の対象である役員の利益の調和の観点から決せられるべきものであり、具体的には、会社において、当該役員に役員としての職務執行をゆだねることができないと判断することもやむをえない客観的な事情があることをいうと判示しています。
また、東京地裁平成25年5月30日判決は、正当な理由が存在する場合とは、当該取締役の職務の執行に当たり、
①不正の行為や定款又は法令に違反する行為があった場合
②取締役が経営に失敗して会社に損害を与えた場合
③当該取締役の経営能力の不足により客観的な状況から判断して将来的に会社に損害を与える可能性が高い場合に認められるとし,単に株主と取締役との間で経営方針が異なるというだけでは正当な理由は認められないとしています。
■解任事由の告知の要否・会社の認識
役員の解任について定める会社法339条において、役員を解任するに当たり、会社の故意過失や当該役員への解任事由の告知は要件とされていない上、「正当な理由」を会社が認識していた事情に限定する旨の規定も存在しないことからすれば、正当な理由の根拠となる事情は、解任時点で客観的に存在していれば足り、会社代表者らが認識していることまで要しないとされています(東京地裁平成30年3月29日判決)。
■正当な理由を認めた裁判例
(東京地裁平成30年3月29日判決)
同判決は、以下の事実を認定し、それぞれが単独で解任の正当な理由になるとまではいえないものの、これらを総合勘案すれば、当該事業について取締役会決議などがされていることなどを踏まえても、取締役として著しく不適任であるとされてもやむをえないといえ、解任には正当な理由があると判断しました。
・企業グループ全体の経営に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事業を企図し実行したこと
・当該事業の実施を決定する取締役会及び当該事業への追加投資を承認する稟議において虚偽説明をしたこと
・子会社に対し虚偽説明を伴って当該事業に係る販売データの購入圧力をかけたこと
・グループ役職員等の電子メールに含まれる情報を不正に取得したこと解任された取締役が企画・実行した事業は、小売店舗の店頭で商品陳列状況を無断で撮影し、その画像をマーケティングに有用な情報にデータ化した上で販売するというものであり、店舗内で隠し撮りをする点で違法と判断される危険性があり、かつ、小売業者との信頼関係を破壊し、グループ全体の経営に悪影響を及ぼしかねないおそれのあるものであって、解任された取締役には、業務を遂行するに当たって要求される手続を軽視する姿勢が顕著に見られ、コンプライアンス意識も欠如していると判示されています。
(東京地裁平成18年8月30日判決)
取締役は、会社代表者から支店への異動を打診された直後から、会社代表者及び副社長の自己に対する人事異動の打診行為について批判し、それにとどまらず、その後は会社及び代表者の数々の問題点、疑問点を挙げ連ねて会社批判を繰り返し、上記打診がある前には全く見受けられなかったところの会社への敵対行動に出ていること、当該取締役は既に会社の情報を訴週刊誌の記者にまで情報提供しているがその必要性はなかったと思われること、会社の内部的な問題は、これをスキャンダルとして週刊誌等に掲載されれば会社の信用を損ね経営に支障を来すことは容易に予期できたものと考えられることなどからすると、当該取締役の行動は、会社の是正というよりも意に沿わない人事異動の打診があったことを契機とした会社と会社代表者への糾弾を中心とする報復措置と受け止められても仕方のないものであったと評価でき、むしろ業務執行を阻害するものというべきであり、現実に会社あるいは会社代表者の信用は損なわれ、取引及び収益の減少も相当程度生じていることから、その解任には正当事由があると判示しています。
(広島地裁平成6年11月29日判決)
正当事由には、経営判断の誤りによって会社に損害を与えた場合も含まれるものというべきであるとし、会社の売上が毎年着実に伸びており、業務の特殊性からして、リスクの大きい株式取引に手を出さなければならない緊急性がなかったにもかかわらず、代表取締役が多額の株式の信用取引や投機性の高い取引を独断で行い、結果的に多額の損失を会社に与えたものであって、これは、代表取締役としての経営判断の誤りと評価されても止むを得ないものであると判示し、解任について正当事由を認めています。
もっとも、同判決は、当該取締役が、脳血栓で二か月もの入院加療を要する状態になり、退院後も長期的な通院治療を必要とし、意識状態は普通であるものの、会話能力や筆記能力が相当程度低下しているのであって、かような状況で取締役として通常どおりの職務の遂行が可能であるとは考え難いというべきことや、当該取締役が、退院してからも、出社して自ら経営者としての職責を全うする態度を見せておらず、却って他の監査役や取締役らの責任追及に対してひたすら弁解に終始するばかりであり、自己の解任が議題になっている株主総会にも出席せず、職務の遂行に対する意欲も失われていたこともあわせて認定して、正当事由を認めたものであり、経営判断の誤りのみによって、正当事由を認めたものではありません。
■正当な理由を否定した裁判例
(東京地裁平成29年1月26日判決)
解任された取締役の次の行為について、各項目ごとに独立して、「正当な理由」があるということはできないと判示しています。
・受嘱承認手続に係る規範の不遵守等
・グループの方針の不遵守
・研修義務不履行者への措置・処分の未策定
・離職者数の多さ
・規程整備への非協力
・業績目標の未達
・アドバイザリー業務体制の検討における非協調姿勢
・独断での新たなQRMプロセスの提案
・パートナーシップの検討における姿勢
・提供を受けたサービスの対価の支払懈怠また、当該取締役の行為や対応が、グループ子会社の代表取締役(社長)の行為として問題のあるものであり、これらを総合すると、代表取締役としての適性に疑念を生じさせる面があることは否定できないとしつつ、他方、業績が低迷して営業力も低い会社の収益を改善し規模を拡大することを目的として招聘されたものであり、当該取締役自身、そのことを十分認識して代表取締役(社長)に就任したものであること、実際、会社の損益は、黒字に転じ、在任中は一応黒字を維持しており、従業員数も、毎年約100人ないし150人ずつ増加していることが認められ、これらの事実を総合すれば、当該取締役が代表取締役として著しく不適任であると断ずることはできず、解任について「正当な理由」があるとまでいうこともできないと判示しています。
(東京地裁平成11年12月24日判決)
正当事由の有無につき検討するに、解任された取締役は、従業員を指導する際、余りにも激しく叱責し、店長や従業員から不満をかうようなことがあったり、会社代表者に苦情を述べる従業員がいたり、各店長から会社代表者に上申書が提出されるようなことがあったり、役員室に内側から施錠して一人役員室にこもって執務することがあるなど従業員らの信頼が十分でなく、当該取締役に適切さを欠く業務執行の態様があったことは否定できないと判示しています。
しかし、従業員に対する叱責に関しては、当該取締役が自己の職務に熱心なあまり、その言動にいきすぎた面があったとも評価できなくもなく、この事実をもって職務への著しい不適任ということはできないし、当該取締役に対する従業員らからの信頼が十分でないことや業務執行の態様にやや不適切な面があったことが、結果として会社の経営にどのような影響を与えたのかも不明であり、業績の悪化、信用失墜等を含めた経営上の支障が会社に生じたことを認めるに足りる証拠もなとして、著しい職務への不適任があったということはできず、正当事由は認められないと判示しています。
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2024年 (2)
-
2022年 (2)
-
2021年 (7)
-
2015年 (2)
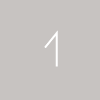
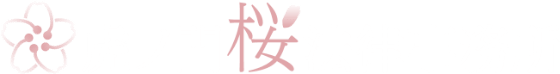
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)