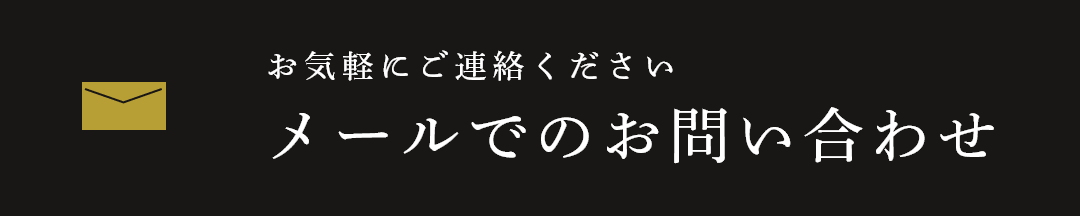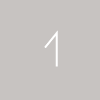借地権譲渡や増改築について、こんな問題はありませんか?

- 木造建物をコンクリート造りに建て替えたいけど、地主が承諾してくれない。
- 建物を増改築したいけど、地主が承諾してくれない。
- 建物を譲渡したいけど、地主が承諾してくれない。
- 建物を競落したけど、借地権の譲受について、地主が承諾してくれない。
- 第三者に譲渡・転貸されるくらいなら、地主である私が建物を借地権ごと買い取りたい(介入権の行使)。
借地非訟とは?
以上のような場合に、裁判所から、地主(土地所有者)の承諾に代わる許可をもらったり、地主の建物の優先的な買取を認めてもらう手続きです。詳しくは、次をご参照ください。
借地上の建物を第三者に譲渡したいのですが、地主が承諾しません。どうしたら、いいですか?
借地上の建物を増改築するには、地主の承諾が必要ですか?承諾が得られない場合には、どうすればよいですか?
当事務所では、顧問先である複数の不動産会社から、継続的に多数の借地非訟事件のご依頼を受けており、借地権譲渡や借地非訟の手続に精通しております。
借地非訟に関する5つのポイント
Point1申立権者
借地権譲渡許可の申立をできるのは、借地権を譲り渡そうとしている借地権者です。譲受予定者が申し立てることはできません。また、建物が共有であった場合、建物の共有者のうち一人だけの申立ても認めれています(東京地裁昭和42年10月18日決定)。
Point2申立の時期
建物及び借地権を譲渡する前に行わなければならず、建物を譲渡した後の申立は認められていません。
ただし、遺贈の場合には、遺贈の効力発生前に借地権譲渡許可の申立を要求するのは、その性質上極めて不当であることから、遺贈の効力が発生した後に、その相続人または遺言執行者が建物の引渡しや所有権移転登記に先立って、申立をすれば足りるとされています。
Point3借地非訟手続の流れ
以下の流れで進行し、多くの事件は概ね1年以内に終わっています。
①借地権者(申立人)が、裁判所(東京地裁の場合、民事第22部)に申立書を提出します。
②第1回審問期日を開かれ、裁判所が、当事者(申立人及び相手方)から意見を聴きます(必要に応じて第2回、第3回と期日が重ねられます。)。
③裁判所が、鑑定委員会に、許可の可否、承諾料額、賃料額、建物及び借地権価格等について意見を求めます。
④当事者立ち会いの下、鑑定委員会による現地調査が行われます。
⑤鑑定委員会が、裁判所に意見書を提出し、裁判所から、当事者に対し、意見書が送付されます。
⑥裁判所が、鑑定委員会の意見について、当事者から意見を聴き、条件に折り合いがつけば、和解が成立します。
⑦和解が成立しない場合、裁判所が、決定書を作成し、当事者に送付します。
Point4承諾料の相場
①借地条件変更(木造建物をコンクリート造に建て直すような場合)
更地価格の10%程度
②増改築
更地価格の3〜5%程度
③譲渡・転貸
借地権価格の10%程度
Point5借地非訟手続にかかる費用
弁護士に依頼する場合、弁護士費用
裁判所へ納付する申立手数料(土地の固定資産評価額を基準として算定されます。)、郵便切手代、その他実費
鑑定委員に要する費用は、国が負担するので、当事者は費用が掛かりません。
弁護士費用
①交渉及び非訟手続(第一審)の弁護士費用を含みます。
②上訴の際は、追加で上記の2分の1の着手金をいただきます。
③出廷費用や日当はかかりません(ただし、往復2時間を超える遠方の場合を除きます)。
④原則として、一括でのお支払いとなりますが、分割払いのご相談にも応じております。
⑤別途、実費(印紙代、切手代、交通費、コピー代等)が生じます。
⑥上記費用は、税込表示です。
■顧問契約締結による、特別割引の対象となります。
■地域貢献の一環として、港区在住・在勤の方限定で、特別に弁護士費用の優待をしております。詳細はお問い合わせください。
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 賃貸人側 | 44万円 | 承諾料の11% (最低44万円) |
| 賃貸人側 (介入権行使する場合) |
44万円 | 借地権価格の5.5% (最低44万円) |
| 賃借人側 | 44万円 | 借地権価格の5.5% (最低44万円) |
| 賃借人側 (介入権行使された場合) |
44万円 | 介入権価格の11% (最低44万円) |
借地非訟において、地主側からよくある主張とこれに対する反論
Q&A
Q
借地権の残存期間が短い場合、借地非訟の申立は認められますか?
A
地主から期間満了により借地契約を終了させるためには、正当事由の具備が必要であるところ、正当事由が認められず、更新が確実である場合には、借地権譲渡等を認めても、地主に不利ではありませんので、申立が認められるでしょう。
これに対し、更新されるか否かが明らかとはいえない場合には、借地人が誰かによって正当事由の判断に影響があり、地主にとって不利になるおそれがありますので、残存期間が短い場合には、認められないことが多いでしょう。残存期間が短いか否かは2〜3年程度が一応の目安とされ、裁判例では、申立時からの残存期間が1年未満の場合に、申立を棄却した裁判例が存在します。
Q
賃貸借契約書がない場合でも、借地非訟の申立や許可は認められますか?
A
相続がなされ、土地の賃貸借契約書が見当たらないということも往々にしてありますが、契約書がない場合でも、借地非訟の申立はできますし、要件を満たせば、許可は認められます。このような場合、建物の登記簿に基づき、建物の建築時期から契約の開始時期を、建物の種類・構造から堅固・非堅固建物所有目的をそれぞれ推測したり、預金通帳や領収書に基づき、地代を主張したりします。また、相手方(地主)が契約書を持っていれば、それを書証として提出してくるでしょう。
Q
借地権の一部を譲渡することができますか?
A
借地非訟において、借地権の一部譲渡が直ちに不適法になるわけではありません。しかし、それが地主にとって不利になるおそれがある場合には、一部譲渡の申立は認められず、棄却されます。例えば、残地だけでは、接道条件を満たさず建物を建てることができなくなったり、土地が狭くなり一般的な利用収益ができなくなったりするような場合です。
これに対し、一部譲渡を認めたものとして、借地上の2つの建物とその敷地の借地権を分割して、別々の人物に譲渡する申し立てを認めた裁判例(昭和46年6月16日判決)があります。この裁判例では、分割により借地が不整形になるが、譲受人は、隣接地を同じ借地権設定者から賃借しており、一括としてみる限り、分割が借地権設定者に不利にならないことを理由としています。
Q
借地権譲渡許可手続きにおいて考慮される「借地に関する従前の経過」とは?
A
借地権の譲渡を認めるか否かは、「借地に関する従前の経過」等を考慮して判断されます(借地借家法第19条2項)。
この点、まず借地権設定時に権利金が授受されているか否かが問題となります。権利金が授受され、それが借地権譲渡の承諾料の対価としての趣旨を含むものであれば、申立を許容する方向に働きます。
次に、借地権の設定をした事情として、当事者間に、親戚関係があったり、法人と役員といった特殊な関係があり、かつ賃料が近隣に比べ極めて低廉であるというような事情から、その賃借人に限って貸すということが当事者間で了解されていたような場合には、譲渡が認められないこともあり得ます。もっとも、地主には介入権行使が認められている一方、借地人は投下資本の回収ができなくなるおそれがありますので、申立を棄却する場合は慎重に判断すべきです。
Q
地主による介入権行使は、必ず認められますか?
A
借地権者が第三者に借地権付建物を譲渡したいと考えるのは、建物や借地権取得に要した資本を回収するため、金銭化する目的である場合がほとんどですから、譲渡先が地主かそれ以外の第三者かはそれほど関心がありません。したがって、ほとんどの場合には、介入権行使が認めれます。
しかし、借地権者が投下資本の回収を目的とするわけではなく、例えば、借地上の建物について、個人事業を営んでいたものを法人成りしたり、親族に対し譲渡をするなど、借地権者側が使用する必要するため、譲渡許可の申立をしているような場合には、介入権の行使が認められない可能性が高いでしょう。
Q
介入権を行使するにあたり、建物に抵当権の設定登記等がある場合、どうなりますか?
A
近時の実務では、建物の所有者である借地権者に、担保権の設定登記や所有権移転に関する仮登記など、所有権の負担となる一切の登記の末梢登記をさせます。その上で、介入権を行使した地主から代金の支払いを受けるのと引き換えに、建物の所有権移転登記及び建物の引き渡しをする運用がなされています。
Q
介入権を行使するにあたり、借家人がいる場合は、どうなりますか?
A
借地上の建物がアパートで賃貸されており、借家人がいる場合があります。通常、借家人は建物の引渡を受け、対抗要件を備えていますので(借地借家法第31条1項)、このような場合には、借家契約における賃貸人の地位が、介入権を行使し、代金の支払いをした地主に承継されます。借地人の方で、借家人を退去させなければいけないわけではありません。借家人がいる場合には、介入権を行使した場合の対価の算出において、借家権価格を控除するのが相当とされています。
これに対し、建物を占有している第三者に対抗しうる占有権原がない場合には、借地権者の方で、第三者を退去させて、代金の支払いと引き換えに、建物の引渡及び所有権移転登記手続きをするのを命じるのが妥当でしょう。もっとも、第三者が退去する見込みがない場合には、第三者がいる状態のまま引き渡しをし、不法占拠者を退去される費用等の負担を考慮し、介入権行使の対価を減額することも考えられます。
Q
借地権設定者が複数の場合、その全員を相手方として借地非訟の申し立てをする必要がありますか?
A
譲渡の承諾は、管理行為と解されますので(東京地裁平成8年9月18日判決)、借地の共有持分の過半数を有する者から、承諾を得られれば法的に有効です(民法第252条本文)。
しかし、借地権設定者による承諾行為そのものは全体として一つであり、共有者全員の意向を確認するのが手続き上相当であることから、借地非訟手続では、共有者全員を相手方として、申立をする必要があります。既に、借地権設定者の一部から譲渡の承諾を得ていたとしても、それが共有持分の過半数に達していない場合には、既に承諾を得ている者も含めて、借地権設定者全員を相手方として申立をする必要があります。
Q
借地権譲渡許可の申立とともに、借地条件変更や、増改築許可、建物再築許可などを同時に申立することはできますか?
A
できます。
賃借権譲渡許可が申し立てられた事案で、譲受予定者が譲受建物をそのまま使用するのではなく、非堅固建物所有を目的とする借地契約において、堅固建物の建築を計画しているような場合には、別途、借地条件変更許可の申立をする必要がありますが、同時申立ては借地権設定者にも不利益でなく、手続経済上合理的であるとして認められています(東京地裁昭和48年3月6日決定)。
また、増改築許可の同時申立についても、増改築の主体が問題ではなく、具体的な増改築計画が土地の利用上相当であるか否かが問題となるものであり、同時申立は、借地権設定者にも不利益でなく、かえって手続経済上便利であるとして認められています(東京地裁昭和48年3月12日決定)。
ただし、借地権設定者から介入権が行使され、それが適法なものとして認められた場合には、これら申立については判断が示されないことになります(申立は失効します)。
Q
地主の承諾を必要とする増改築とはどのようなことですか?
A
一般的に借地契約には、建物の増改築をする場合には、賃貸人の承諾を必要とする旨の増改築制限特約が存在しますが、ここにいう「増築」とは、①同一棟で床面積を増加させる行為や、②同一敷地内に別棟の建物を建築する行為のうち、改築に該当しないもののことです。他方、「改築」とは、建物を建て替えることをいい、同一場所に従前の資材とは異なる資材を使用して建築する場合(狭義の改築)のほか、従前の資材を使用する場合(再築)、同一借地内で建て直す場合(移築)が含まれます。さらに、大修繕も、建物の存続期間に影響を及ぼす程度の場合、例えば、建物の柱・土台・壁・床・梁・屋根・階段など主要構造部の取替は増改築にあたると解されています。
Q
増改築予定建物は、どのように特定する必要がありますか?
A
増改築許可の申立をするには、具体的にどのような増改築をするのか、その内容を特定する必要があります。実務では、増改築予定建物の種類・構造・床面積のわかる図面、すなわち配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上仕様書の提出が求められます。
Q
増改築予定建物を変更することはできますか?
A
申立後に、増改築の内容が変更されることもあることから、借地非訟の手続中に、増改築の内容を変更することも認められています(申立ての趣旨の変更として扱われます)。これに対し、決定後は、原則として、裁判の主文で特定された建物とは異なる建物を増改築することは許されません。もっとも、若干の差異が生じても裁判の趣旨には反しないと解されています。階高が変わったが、総床面積がほとんど変わらない建物を建築した事案において、同様の判断をした裁判例が存在します(東京高裁昭和53年7月4日決定)。
Q
離婚に伴う財産分与において、地主に無断で借地権を譲渡すると借地契約を解除されますか?
A
最高裁昭和44年4月24日判決は、夫が借地人であり、妻が借地上に建物を所有して同棲していたところ、離婚に伴い、夫が妻に借地権を譲渡した事案につき、地主の承諾がなくても、背信行為とは認められない特段の事由があるとして、解除を否定しています。
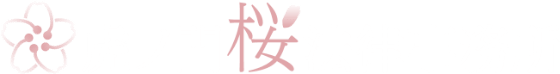
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)