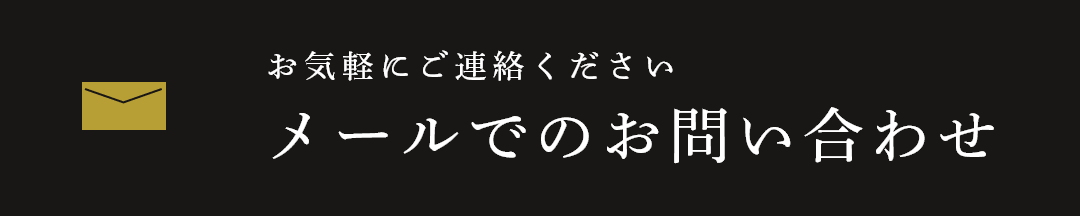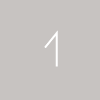労働問題について、こんなお悩みはありませんか?

- 【残業代請求】管理職や従業員から残業代を請求されたが、どのように対応すればよいか。
- 【退職勧奨】業務成績や勤務態度が悪い従業員を辞めさせたいがどうすればよいか。
- 【メンタルヘルス】精神的不調をきたした従業員に対して、どのように対応したらよいか。
- 【ハラスメント】パワハラ・セクハラを理由に、上司と会社が損害賠償請求されたが、どうすればよいか。
- 【派遣労働】派遣社員を受け入れたいが、気をつけるべき点は
労働問題・労務管理のポイント
Point1みなし割増賃金制
時間外労働が常態化している職場においては、労働基準法に定める計算方法による残業代を支払う代わりに、別の方法(年俸制、定額残業代制など)により手当を支給することが認められています。
定額の手当を支給している場合には、それが時間外手当に該当するものか否かが争うわれることが多いため、その趣旨を明確にしておくことが重要です。また、基本給に時間外手当が組み込まれている場合には、「基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ」割増賃金として認められます。
みなし割増賃金制を導入する際は、①最低賃金に抵触しないようにすること、②必ず就業規則や雇用契約書に定めること、③みなし残業時間を極端に長くしないこと、などに注意してください。
Point 2労働条件を変更する方法
個別の労働契約による変更
個々の労働者との合意により労働条件を労働者に不利益に変更することもできます。ただし、労働者が真に合意をしているかについて、慎重に確認する必要があります。また、労働者から合意を得られても、就業規則で定められた基準を下回る労働条件は無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準になります(労働契約法第12条)。
就業規則による変更
労働者と合意することなく、就業規則の変更により、労働条件を労働者にとって不利益に変更することは原則としてできません。ただし、例外的に、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の相当性、労働組合等との交渉の状況、その他の就業規則の変更に係る事情等を考慮して合理的な内容であり、かつ変更後の就業規則を労働者に周知させることによって、労働条件を労働者にとって不利益に変更することもできます(労働契約法第9、10条)。
労働協約による変更
労働協約は、使用者と組合との交渉・取引によって合意されるものであるため、合理的な内容であれば、労働条件を労働者にとって不利益に変更することもできます。もっとも、合理性の判断要素は、労働協約の内容について意見できた者が組合員であったか、非組合員であったかによって異なります。
Point3ハラスメント
使用者の責任
ハラスメントが不法行為責任(民法709条)の要件を満たす場合には、直接の行為者が被害者に対し損害賠償責任を負うことは当然ですが、会社も主に使用者責任(715条)を追及されます。また、職場環境を調整・保全する義務を怠ったとして、直接の不法行為責任(709条)や債務不履行責任(415条)を問われることがあります。
調査の注意点
ハラスメントの相談があった場合、まずは事実関係を確認する必要がありますが、被害者のプライバシー保護を優先すべきであり、被害者の同意なく、加害者や第三者へのヒアリングは控えるべきです。
加害者への対応
パワハラ、セクハラ、マタハラ等の加害者に対しては、事実関係を確認した上で、注意・指導を行うほか、異動を命じ、被害者が加害者と顔を合わせないよう配慮することが考えられます。また、ハラスメント防止指針に基づき、再発防止研修を実施することも有用です。
さらに、一般的に、ハラスメントは就業規則で懲戒事由とされており、懲戒処分を行うことも考えられますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒処分は権利濫用で無効となりますので(労働契約法第15条)、注意が必要です。
会社が、ハラスメント被害者に対して、使用者責任に基づき損害賠償した場合には、加害者に対し求償することが考えられますが、その範囲は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限定されます。
Point 4メンタルヘルス
予防対策
常時労働者50名以上を使用する事業主は、「ストレスチェック」や「面接指導」が義務付けられています(労安66条の10)。これに該当しない事業主に対しては、努力義務としてストレスチェックの制度が要請されています(同規則10条)。厚生労働省が公表している「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」をご参照ください。
休職制度
業務外の要因に基づくメンタルヘルスの不調により休職した場合、休職期間満了時までに復職できなければ解雇か退職となり、休職期間中も無給であることが多いです。これに対し、業務上の原因である場合、労災認定や休業補償等の対象となり、使用者は安全配慮義務違反を理由とする損害賠償責任を負うことがあります。また、この場合、休業中及び復職後30日間の解雇が原則として制限されます(労働基準法19条1項)。
労災認定・業務起因性の判断基準
一般的な基準としては、厚生労働省の新認定基準があり、発症のおおむね6か月前に精神障害を発症させるおそれのある業務による強度の心理的な負荷が認められること、業務以外の心理的負荷及び個人的要因によりその精神障害が発生したと認められないこと、が要件となります。
また、長時間労働による過重労働が認められる場合、メンタルヘルスの不調には業務起因性が肯定されやすい傾向にあります。
復職可否の判断
労働者が復職を希望する場合、主治医の診断書を提出するのが通常ですが、使用者はこの診断書だけで復職を認めなければいけないわけではありません。必要に応じて、主治医との面談、主治医からの情報提供を受けたり、産業医や人事部等と労働者を面談させて復職の可否を判断することになります。
復職後の業務
復職を認める診断書でも、一定期間は軽作業であることなどの条件が付されている場合には、会社の規模や業種なども考慮し、配置される可能性が現実的に認められれば、配置転換を認めて復職をさせるべきです(片山組事件。最高裁平成10年4月9日判決)。
Point 5安全配慮義務
使用者は、労働者の生命や身体等の安全を配慮しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負います(労働契約法第5条)。
業務起因性
業務と労働者の生命・身体等の損害の発生との間に相当因果関係が認められることが要件になりますが、例えば、うつ病の罹患や、それにより自殺に至った場合のように、業務上の疾病に罹患したとされる場合については、相当因果関係がはっきりさせず、争われることがあります。この点については、労災補償における業務上の認定に近い手法で判定されることが多いですが、労災補償が否定される場合でも、司法判断では相当因果関係が認められる場合があります。
精神障害についての業務起因性の認定に関しては、厚労省の通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23・12・26基発1226第1号)が参考になり、次の要件をすべて充たす場合には、当該精神障害は業務上のものと認められるとされています。
① 精神障害が業務との関連で発病する可能性のある一定の精神疾患(代表例として、うつ病や急性ストレス反応)であること。
② 発病前の概ね6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷および労働者側の要因により発病したとは認められないこと。
このうち、実務上、主に問題となるのは、②であり、上記認定基準には、具体的に心理的負荷の強度(弱・中・強)の例が具体的に示されており、例えば、酷いいじめや、精神障害発病の直前の連続した3か月間に月概ね100時間以上の時間外労働を行なったような場合(その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであれば)は「強」とされています。
過失相殺
労働者の落ち度、不注意のほか、基礎疾患や性格、心因的要素(脆弱性)を理由に、賠償額の減額が認められる場合があります。
Point 6退職勧奨の方法
退職勧奨が労働者の自発的な退職意思の形成を促す限度を超え、その手段及び方法が社会通念上不相当な場合には違法となります。そこで、対象者との面談において、退職勧奨の目的や、対象者の選定基準、対象者が選定された具体的な理由等を丁寧に説明し、退職を受諾した場合の条件を具体的に提示して説明をしてください。また、面談出席者の地位や人数、面談時間、面談の頻度も過大にならないようにし、録音されている可能性があることを念頭に言動に注意し、冷静な対応を心がけてください。
そして、業務改善が必要な労働者に対して、PIP(一定期間に、指導の一環として具体的な目標や行うべき行動を示唆し、面談を重ねながら改善を図るプロセス)を運用する際は、達成が極めて困難な課題を与えたり、労働者の経歴や実績を軽視した無意味で過小な課題を与えて実質的な退職勧奨をすることも違法となるおそれがあります。
労働者から退職勧奨には応じられないことを明確に伝えられた場合には、以後の退職勧奨は慎重に行う必要があります。
Point7 労働審判の流れ
労働審判は、使用者と個々の労働者との間の個別労働紛争を迅速に解決する手続きです。労働審判は、地方裁判所において、裁判官1名と労働審判員(労働者側1名、使用者側1名)の計3名で構成される労働審判委員会によって行われます。
労働審判の申立てがなされると、裁判所から相手方に対し呼出状が送付されますが、答弁書の提出期限はそれから約1か月後、第1回期日はその約1週間後、第2回期日が開かれる場合は、第1回期日の約2週間後に開かれるのが一般的です。手続きは非公開です。
労働審判は原則として3回の期日以内に決着することとされ、基本的事実関係の確認は第1回期日で審判官から事前提出した書面に基づく口頭の質問により、ほぼ終了しますので、十分準備して臨む必要があります。
労働審判では使用者側と労働者側がお互いに譲歩し、調停による解決を目指しますが、調停が成立しない場合には、審判が下されます。当事者が審判に不服があり、異議の申立てをすると、審判は効力を失い、自動的に訴訟手続きに移行します。
労働法に関する改正
- 【高齢者雇用】令和3年4月1日から施行される高齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業規則の確保が努力義務となります(70歳までの雇用を義務化するものではありません)。70歳までの定年引上げや、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度や社会貢献事業に従事できる制度の導入に努める必要があります。
- 【派遣労働】令和3年1月から施行された改正派遣法により、派遣先にも、派遣労働者から苦情の申し出を受けたときは、苦情の内容を派遣元に通知するとともに、派遣元との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図ることが義務付けられました。
Q&A
Q
管理監督者とは?
A
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいいます。管理監督者には、労働時間や休憩、休日に関する規定は適用されませんので(労働基準法第41条2号)、残業代請求も問題にはなりません。管理監督者は、自らの労働時間を自らの裁量で律することができ、地位に応じた高い待遇を受けていることから、労働時間の規制を適用するのは適当ではないからです。
管理監督者に該当するか否かは、肩書きのいかんにかかわらず、裁判例上、次の点が重要なポイントとされています。
①事業の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められているか。
②出退勤をはじめとする労働時間について裁量権があるか。
③一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金が支給されているか。
Q
経営が悪化したことを理由に採用内定を取り消すことはできますか?
A
採用内定は、始期付・解約留保権付・労働契約の成立と解されています。内定取消は、内定時に通知書等に定められる内定取消事由に基づくものですが、取消事由があれば必ず内定取消できるわけではなく、その行使は、客観的に合理的で、社会通念上相当な場合に認められます。
内定後の経営悪化を理由に、内定取り消しをする場合は、整理解雇に準じた検討をする必要がありますが、現従業員の解雇よりも、採用内定者の内定取消を優先することは、人選基準の合理性が認められると考えられます。
これに対し、採用内定時に既に経営悪化が判明していた場合には、それを織り込んで内定を出しているので、それを理由として内定取消をすることは原則として認められないでしょう。
Q
労働時間を裏付ける証拠として、どのようなものがありますか?
A
タイムカードのほか、職場のビルの入退館記録、パソコンのログイン・ログオフの時間、業務日誌、パスモやスイカなど職場最寄り駅の改札を通った履歴などが考えられます。労働者自らがつけていた労働時間に関するメモも一応証拠にはなりますが、客観的な信ぴょう性は劣るでしょう。厚生労働省が平成29年1月20日に公表したガイドラインでは、タイムカードなど客観的な記録がない場合には、使用者自らが労働者の始業・就業時間を現認したり、自己申告制の場合には労働時間の実態を正しく記録するよう労働者に十分説明したり、必要に応じて実態調査を実施して、労働時間の補正を行うことが求められています。なお、使用者側には、勤務時間の管理、労働時間の記録に書類を関する書類を3年間保存することが要請されています(労働基準法第109条)。
Q
指示していないのに、勝手に残業したにもかかわらず、残業代を支払う必要がありますか?
A
労働時間といえるか否かは、客観的にみて、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価されるか否かによって判断され、単に残業を指示していなかったというだけでは、残業代支払い義務は免れません。使用者には、労働者の管理時間を適正に把握することが求められていますので、残業をしなければ処理できないほどの過重な業務を負わせないようにしたり、従業員が遅くまで会社に残っていたら、帰宅させたりするなど、適切な労務管理をする必要があります。
Q
懲戒処分を有効に行うためにはどのような点に注意する必要がありますか?
A
懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用で無効となります(労働契約法第15条)。そのため、懲戒処分を有効に行うためには、次の要素を充たす必要があります。
① 就業規則等に懲戒処分の根拠規定があること
② 労働者の行為が懲戒事由に該当すること
③ 懲戒事由と懲戒処分の重さが均衡していること
④ 他の同種事案における処分と均衡していること
⑤ 懲戒処分を行う手続きが適正に行われていること
Q
労働者に対し、その地位や能力、経験に照らして、程度の低い業務を行わせることは問題がありますか?
A
使用者は、労働者の配置及び業務の割当て等について、業務上の合理性に基づく裁量権を有します。しかしながら、労働者に労務提供の意思及び能力があるにもかかわらず、使用者が業務を与えず、又は、その地位、能力及び経験に照らして、これらとかけ離れた程度の低い業務にしか従事させない状態を継続させることは、業務上の合理性があるのでなければ許されません。
そして、このような状態の継続は、労働者に対し、自らが使用者から必要とされていないという無力感を与え、他の労働者との関係においても劣等感や恥辱感を生じさせる危険性が高いといえ、そのような状態に置かれた期間及び具体的な状況等次第で、労働者に心理的負荷を与えたと評価されるおそれがあるので、注意が必要です(札幌地裁令和1年6月19日判決)。
Q
過重労働にならないようにするには、どのような点に注意すればよいですか?
A
過重労働の目安は第一に労働時間ですので、従業員の労働時間を的確に把握し、平均的な労働時間が月80時間を超えている場合には、他の従業員への配分や応援人員の補充など仕事の調整をすべきです。次に、従業員の慣れていない業務や、緊急性があったり、納期が迫っていてストレスが大きい業務の場合も、配慮が必要となります。
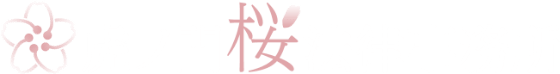
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)